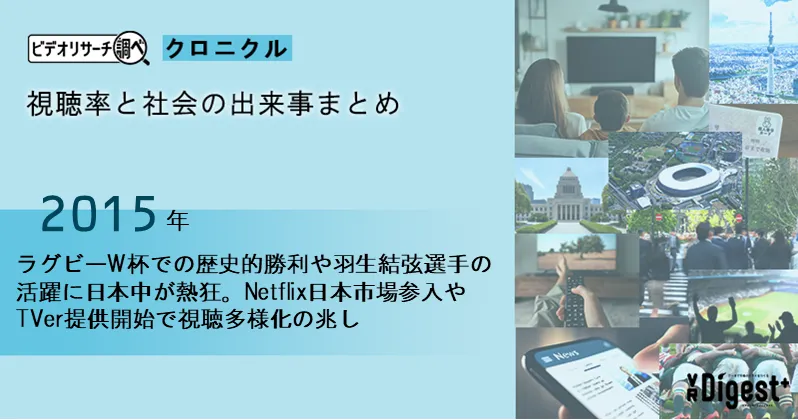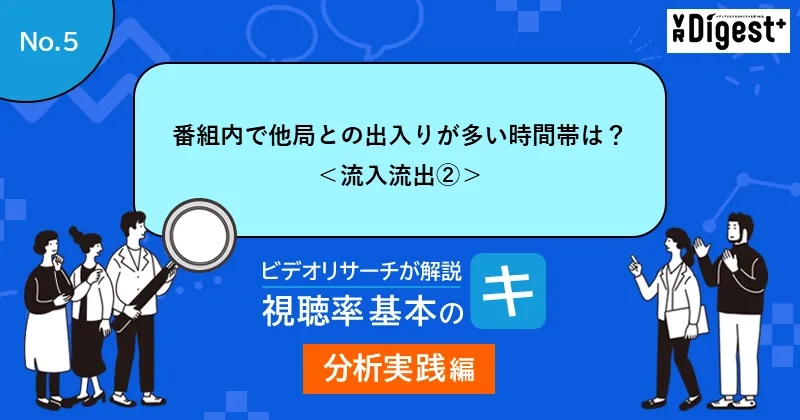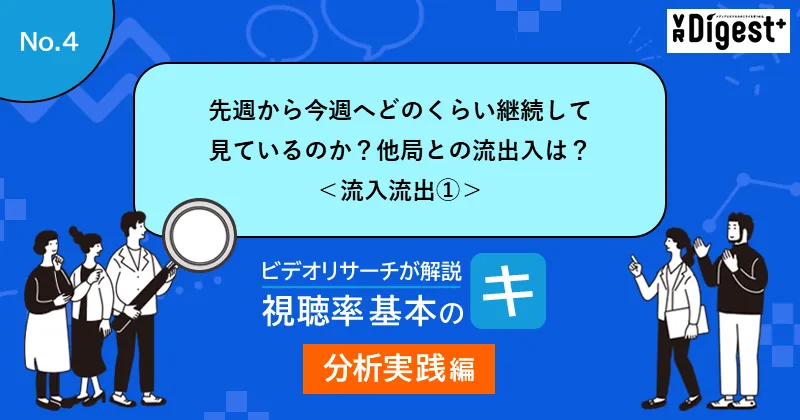てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「澤田隆治」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第4回
80年代に興った"マンザイブーム"の礎を築いた人物のひとりだといわれているのが、数多くの演芸番組を経て『花王名人劇場』を生み出した澤田隆治氏だ。
澤田は、1955年、まだラジオ単営局だった朝日放送に入社した。
正式入社前の1月から研修として会社に行き、様々な部署を経験。最終的に制作に配属された。
「お笑いをやりたいです」
制作でどんな番組をやりたいかと問われ、澤田がそう答えると、「変な人だね君は」と人事に言われた(※1)。当時は、今とは比べ物にならないくらい"お笑い"番組の地位は低かった。そのため、大抵の人はラジオドラマや音楽番組を希望する。最初から"お笑い"をやりたいという人など初めてだったという。
入社してまもなく大阪テレビ(のちに朝日放送と合併)が立ち上がると、中堅スタッフの多くがテレビへ異動。その結果、スタッフが手薄になり、新入社員にもかかわらず、澤田が新番組を任されるようになった。
澤田はその責任感の重さからか、毎日のように寄席に通いすべてのプログラムを見て、勉強するようになった。
最初に寄席に行ったとき、先輩から怒られた。
「金も払ってないのに笑うな」と。
それから「朝から晩まで寄席でネタを見て、なんで笑いが生まれるんだ、それを理屈で考えていくわけやからネタづくりが出来るようになった。だから、寄席で笑ったことない」(※1)という。
当時は10日間同じネタをやる。だからそれを見続けていると客がどのようなタイミングで笑うかがだんだんとわかってくる。逆に笑わない原因も見えてくる。そういう理屈がわかるから、のちに「ここ、こうしたほうが面白くなるよ」などとアドバイスができるようになった。
テレビに活躍の場を移した澤田は、中田ダイマル・ラケット、森光子という強力なスターが主演する日曜昼の『びっくり捕物帳』を担当。それが視聴率を落とし始めると、すぐにサラリーマンコメディ『スチャラカ社員』にリニューアルして、軌道に乗せた。さらに花菱アチャコの民間放送テレビ初主演となる『アチャコのどっこい御用だ』も手掛けた。
もともと、このふたつの番組はどちらもスタジオでのVTR収録だった。だが、それぞれの裏番組の視聴率が良い原因は、劇場公開で制作されているからではないか、という分析がされた。
そこで、公開番組に切り替えたのだ。スタジオ収録とそれほど違いがないと漠然と思っていた澤田だが、その作法がまったく違うことを思い知る。けれど、この経験が次の番組に大いに役立ったのだ。
その番組こそ、『てなもんや三度笠』だ。
番組平均世帯視聴率が56.2%(※2)という驚異の数字を叩き出したバラエティ番組。1962年から始まった番組は1968年まで全309回放送された。この番組から「オレがこんなに強いのも、あたり前田のクラッカー!」「耳の穴から手ぇ突っ込んで奥歯ガタガタいわしたろか」「非ッ常にキビシ~ッ!!」「許して...チョーダイ!!」など数多くの流行語も生まれた。
ちなみに「あたり前田のクラッカー」は、生で音をつけていたダジャレ好きな演出家がよく言っていたのを「もらった」のだと言う。
『てなもんや三度笠』は道中物コメディ。主人公・あんかけの時次郎に起用された藤田まことは当時まだ無名の存在で、他の番組にも出演しても、せいぜい"三番手"くらいのポジション。相当な抜擢だった。
テレビへ異動して最初に担当したコント番組『パッチリ天国』で藤田まことを若い二枚目半のやくざ役に起用した際、光るものを感じていた。そんな新人コメディアンと、時次郎を重ね合わせた人生修業のための道中だった。演出の澤田隆治は藤田まことと同い年。自分自身を重ねた部分もあったのだろう。
『てなもんや三度笠』で全国の視聴者がまず驚いたのは、時次郎の相棒である小坊主・珍念を演じた白木みのるの存在だった。
「なんだ、この達者な子供は!」と。
140cmの身長と子供らしい仕草だから、そう思っても無理はない。けれど、34年生まれの白木は33年生まれの藤田まこととわずか1歳差。当時28歳で、大阪では知らぬものがいないほど既に大スターだった。
そんな白木に澤田は「子供らしさをもういっぺん勉強してくれ」と、子供たちと一緒に遊ばせたりして珍念の役作りをしていったという。その甲斐もあってか、藤田や同い年の財津一郎との掛け合いは大評判になった。
メインキャスト3人と演出がほぼ同い年の20代後半。関西から全国に一旗揚げてやるという意気揚々たる野心に満ちていた。
だが、主役が藤田まことという"若手"では、ゲストに関西の売れっ子芸人たちは来てくれなかった。『てなもんや三度笠』は朝日放送制作ながらTBS系でネットされた全国放送。だったら、関東で活躍しているコメディアンを呼べばいいじゃないか。
そう澤田は考え、脱線トリオを筆頭に大物たちに次々とオファー。結果論で言えば、これが全国的にこの番組が人気を得た一つの要因だろう。もし、関西で制作しているからと言って関西のコメディアンだけでつくっていたら、これだけの人気は得られなかったのではないか。
この番組の特長のひとつがリアルで豪華なセットだ。
当時は「コメディは書き割りのものだよ」と言われたが、「リアルなセットの中でバカなことをするほうが落差があっていい」という信念のもと、木や草もホンモノにこだわった。舞台に「蚊が飛んできそう」な林を作るのだ。
いつしか、本番直前に植木職人がやってきて、ジョウロから水を口に含んで、それを木々に吹きかけるのがひとつの名物になった。そうすると途端に木々が生き返るのだ。
セットは歌川広重の『東海道五十三次』の浮世絵をリアルに再現。それが尽きるとスタッフがロケハンをし、その土地々々の名所旧跡をセットにした。
「自分の生まれ故郷の山の姿がそのままで感激した」というような投書が来るほどだったという。
さらにこだわったのが、殺陣。澤田は自らも猛勉強し、殺陣師の的場達雄と一緒に考えた。自分も考えてなければ演出が十分にできないからだ。一緒に組み立てていれば、どこをどう撮ったらより魅力的に映るかがわかる。
「殺陣をつける時からわかっていたら(細部まで)見えるんですよ。テレビのディレクターは引いてポンポンとアップで抜くしかやらないんです。僕は殺陣の稽古からついていってましたから、スローモーションで見えるんです」(※3)
映画などでは、殺陣は何度も同じシーンを撮り、編集することでそれを撮影することができるが、『てなもんや三度笠』の場合、一発本番だ。通常の公開コメディでは、引きの画を多用し、決めポーズだけアップで撮るのがせいぜいだった。
しかも、『てなもんや三度笠』のカメラはわずか3台。今、このような公開コメディを成立させるとすると最低でも6~7台は使うという。そんな中でも、澤田は、殺陣を躍動的に見せながら、しっかりアップとリアクションを撮ることにこだわった。それが面白さを際立たせると確信していたからだ。
これを実現するために徹底的にリハーサルを繰り返し、作り込んだ。「鬼」だとか「魔王」などと呼ばれる所以である。
当時の普通のコメディは60カットくらい。だが、『てなもんや三度笠』は80から100カットくらいに割っていた。
「テレビっていうのはアップだから。アップを撮ってあげなきゃダメ」「やっぱり表情が変わるところとかをキチッと撮ってあげないと」(※3)
そのこだわりが躍動感と臨場感を生んでいったのだ。
1974年、朝日放送から独立し東阪企画を設立した澤田は、1979年、関西テレビで『花王名人劇場』を立ち上げた。
その頃、演芸番組は下火になっていたが、澤田は花王が一社提供枠で番組をつくりたいと考えていることを知ると、わずか1週間で、3年分、150本もの企画書を作った。その熱意からか、一発で企画が通ったのだ。落語・漫才・コメディなど、お笑いの様々なジャンルの"名人"を集め、その芸を見せてもらおうという公開録画番組。その収録は主に国立演芸場で行われた。しかし、普通の公開番組と違ったのは客を"選んだ"ことだった。
澤田は自ら前説をしながら、客席をずっと見て、番組に非協力的な客がいると席を代わってもらったり、客席を撮るカメラにそのあたりのリアクションはロング以外、撮らせないようにした。帰りにアンケートを書いてもらい名前を調べ、その人には次からチケットを売らないということまでした。『花王名人劇場』を有料でやっていたのは、そういうことをしたかったからだ。やはり彼は「鬼」であり「魔王」と呼ぶにふさわしい。
「ずいぶん過激な思い上がった考え方だと私も思うんですが、番組のレベルをあげるのにはこれしかない」(※4)
そう信じてやり続けた。そして、選別した客席を別のカメラでずっと追い続けた。あまりウケていないネタに別の場面で笑った客の映像をインサートするという『エンタの神様』(日本テレビ)などに継承された演出を最初に"発明"したのも澤田だった。そうでもしなければ、閉塞した演芸番組を変えられないと思ったのだ。
「"こんなに大勢の人が笑っているんだよ"と、そのステージをどういう人がどういうふうに楽しんでいるかということを作為的に見せていこうと計算したんです」
当時、演芸番組といえばお年寄りのものというイメージだった。だから、若い客、特に若い女性をたくさん入れて、彼女たちが楽しそうに笑っているところを画面に積極的に映した。本当に楽しんでいる顔を選ぶ。意識的にそういう番組づくりをしていたという。
『花王名人劇場』が画期的だったのはそれだけではない。
実は公開収録と、実際に放送された番組が違っていたのだ。
水物の演芸において、同じネタであっても同じようにウケるとは限らない。寄席に通い続けていたからこそ澤田は実感していた。だから、収録を複数回行い、その中からウケが良かったものだけを放送したのだ。従って、収録に参加しても放送されないという芸人もいた。自然と、芸人たちも今まで以上に"本気"になったのだ。
こうした徹底的なこだわりが熱を生み、ブームへと昇華していったのだ。
※1 相沢直:著「『てなもんや』を作った男 澤田隆治インタビュー」(水道橋博士のメルマ旬報)
※2 1966年2月20日18:00~18:30 関西地区 ビデオリサーチ調べ
※3 『これが伝説の裏側! てなもんや奮闘記』(時代劇専門チャンネル)
※4 大山勝美:著『時代の予感―TVプロデューサーの世界』(東洋経済新報社)
<了>