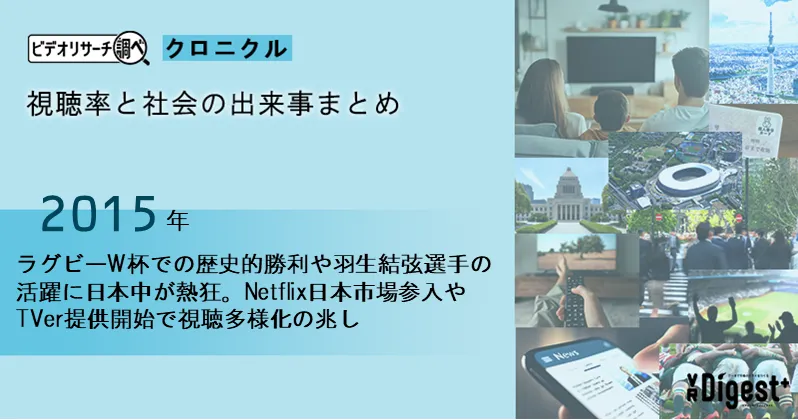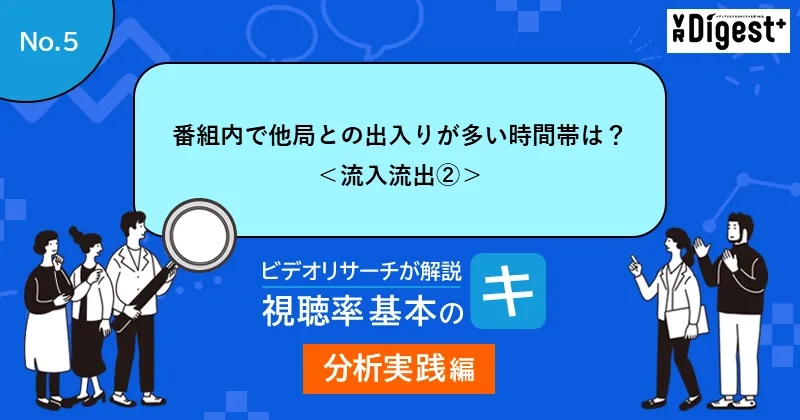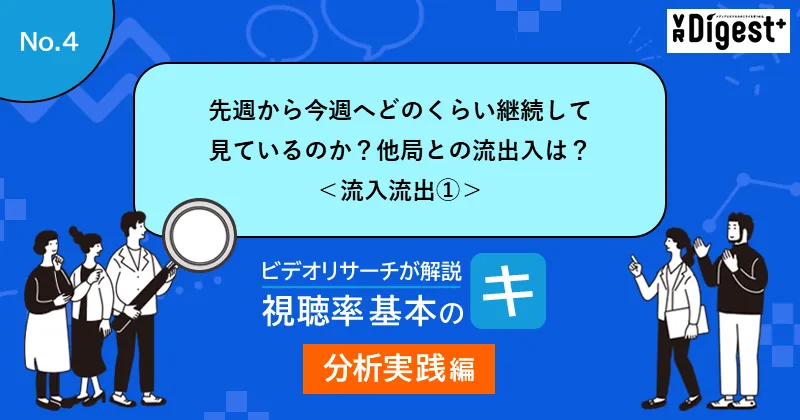【徳永 有美のメディア先読み】目に見えないもの、こぼれ落ちるものを伝える。そんな表現への挑戦〜作家・マンガ家 小林エリカさん〜
聞き手:フリーアナウンサー 徳永 有美(とくなが ゆみ)
1998年にテレビ朝日入社。『やじうまワイド』『スーパーモーニング』などのMCを務め、2004年4月から『報道ステーション』のスポーツコーナーを担当。2005年4月にテレビ朝日を退職し、2017年に12年ぶりにAbemaTV『けやきヒルズ』のキャスターとして現場復帰。
2018年10月より『報道ステーション』メインキャスターに就任した。
話し手:作家・マンガ家 小林 エリカ(こばやし えりか)
1978年東京生まれ。著書に、小説『マダム・キュリーと朝食を』(第27回三島由紀夫賞候補、第151回芥川龍之介賞候補)(集英社)、"放射能"の科学史を巡るコミック『光の子ども1,2』(リトルモア)、短編小説『彼女は鏡の中を覗きこむ』(集英社)、作品集『忘れられないの」(青土社)など。アーティストとして個展やグループ展も開催。アンネ・フランクと実父の日記をモチーフにした『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)、訳書アンネ・フランク・ハウス編『アンネのこと、すべて』(ポプラ社)などアンネに関する著書も多数。
【徳永 有美のメディア先読み】 第5回
今回は作家、マンガ家、アーティストとして幅広くご活躍する小林エリカさんをゲストにお迎えしました。2019年に刊行した近未来小説『トリニティ、トリニティ、トリニティ』をはじめ、過去の時間や放射能、家族など、「目に見えないもの」をテーマに表現活動を行う小林さん。それは報道に携わる徳永さんの心にも、深く共鳴する部分があったようです。
異なる世界で活躍するお二人ですが、表現者として、また親として同志のような絆が生まれた対談でした。
きっかけはアンネ・フランク
徳永 小林さん、本日はよろしくおねがいします。
もともと私が小林さんを知ったきっかけは、MilK JAPON(WEB)に連載されている「おこさま人生相談室」でした。とても面白くて大ファンになり、以来ずっと小林さんにお会いしたいなと思っていました。
小林 えー!「おこさま人生相談室」を見ていただいていたんですか?ありがとうございます!
徳永 小林さんは小説、マンガ、アートと幅広いジャンルでご活躍されていて、本当に多才ですよね。
小林 ありがとうございます。光栄です。
私は子どものころからずっと作家になりたいと思って創作活動をしていたのですが、文章を書いているうちに様々な気持ちがあふれてくるんです。例えば、本って色々な環境で好きに読んでもらえるのですが、「展示空間の中で、ここでしか読めないテキストがあったらどうなるんだろう」とか。そんな思いがインスタレーション・アートにも広がっていきました。
徳永 小林さんが作家になりたいと思われた理由を教えてください。
小林 本がたくさんある家だったので、子どもの頃から読書が好きでした。
中でも10歳の時に読んだ『アンネの日記』に多大な影響を受けています。特に印象的だったのは、アンネが「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」という言葉です。子どもながらにも漠然と死に対する恐怖があったのですが、アンネのように何かを残すことができれば死んだ後も形を変えて生き続けることができるのか!、と感動して作家を志しました。
徳永 10歳の時に『アンネの日記』が心に刺さるのというのはすごく感受性が豊かですね。
小林 今でも「もしアンネがおばあさんになるまで生きていたら、どんなことを書いていたのだろう?」と、思ったりしますね。読みたいけれど、それが読めないのが死んでしまうという事なんですよね。
徳永 アンネが生きている内に書き残したこと、そして若くして亡くなったことが小林さんの人生に影響を与えているのですね。

小林 私の父は生まれた年が偶然アンネと同じなんです。父が80歳の誕生日のとき実家へ戻ったら、たまたま父が16歳から17歳のときに書いた日記を見つけて読む機会があって。
第二次世界大戦中と大戦後のことが記された日記には「又一日命が延びた」と書いてあったんです。大日本帝国、つまりナチ・ドイツと同盟国だった国の少年が大好きな私の父でもあり、ナチ・ドイツに殺されたユダヤ人の少女が私の敬愛するアンネ・フランクでもある。
父の日記と、アンネの日記を携えて、実際にアンネの足取りを死から生へ遡るように辿りながら、同じ日の日記を読み、自分も日記を書く、という『親愛なるキティーたちへ』という作品を書きました。アンネの足取りを遡りながら、「あと一ヶ月戦争が早く終わっていれば」「あと一週間《隠れ家》が密告されなければ」という思いがよぎりました。そうして、最後にアンネが生まれたフランク・フルト・アムマインの街へ辿り着いたとき、「もしもだれもナチスに投票していなかったら、1人の少女が死ぬことはなかったかもしれない...」という考えにいたりました。
その経験から、今生きている私の、私たち一人ひとりの選択が、未来を生きるひとりの人間を生かす事も殺す事も出来る、ということを考えるきっかけになりました。
徳永 目の前のことが実は大きな未来に繋がっているなんて、なかなか意識できないですよね。
小林 現在起きている事に対して、即時にジャッジを求められてしまうことって多いですよね。でも、私が敬愛する作家の一人であるスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチが、「裁くのは時代にまかせましょう。」「でもそれは近い時代ではなく、わたしたちがいなくなった遠い時代。」と書いているんです。それを読んで、「ああそうか、私の仕事は善悪をジャッジすることではなく、ただひたすら書き留めることなんだ」と思ったらすごく心強い気持ちになりました。
裁いて批判したり褒め称えたりすることは気持ちがよいし、良い悪いを言った方が簡単だし、納得しやすいのは分かるんです。でも、善悪は時代によって移り変わるものだし、一見、善悪のどちらにもつかないような "こぼれ落ちてしまうもの"をあえて私は書いていきたいと思っています。
徳永 それ、すごく共感します。『報道ステーション』の仕事をしていても、上のレイヤーから物事をジャッジすることは絶対にやりたくないと思っています。報道の仕事をしていると、簡単に一括りにできないこと、表現しきれないことをたくさん抱えてモヤモヤしてしまうことも多いです。だから、そういったことをひっくるめて作品として表現できる小林さんの世界が羨ましいですし、心が洗われます。
小林 私の方こそ、わかりやすい答えを期待されるテレビというマスに開かれた場で、且つ時間も限られた中でそれを貫く姿勢、尊敬します。一人ひとりの思いを大事にしている現場の人がいるということが伝わるだけで、勇気づけられる人はたくさんいると思います。
長編小説でも書ききれないことがたくさんあるのですから、徳永さんは本当に難しいことに挑戦しているのだなと思います。

原子力発電所内で、コンビニエンスストアを見たときの衝撃
徳永 小林さんは、2019年に刊行した『トリニティ、トリニティ、トリニティ』をはじめ、核や放射性物質をテーマにした作品を多数手がけていらっしゃいます。関心を持ったきっかけは何かあったのでしょうか?
小林 「放射能」という言葉の名づけ親でもある科学者マリ・キュリー(キュリー夫人)の実験ノートを明星大学の貴重書図書館で見たことが大きいですね。そのノートは、マリ・キュリーが直筆で研究や実験などを記録したものなんですが、そのノートにガイガーカウンター(放射線量計測器)をかざすといまなお放射線量がわずかに高いんです。
なぜかというと、彼女はラジウムやポロニウムなどの放射性物質を素手で扱っていたので、その指紋の部分には放射性物質がいまだに残っているから、と教えられました。私はそれを聞いてすごくびっくりしました。マリ・キュリーが亡くなったのは遥か昔だし、ここは遠く離れた東京。それでもなお、時間も距離も超えて、目に見えない彼女の痕跡が残っている。
ラジウムの半減期は1601年といわれています。そうすると、1902年に彼女がその手にしたラジウムが半減期を迎えるのは西暦3503年。つまり一世代を30年とすると53世代後の子どもたちが生きている未来にもなお、彼女の痕跡はあり続けるということなんです。私はそれを知って、「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」というアンネの言葉を思い出したんです。以来ずっと放射性物質に興味を持っています。
徳永 放射性物質を介して、遥か未来まで指紋が残るんですね...。
小林 そうなんです。そんな体験があって、放射性物質という見えないものを自分の目で見てみたいと思って、いろいろなところを訪ねました。例えば、世界で初めての原子爆弾実験が行われたアメリカ、ニューメキシコ州のトリニティ・サイトに行ってみたり、パリのキュリー夫妻の研究所の跡地に行ったり。
だけど、「何も見えない」ということだけ分かって帰ってきていました。
2017年には、東京電力福島第一原子力発電所の構内に行く機会がありました。その中に入ったら、なんとコンビニエンスストアがあったんですよ。うちの近所にあるコンビニと同じコンビニ。それを見て、私はすごく衝撃を受けたんです。そこではじめて、気づきました。放射性物質というのは目にはみえないはずのものなのに、やっぱり心の中では、放射性物質があるような場所というのは、どこか自分の住むこことは違う場所、たとえばチェルノブイリのような瓦礫や緑に覆われた街並みを、勝手にあてはめて想像していたのではないか、ということに。
こんなにも長いこと放射性物質は目に見えない、と書き続けていたにもかかわらず、「目に見えないものを見たつもり」になったり「わかって知ったつもり」になっていたのではないかと猛省しました。それ以来、目に見えないものを目に見えるようにするのではなく、どうしたら目には見えないものを目に見えないまま書き記したり理解しようとすることができるのか、ということを考えています。
徳永 目に見えないものを、目に見えないまま理解する...。とても深いですね。その世界観が小林さんの作品に繋がっているんだなと、お話を伺っていて思いました。
小林 それは嬉しいですね。どうやったら見えないものを見えないままで伝えられるのかについては、これからも考えていきたいです。
徳永 他に小林さんが最近気になっていることはありますか?
小林 最近は、善悪だけでは捉えきれないような人間の欲望の部分に興味があります。人間は火を発見して以来、どんどん暗闇を照らす光を欲して、結果的に今の文明社会が築き上げられていると思うんです。
マリ・キュリーが礎を築いた決して消えることのない「光」や「核」は、その究極ですよね。太陽のような核さえ作り上げたのは、「神のような力さえも手に入れたい」という欲望が背景にあるのだと思います。光だけでなく、死にたくないという欲望から、命さえもコントロールしたいと願う。そういう欲望があって、私が生きている今があるのかなと。
徳永 欲望が文明を築いてきたという考えは、とても面白いですね。
小林 あとは、お金についても、今とても興味があります。16世紀、ボヘミア地方で鋳造されたヨアヒムス・ターラーというのがやがて新世界アメリカへ渡ってダラー「ドル」の語源になるのですが、その銀を掘っていた坑夫達から「不幸の石」と呼ばれていた黒光りする鉱石があったんです。お金にもならないし、鉱夫たちは次々と病気になるわで捨てられていました。
でも、ある時その「不幸の石」がパリに運ばれて、マリ・キュリーたちの手でそこから放射性物質のラジウムが取り出されることになるんです。キュリー夫妻がノーベル賞を受賞したことで、放射性ラジウムは一気に人気になって、そのうえ癌も治ると謳われて、たちまち金よりもなお高価な物質になるんです。
そういう歴史を追っていくと、価値も善し悪しも時代によってたちまち逆転するし、お金という目に見えないものを巡って欲望も絡まり合っていて、すごく興味深いです。

その人のことをすべて知ることはできない。でも諦めたくない
徳永 私は、ニュースで報じられる人の背景だったり、その人の抱えているものを想像しながら仕事をしています。しかし、目には見えないので、それを想像していくのはなかなか難しいことだなといつも感じています。小林さんはそこを丁寧に探っていらっしゃるなと思いました。
小林 父の日記を読んだことの影響が大きいですね。というのも、父とは家族だし、何十年も一緒に生きてきて、とても身近で、何でも知っている存在だと思っていた。だけど、当然、父にも、父になるより前の若い頃もあるわけです。戦争のことも聞いたことはありましたが、日記に書かれていたようなことは絶対に口にはしなかったし、語ることができなかったんだと思います。
以来、すごく親しい相手のことはなんでも知っているような気になるけれど、それでも分からない部分があるし、知り得ないこともある、という認識で常にいます。だから全て知ることはできなかったとしても、どこまで想像できるんだろうといつも考えています。
徳永 どれだけ密接になっても知り得ないことってありますよね。知りたいと思って、諦めないことはすごく大切なことだと思うのですが、結局全部知ることはできない。でも知りたいと思ったり、表現したいということに対して諦めてはだめなんですよね。
小林 徳永さんは報道の仕事をされているので、人の歴史や背景をたくさんの人に伝えるというミッションがありますよね。かつ、瞬発的に考えを述べたり、その状況を判断して行動できるのはすごいなと思います。
徳永 それが全然できなくて、どうやったらできるのかといつも自問自答して、一回全部考えるのをやめてみたり、試行錯誤しています。
2019年12月にアフガニスタンに貢献された中村哲さんがお亡くなりになった時、いろいろと思いを巡らせてしまい、VTRを見ていたら感極まって言葉が震えてしまいました。そうなってしまうと何も伝えられない。早く冷静にならなければと思ったのですが、結局震えを止められなかったです。こんな体たらくでどうする、とすごく反省しました。
小林 それは言葉が震えてしまったことも含めて、徳永さんの伝え方として素晴らしいと思う。その姿勢に胸が打たれて、徳永さんが伝えたいことを受けとめた視聴者の方もいたはずですし。
私はその瞬発力がなくて。『トリニティ、トリニティ、トリニティ』だって、初めてトリニティ・サイトに行ったのが2008年。構想から作品ができるまでに10年かかってしまいました。10年後になってやっと感想が思い浮かぶ、という感じです。
徳永 まさに、長い時間かけて誠実に絞って出てきた一滴のような作品だということなんだと思います。物事に対する関わり方の深さは見ている人にはわかるので、私自身も努力していきたい部分でもあります。

子ども、子育てを通じて気付かされた
徳永 冒頭で小林さんの「おこさま人生相談室」がすごく好き、とお伝えしたのですが、連載を始められたきっかけを教えてください。
小林 子どもが生まれたタイミングで、MilK JAPONさんから「何かやりませんか」と声をかけていただいたのがきっかけです。子どもが大人の悩みに答えるというアイディアは、私自身が子どもの頃に抱えていた「なんで大人は子どもだと思って意見をちゃんと聞こうとしてくれないの?」「いつも大人は偉そうで子どもがそれに従うというのは納得いかない!」という思いがきっかけです。
大人になったら、もっとずっと賢くなって、何でもわかるようになるし、悩みだってなくなるんだろう、と思っていたのに、私自身、不惑の年を迎えてもスーパーの買い物から人生まで悩んでばかりで、「違うじゃん!」みたいな。きっとそんな大人がたくさんいるんじゃないかなと思ったのもありますね(笑)。
大人の悩みに子どもが答える形なので、最初の頃はどういう答えが返ってくるんだろうとドキドキしていました。だけど、毎回予想の斜め上をゆく素晴らしい答えが返ってくるので、いつも私自身が勉強させてもらってます。
徳永 子どもの意見を尊重する、という当たり前のことを「おこさま人生相談室」を読んで思い出しました。私も毎日悩んでばかりなのですが、子どもの意見の中に答えもあるのかもしれない、という新鮮な発見もありましたね。
小林さんはお子さんを育てながら作家活動を続けていらっしゃいます。大変ではないですか?
小林 子どもを産んで1年ぐらいは体調も具合も悪くて、何もできない時期、というのがありました。仕事も全然できなくて、家事とかはもとから苦手で、そのうえ子育てなんてどうしたらいいかわからないし、そのうえ、母乳もでない!みたいになって。私はそのとき、なんて私は無価値な存在なんだ!とすごく自分を責めてしまったんです。
で、努力が足りないから、仕事も、家事も、子育てもできないんだ、と考えて、頑張ろうとして、母乳の量を測ってはグラフを作り続ける、みたいな間違った方向性の努力を重ねる、という日々でした。今思えば、完全に産後うつみたいなやつだったんだと思うのですが。
でも、当時の自分を振り返って、私、すごく反省したんです。
そもそも、自分はこれまで価値というものを、お金を稼ぐとか、役に立つとか、そういうことでしか考えていなかったのかもしれないって。自分を無価値だと考えることは、ひるがえって、他の人のことも、そういう価値でしか見ていなかったんじゃないかって。でも、人間って、本当はただ、生きてそこにいるだけで、価値があるものなはずじゃないですか。
あと、これまで自分がいかに"努力信仰"だったかということにも気づきました。努力すればなんとかなる、っていうのは幻想ですよね。
人生って頑張ったところでどうにもならないことってあるじゃないですか。なのに、それをどこかで努力でなんとかできると信じる、というのは心底恐ろしいことだな、と思います。それは、何かができなかった人に対して、努力が足りないからだって、責めることにもつながるし。だって、いくら努力しても、赤子は泣き止まないし、人間は病気にもなるし、人間いつかは必ず死ぬんです。神の力を手にしてはいないんだから。恋愛や出産だって、努力でどうにかなるものではないですよね。
徳永 猛省した後にどんな時間が待っていましたか?
小林 何もしていなくてもただ生きているだけで価値があるし、努力したからって上手く行かないこともあるよな、という思いに至りました。
そのうちに子どもが3歳になって産後うつも抜け、価値と努力に対する気づきから『トリニティ、トリニティ、トリニティ』という作品もできました。
でも本当に、みんなどうしているんだろう?!って思います。徳永さんは、いったいどんなふうに、子どもを育てながらお仕事しているんですか?
徳永 私の場合ですが、全て抱えるのはやはり苦しいだけなので、子育てや家事を自分がすべてやることは諦めました。
私は月曜日から木曜日は子どもといる時間が本当に限られているので、子どもに対して「申し訳ないな、ごめんね」という気持ちを抱えているのですが、ある時から「無理なものは無理」と降参して(笑)、自分も腹をくくり、子どもたちにも腹をくくってもらいました。
それでも毎日の中で寂しい想いや様々な出来事の濃淡があって、切ないこともたくさんあります。でもしようがないんです!ママもパパも両方大変なら他の誰かを巻き込んでいくしかなくて。申し訳ない気持ちもありますが、子どもなりに両親の仕事に対しての思いもあるようなので、そこを尊重して「いつか分かってくれるといいな」という希望を持ちながら頑張っているところです。
小林 徳永さんみたいな女性もいるということがとても大事ですよね。「母たるものは」という確固たるものがあると息苦しいですから。
仕事ができて、家事も育児もこなして、家も綺麗、みたいな理想像が私の中には無意識のうちに刷り込まれていて、そうならなきゃと焦っていました。だけどよく考えたら、私が育った家は、両親が本好きでだれひとり掃除をしないゴミ屋敷だったんですけど、思い返せばそういう家でも結構楽しかったな、と思って。掃除もしないし家事もしない、と決めたらすごく楽になりました。
多様な生き方を一人ひとりがしてゆくことで、いろんなかたちの「母」や「家族」ができたらいいと思います。
徳永 小林さんは、感じて、考えて、表現する、という創作の世界にいらっしゃいますが、お仕事と生活のバランスはどのようにされていますか?
小林 子どもがいないときにはダラダラ昼夜問わず仕事をしていたのですが、今は仕事をするのは子どもを保育園に預かってもらっている9時~18時の間と決めています。その時間はアトリエや喫茶店で、創作活動です。まあ、いつも時間が足りない!終わらない!ってなってますが(笑)。
その後は、強制的に子どもに教えてもらう時間になりますね。子どもから学ぶことってすごく多いんです。「おこさま人生相談室」でもそうなのですが、子どもの声を聞くと、今まで自分が忙しくて子どもの声に耳を傾けていなかったことに気づきます。それは子育てしている人だけじゃなくて社会全体に言えると思います。

時間や場所を越え、自分の作品を手にとってもらいたい
徳永 最後にお聞きしたいのですが、小林さんはご自身の作品が受け手にどう伝わっているのかという点についてはどうお考えですか?
小林 作品がどこでどういう風に読まれているのか分からないのでいつもドキドキしていますが、自分とはかけ離れた遠い場所や時間のなかでも読んでもらえていたら嬉しいですね。でもやっぱり直接、本や作品を手にとっていただいた、という話も聞くと勇気が出ます。
以前は、読者というものを勝手にイメージして、こうしたら読みやすいんじゃないか、こうしたら喜んでもらえるのではないか、とあれこれ考えていたこともありました。マンガや小説は歴史が長い分、定型があって、そこに沿って作品を作るべきというプレッシャーがあったのかもしれません。だけど一人ひとり好きなものは違うし、私の人生を生きているのは私だし、「本当にこれって小説なの?」と批判されたとしても構わないので、私自身が一番好きなように、やりたいように表現しよう、と思うようになりました。
それこそ報道番組にも型があると思うのですが、徳永さんはどのように向き合っているのですか?
徳永 精神的には超えたつもりなのですが、定型に逃げることが多々あることも事実です。だけどなるべくそこに逃げないよう、常にぶち破る力を持っていたいと意識しています。気を緩めたり、集中力が欠けるとすぐに流れてしまいそうになるんです。
そして、その先に「どう伝えるか」があるのですが、今私がいる場所は10数秒で勝負、いわゆる表現だったり伝えなくてはいけない場面があるので、そうすると本当の部分が伝わっていないのではないかという不安を抱くことも多々あります。
特に、自分が心の底から強く思っていることを伝えようとすると、逆に分かりにくくなってしまうことが今抱えている課題です。押しつけや自己満足に陥ることもしたくない。だけど、この仕事をしている限り、たくさんの人にひとくくりにはできないたくさんの思いを伝えるということは諦めてはいけないと思っています。
小林 私はアンネ・フランクに憧れて作家になったので、ジャーナリズムに携わって前線で活動している徳永さんはすごく輝いて見えます。徳永さんに私の作品を読んでいただいて、今日こうしてお話ができて光栄でした。
徳永 こちらこそ、尊敬している小林さんからお話が聞けて心が洗われました。世界は違いますが、目に見えないものへの想像力や、ひとくくりにできずにそこからこぼれ落ちるものこそ大切に、それらをどう伝えるのか、いつだって諦めないで進んでいきたいなと改めて思いました。
今日はありがとうございました!
<了>