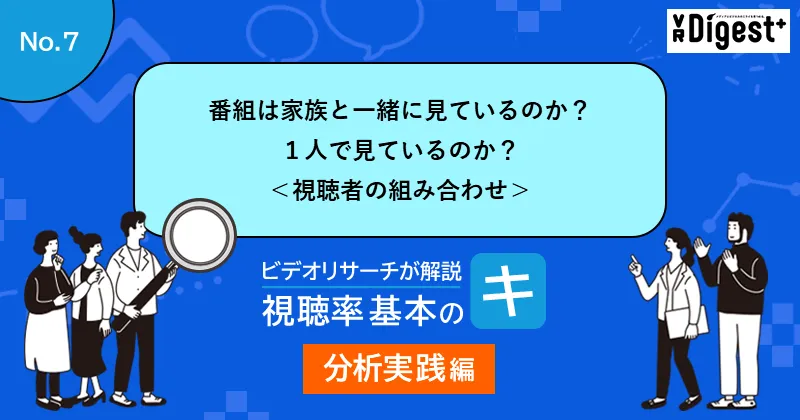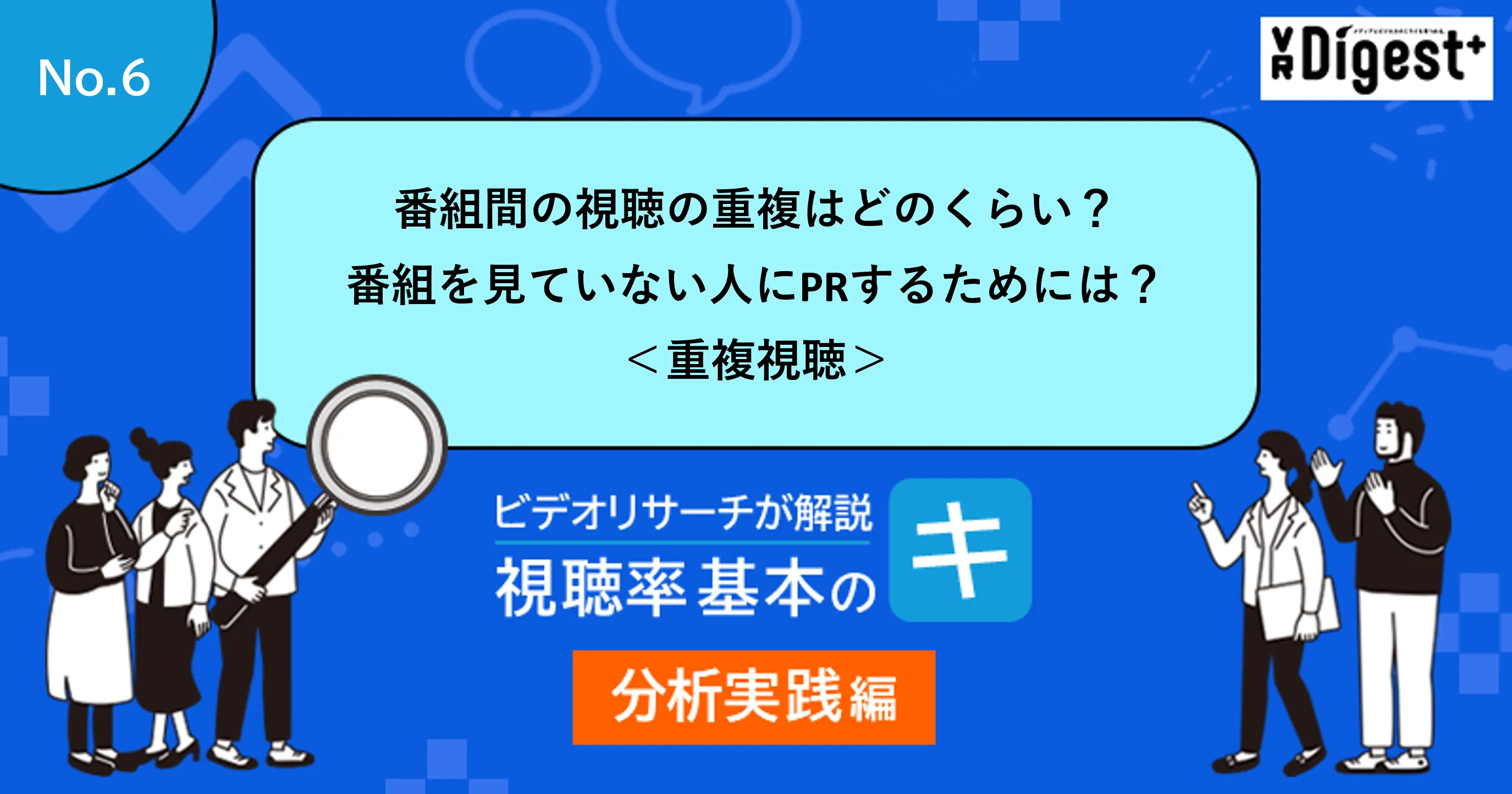てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「星野淳一郎」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第5回
その男はとてつもなく大きかったという。
身長190cm近くある大男で、ロシア人のような日本人離れした顔立ち。常に目につく存在だった。
けれど、大きかったのは体躯だけではない。
その存在感は、並み居るディレクターを凌駕していた。
男の名は星野淳一郎氏。
フリーランスのディレクターとして『ダウンタウンのごっつええ感じ』などを手掛けた名演出家である。
彼は『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』などの吉田正樹と同年代の"ライバル"として切磋琢磨し、ダウンタウンやウッチャンナンチャン、野沢直子、清水ミチコによるユニットコント番組『夢で逢えたら』を一緒に生み出した。また、『ごっつええ感じ』の小松純也や『めちゃ×2イケてるッ!』(以上、番組はいずれもフジテレビ)の片岡飛鳥がともに「師匠」的存在として慕っていた。
星野淳一郎は、「素晴らしい演出家だった」と言われている。
だが、同僚として長年間近で星野と接してきた吉田正樹の実感は違う。
「スーパーAD」
それこそが、星野をもっとも的確にあらわした形容だという。
つまり、いかに80年代のテレビは現場が回していたか、現場が面白かったかということだ、と(※1)。
星野淳一郎は、高校在学中の17歳の頃、アルバイトでADとなり横沢彪率いる横澤班が作る『THE MANZAI』に配属された。
『THE MANZAI』がヒットするとそのメンバーを中心に昼の帯番組『笑ってる場合ですよ!』を制作。そして、その後継番組として、タモリを司会に抜擢した『笑っていいとも!』が生まれた。
そのまま横澤班で働いていた星野はこの番組立ち上げ時から、「チーフAD」だった。
『いいとも』では、1カメからハンディの5カメまである。当然1カメが一番重要で、「テレフォンショッキング」は、その1カメからの目線となる。また、アルタの控室、つまりプロデューサーの横澤たちがいる本部席が扉1枚挟んである。
ここのモニター横に仁王立ちしていたのが星野淳一郎だった。
毎日、ここから離れない。1カメ横は常にタモリの目線に入る位置。実質的に全体を指揮するポジションだった。
「タモリさんの目線からオレは外れられないんだ」と。
その巨大な体躯は、まさに"アルタの主"のようだった。
「アルタはオレが仕切ってるんだ。生放送が始まってしまえば、ディレクターよりもすべての権限はオレにある。タモリさん、オレを見ろ」
そんなプライドを持って、現場を仕切っていたのだ。
ADの人事や、誰をどこにつけるのかまで全部取り仕切り、出演者側とのギャラ交渉まで彼がやっていた。だから、若いディレクターもADである彼の言うことに従わざるを得ないくらいだったという。
星野は、『笑っていいとも!』という生放送のドラマ性、台本には書けないこともあるんだっていうことを本質的に知っていた。番組の最初に起こったことを同時間に処理して、その日の結末にちゃんと回収する。あるいは前日に起こった出来事をどこで生かすかということを常に考えていた。
たとえば、「テレフォンショッキング」のお友達紹介で間違い電話をしたら、その間違えた人を呼んでしまう。さらに、その人を年末の『特大号』にまで呼んでしまう。起こったことをダイナミックに回収することに長けていた。
それはタモリの生放送観にも見事に合致していた。
吉田正樹は早逝した星野への弔事でその仕事っぷりをこのように綴っている。
「毎日の笑っていいいとも!スタジオアルタの下手に仁王立ちして、どんなことがあってもこの場は俺が支えるというまさに無双の存在でした。
几帳面で豪胆、最悪の事態を悲観論で準備して、本番は何があっても『しゃーねーや』と最高の楽観論で楽しんでゆく。
タモリさんとの信頼、そして当時の最高の出演者のなかでうまれた、フジテレビらしい幸せな空気でした」
フジテレビ版"24時間テレビ"である第1回の『FNSテレビ夢列島(現『27時間テレビ』)』でも彼は当初、チーフADとして参加した。
だが役割は絶大だった。たとえば、進行台本を書いたのも星野だった。
だから総合演出の三宅恵介の後方で、星野が全スタッフに対し指令を飛ばす。彼自身が台本をまとめているため、24時間分の進行が全部頭に入っているからだ。
一時期までフジテレビの『27時間テレビ』の台本は、1ロール(CMとCMの間)が1ページに入るようになっている横長の本になっていた。そういう仕組みやフォーマットまで全部、30年にも及ぶその基礎を星野が作ったのだ。
「星野、お前はプロデューサーの仕事をしたよ」
横澤はそんな星野の仕事を最大限評価し、『FNSテレビ夢列島』のエンドクレジットに「プロデューサー」として星野淳一郎の名前を刻んだのだ(※1)。
星野は片岡飛鳥を「小僧」と呼んだ。彼が悩んでいるのに気づくと、そっと置き手紙をしてくれたりした。
そこには「編集の鉄則」が書かれていた。
たとえば「編集は直感を信じてやりなさい」。収録を終えたあとで山のような素材と向き合って、何回も何回もその素材を繰り返し見ていると何が面白いのかだんだんわからなくなって、編集した結果、「こんなもん、作りたかったんだっけ?」というものが出来上がってしまうのが若手ディレクターの陥りがちな罠だ。
そうならないためには「収録現場で何を見て笑っていたのか?」を大事にしなければならない。だから編集に時間をかけるのではなく、収録に行く前の準備に時間をかけなければならないという教えだった。
「編集で何とかしようというのは一番ダメなディレクター。そもそもプロなんだからつまらないものを撮ってきちゃいけないんだ」と(※2)。
『ごっつええ感じ』のベースを作った星野は小松純也に演出の座を譲った。
小松に星野から「視聴率はお前と視聴者の距離だ」と教わったと述懐する。
「誰のために番組を作っているのかということ。制作者と出演者の距離感はどうあるべきかとか、そういうことも含めて教わりましたね。(略)例えば演者が何をやろうかって演じ方を考えている時には話しかけちゃダメ。そういうデリカシーっていうのは、ディレクターの大事なスキルだと思います。
演者のやりようの工夫、創意をめぐらせるストロークを作ってあげる。だから芸人と仲良くなってこんな内輪話が撮れたとか、収入がいくらって言ったとか、そんなことまでテレビで言わせる関係性を作る制作者っていうのはどうかなと。本当にやめてくれよって思います。芸人さんと飲みに行って『面白いことやりたいな』ってくだをまくのが仕事じゃないと思うんです。その人がどうやったら視聴者に面白く届くかを客観的に考える。その人を活かせる企画を真摯に考えるのがテレビマンのすべきことなんじゃないかと。それは星野淳一郎さんに学んだことですね」(※3)
※1 「マイナビニュース」2018/01/13
※2 「文春オンライン」 2019/03/30
※3 「文春オンライン」 2017/05/02
<了>