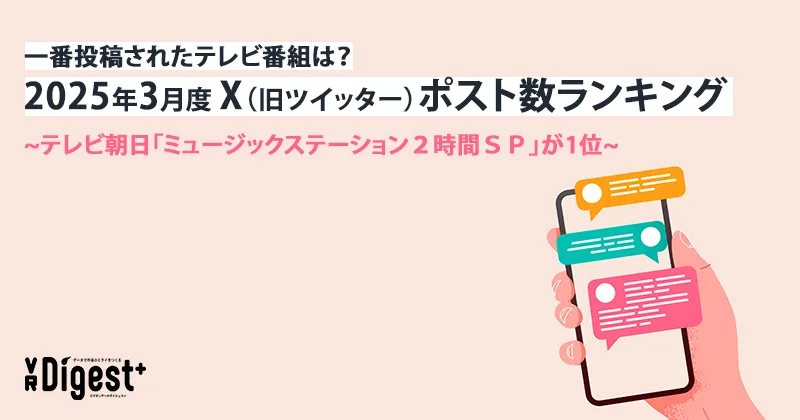【TV2020】恐れずに、テレビの矜持をもって。新しい羅針盤で大海原へ乗り出そう〜筑波大学メディア論教授 辻 泰明さん〜
筑波大学 メディア論教授 辻 泰明さん
2020年3月「NHKプラス」がスタート。これに追随するように、2020年秋以降、民放各社でのテレビ放送のネット同時配信が始まるとみられています。放送と通信の連携・融和が既定路線となるなか、テレビビジネスに携わる人たちが感じている、疾風迅雷のインターネットにのみこまれてしまうのではないかという懸念。それに対して、海外事情にも精通している筑波大学メディア論教授・辻氏に、テレビの活路や進むべき方向性について、深く語っていただきました。
インターネットメディアの急成長
─2020年3月より常時同時配信「NHKプラス」が始まったこともあり、放送と通信の融合がますます話題になっています。辻先生のご見解をお聞かせいただけますか?
イギリスのBBC(英国放送協会)は、2007年に「iPlayer」というサービスの提供を開始しました。放送側から通信へのアプローチという形でiPlayerが登場し、見逃し配信がスタート。イギリスでは、放送と通信の本格的な融合が始まりました。この2007年という年はiPlayerの登場だけではなく、YouTubeが一部の投稿者に収益を得ることを可能にしたり、Netflixが事業転換をして配信を開始したりといった出来事が相次ぎ、インターネット動画メディアにとって重要な節目となった年です。
日本でも当時から放送と通信の融合についてさまざまに議論・検討されてきました。iPlayerから10数年のタイムラグを経て、今ようやく歩を進めることになったのですが、この10年の間に映像メディアの転換は劇的に進行しています。
2010年代にインターネット動画メディアは急成長し、2019年時点でYouTubeの月間利用者は全世界に19億人(※)。全員が毎日接触するわけではありませんが、極めて大きな規模です。
※『インターネット動画メディア論』(大学教育出版)より
─多数のネットメディアが動画を取り扱うようにもなりました。
YouTubeはGoogleの傘下にあります。Amazonは元々かなり早い段階から「Amazonプライム・ビデオ」を会員獲得の目玉にしています。Facebookは「ストーリーズ」、Appleも「Apple TV+」を始めました。Netflixは動画専業です。GAFAにNetflixを加えてFAANGとも呼ばれる5つのプラットフォームが、いずれも動画を成長の主力と位置づけ、テレビを凌駕する巨大なメディアとなりつつあります。
テレビはドメスティックなメディアで、それぞれの国のなかでは巨大なメディアでした。ところがインターネットはグローバルに国境を越えていくので、テレビよりもはるかに大きなメディアとして存在するようになったといえます。
─「NHKプラス」を皮切りに、民放局でも常時同時配信の検討が進んでいます。
2007年にBBCが「iPlayer」を始めたときや、2000年代に日本で盛んに「放送と通信の融合」が議論されていた時代とは、決定的に取り巻く環境が変わっています。放送とは別のところで、インターネット動画メディアが巨大メディアとして成長している状況で、今あらためて出発をしていくわけですから、「状況が変わっている」ということを意識する必要があるのではないでしょうか。

21世紀 メディアの転換
─放送と通信、それぞれの特徴や違いについてお聞かせください。
テレビが基本的には送り手から受け手への"一方向のメディア"であるのに対し、インターネットは"双方向のメディア"であるという、決定的な原理の違いがあります。インターネットは双方向性の機能を用いて、テレビでは難しかった利便性やサービスを提供できます。オンデマンド視聴、多様なインターフェイス、番組検索、コメントや評価の共有、ユーザーによるコンテンツの投稿など。今までになかった新しい形の、利便性が高いメディアなので、膨大な数のユーザーが集まるのです。アメリカで急速に進行しているコードカッティング(ケーブルTVからネット動画への乗り換え)にも、料金の安さに加えて、こうした利便性が背景にあると考えられます。
1990年代、インターネットが登場した頃は、広報の手段としてサイトを開設する等、通信はあくまで放送の補完的な役割を果たすものとしてとらえられていました。2000年代に「放送と通信の融合」が盛んに唱えられていた頃も、放送と対立する部分がありながらも、「新たな伝送路の獲得」といった意味では放送の補完的な存在になるという意識がありました。
しかし、2010年代にインターネット動画メディアが急成長して新たな"映像メディアの転換"が生じたことで、その関係は変化しつつあります。映像メディアの転換がおこるときの非常に重要な経験則として「次のメディアが前のメディアを包含する」という構造になるのです。
─具体的にどういうことでしょうか?
20世紀に起こった映画からテレビへの転換でいうと、テレビで映画を放送することは可能でしたが、映画はテレビを包含することはできませんでした。それと同様に、テレビはインターネットを包含することはできませんが、インターネットは通信回線を通じて同時配信という形でテレビを包含することができます。
─視聴のされ方も大きく変化していますよね。
その功罪が議論されてはいますが、ビンジウォッチング(一気見)のような新たな視聴態様が生じていますね。今後、テレビ視聴や映像コンテンツに対する接し方はさらに変わってくるでしょう。
映画やテレビは、みんなが同じものを、同じときに同じ場所で視聴する映像メディアでした。映画は上映時間に合わせて映画館に足を運んで見るものですし、テレビもまた"お茶の間の王様"と呼ばれた頃は、決まった時間にみんなが集まって見ていました。『8時だョ!全員集合』という番組タイトルは、テレビメディアの本質をよくあらわしていると思います。
それに対して、インターネット動画メディアは、一人ひとりが自分の好きなものを、好きなときに好きな場所で見るメディアです。ユーザーは見たいコンテンツを自分で検索し、選択することができます。「好きな場所で」というのは、テレビもずっとポータブルテレビのような形を追求してきたのですが、テレビとは全く別の新しいハードウェアであるスマートフォンによって実現されたことになりますね。
こうした視聴態様の変化は、かつての大量生産・大量消費を前提とした均一的な社会が、個性と多様化を重んじる社会に変わってきたことと軌を一にしており、ライフスタイルの変容とテクノロジーの進化が合致した結果ともいえるでしょう。
―テレビが担ってきた役割が通信に移行しつつある、とういうことでしょうか?
テレビ制作者の一部にはまだ通信を「情報収集のツール」としてしか見ていない人がいるかもしれませんが、ユーザーの動向は違います。2010年代にYouTuberが台頭し、Netflixがオリジナルコンテンツの制作を始めるなど、インターネット動画メディアが発達して、通信は単なる「情報収集のツール」ではなく、動画を楽しむ「娯楽メディア」に進化しています。
実は"テレビ離れ"という現象は、日本では1980年代にも生じていました。マンネリ化が指摘され、視聴時間も減少したのです。この"テレビ離れ"に際して、1980年代には「教養の娯楽化」や「報道の劇場化」と呼ばれた変革が起こり、ニュースショーやクイズ型の教養番組など新機軸番組が登場しました。こうした変革もひとつの要因となって視聴時間は増加に転じ、その後安定的に推移していたのです。
ところが、インターネットでの動画配信が本格化して、通信が映像コンテンツを楽しむための新たな娯楽メディアとしての性格を強めるのと符合して、日本では2010年代半ばには、改めて"テレビ離れ"が顕著になってきたのです。インターネットでは、テレビでは見られないコンテンツや、ハリウッド映画に匹敵するコンテンツも提供されています。YouTuberはアイドルよりも身近な存在で、「すぐそこにいる友達が面白いコンテンツを出している」という感覚を味わえる。特に若年層には、こうしたインターネット動画を「テレビよりも魅力的、面白い」と感じる人が多いと考えられます。
現にアメリカでは、かつてMTVが担っていた「音楽の最新情報に接する場」としての役割をYouTube Musicが果たすようになっているという研究者もいます。インターネット動画メディアが新世代の映像メディアとしてテレビを包含しつつ発展していることは、いずれ誰もが認識せざるを得なくなるでしょう。

"双方向性メディア"がもたらした変化
─インターネット動画メディアの発展によって、最も変化したことは何でしょうか?
送り手と受け手の関係性ですね。インターネットが圧倒的な利便性を持ち、ユーザー側がコンテンツを選べるようになった今、日本で"4マス(テレビ、新聞、ラジオ、雑誌という4媒体の通称)"と呼ぶようなトラディショナルなマスメディアが持っていた "優位性"が薄らいできました。
かつてマスコミが非常に大きな力を持ち、第4権力と呼ばれていた時代がありました。トラディショナルなメディアが強力だったのは、「何を供給するか」をメディア側がある程度決めることができたからです。
一方、インターネット動画メディアは、プラットフォーム自体は強力であるものの、ユーザーの存在も大きくなり、送り手と受け手の力関係が変化してきています。インターネット動画メディアの決定的な特徴は、送り手だけでなくユーザー側も情報を発信できる「双方向性」が生まれたこと。これによってユーザーの存在が非常に大きくなり、送り手と受け手の溶融が進んでいます。視聴態様の変化も、ここに起因する部分があるでしょう。ユーザー側の選択肢が拡大した今、ユーザーを強く意識したコンテンツの制作、伝播の在り方の変化に対する対応を余儀なくされています。
─ネット動画は、テレビのような"放送枠"がないことも大きいと感じます。
テレビは1日24時間のなかに15分、30分、1時間といった単位で枠が設けられ、そこにコンテンツを入れていくわけですから、搭載できるコンテンツの分量や数が限られますね。
19世紀以降、さまざまなメディアのコンテンツには、ずっとこうした「パッケージの束縛」がありました。LPレコードであれば毎分33回転で片面20分程度、シングル(EP)なら45回転で5分。映画であればだいたい2時間前後。ところがインターネットは、このパッケージの束縛を解き放ってしまう。どんな尺のコンテンツも搭載できますし、サーバーの容量いっぱいまで、あるいはサーバーの容量を増大できるとしたら、原理的にはさらに多くのコンテンツを搭載することが可能です。現にYouTubeには膨大な量のコンテンツが掲載されています。
─縛りがなくなることで、コンテンツの性質も変化しますね。
個人の好みが細分化していくと同時に、一人ひとりの好みに合わせてコンテンツが細分化していき、テレビであれば考えられなかったようなニッチなコンテンツが登場しています。
たとえば、ただ暖炉の焚き火をうつした癒し動画や、『チャーリーが僕の指を?んだ!』のように日常生活を切り取っただけの動画に視聴が集まり、アメリカではマイノリティの人たちが積極的にコンテンツを配信しています。そしてそれらを、テレビのように膨大な数ではなくとも非常に熱心な人たちが支持するのです。日本でも、極めてニッチなコンテンツが、さまざまに存在しています。
今後、メディアの転換がさらに進んでいくと、インターネット動画メディアはテレビメディアのコンテンツ群を包含しつつ、テレビでは不可能だったコンテンツやジャンルを次々と生み出していくでしょう。

放送と通信の有機的結合
─テレビとインターネットを融合させていくために、留意すべきことを教えてください。
2000年代までのような、通信=「放送の補完的存在」「二次展開の新しい供給路・伝送路」といった意識から脱却する必要があるでしょうね。
一斉同報で大勢の人に同時に同じコンテンツを見せることができるのは、テレビならではの特性です。テレビは「第5の壁」ともいわれたように、「常にそこにあるもの」として日常生活に溶け込んでいるので、ユーザーの接し方は受動的になります。対して、インターネットでは細分化されたコンテンツ・情報を、ユーザー自ら能動的に取りにいきます。これはあくまで特性であり、この違いを悲観的に考えるのではなく、テレビはテレビの特性を活かしながら、テレビの受動性とインターネットの能動性を組み合わせるのが良いと考えます。
─具体的にはどのようなことに取り組むと良いのでしょうか?
テレビをつけっぱなしにしてスマートフォンを操作しているという視聴形態もあるので、リアルタイムの放送から思いがけない情報や知らない事柄に遭遇した際、すかさず通信に連携できるサービスができるといいですよね。放送は「あまねく」、通信は「深掘り」の役割を担う。
横軸(放送)で流れるリアルタイムの放送から、そのなかの1点をとらえて縦軸(通信)で深掘りしていくのです。「放送と通信のT字型連動」という形です。NHKがサッカー・ワールドカップのときに制作したアプリがその可能性を感じさせたように、テレビ中継を見て気になった選手のデータや過去のシーンを通信で見ることができるなど、スポーツ中継は特にT字型連動に適応しやすいと考えます。
─そのようなアプローチはリソースに限りがあるローカル局にとってハードルが高いように感じます。
地域で放送に取り組んでいる方々とお話をする機会も多々あるのですが、キー局よりも切迫した危機感を抱いて、なんらかの取り組みを試みようとする意識を持つ方々が多いようです。現在は映像メディアの転換という大変化の最中にあり、対応力が問われているわけです。
放送局の規模や体力に関わらず、変化の実相を観察し、その本質を見極めることが重要だと思います。また、他には無い独自性を確立しグローバルな展開を視野に入れることも一つの方策となると考えられます。
─実現の鍵となる要素はありますか?
今後のAIの発展にもかかっているのではないかと考えています。従来のテレビは労働集約型産業で、優れた技能を持つ人々の共同作業で支えられていますが、通信への展開に際して、ルーティンな部分に関しては、AIの力を借りれば、システムの劇的な改善や省略化が期待できると考えられます。
職人技や芸術的なこと、ジャーナリストとしての取り組みなど、テレビとして重要な部分は残しつつ、通信への展開では、ルーティンに費やしていた時間と労力を他に注げるようになれば、現状では膨大な手間がかかって不可能に見えることも、可能に転じるのではないでしょうか。あるいは、AIの利用とまではいかずとも、業務の流れを見直して組替をおこなうことから始めることもできると思います。これは、かつて現場にいた者としての実感です。
実現のためには、放送と通信それぞれの利点や特性の違い、ユーザーの接し方の違いをわきまえたうえでの組織化、体系化、再現性のある方法論が求められます。放送と通信の連携において、両者を並列的に配置するのではなく、有機的に結合したサービスを設計することが大切です。制作と編成の連携が非常に重要になってくるでしょう。こうした仕組みを構築していくことができた者こそが、次の時代の覇者となる可能性を秘めているのです。

"3つのテレビ"と、テレビの現在地
─放送コンテンツの動画配信は、"テレビ離れ"が著しい若い世代をテレビに触れさせるきっかけになるでしょうか?
"テレビ"と一口に言いますが、実は"テレビ"には、(1)放送波を受信するハードウェアとしてのテレビ、(2)放送波(あるいは放送の免許を与えられた放送局)というメディアとしてのテレビ、そして、(3)テレビ番組すなわちコンテンツとしてのテレビ、という3つの態様があります。
20世紀までは、これらは不可分のものでした。しかし今では、この中からテレビ番組というコンテンツを分けて取り出して、通信で提供することができます。テレビ番組は受像機であるテレビによらずとも、通信回線経由でPCやスマートフォンでも視聴できるようになりました。もう3つのテレビを同一にとらえることはできないのです。
"テレビ離れ"といっても、受像機(ハードウェア)や放送波(メディア)への接触が減っているだけで、コンテンツ、つまりテレビ番組自体はインターネット上でかなり見られているんです。若年層を対象にした最近の調査によると、アメリカにおいてYouTubeで見られている動画のうち、テレビ番組がかなりの割合を占めていることがわかっています。
─コンテンツとしてのテレビは、今も力を持っているということですね。
少なくとも現状では、見られていないわけではありません。ただし、視聴者が従来のような"テレビ"として意識しているかどうかについては疑問が残ります。20世紀なら、番組を見ること=「受像機に向かい合い放送波に接すること」でした。チャンネルをある特定の放送局に合わせてそこで放送している番組を見るといったように。しかし今は多くの人が、そのコンテンツが「どこから来ているか」をあまり意識することなく、テレビ番組に接しています。
日本のテレビ番組は、やはりそれなりの資金を投じて作りこまれていて面白いものもあるので、インターネットでも見られていると考えられます。若年層はテレビ番組に接していないわけではなく、受像機や放送波に接していないだけ。ですから、同時配信でもう一つの伝送路を設けることで、接点が生まれる可能性は十分にあると思います。ただ、通信の利便性の高さに対してどこまで対抗できるか...。
─インターネット動画なら、好きな時間に好きな場所で、好きな長さで、好きなものを選んで視聴できるので、自分の時間を有効に使えますからね。
電車が来るまで2分という場面では2分で見られるコンテンツを選ぶし、アメリカでは社会問題にもなっていますが、帰宅したら他の予定をキャンセルしてでもハマっている動画をビンジウォッチングします。Netflixなどの配信業者はビンジウォッチングが発生しやすいように、非常にうまく設計しています。次がどうしても見たくなったときに「待つ必要がない」という利便性もある。
時間の有効活用や利便性から通信を選ぶ人が多くなる可能性は否定できません。テレビは、ここにどう対抗し作りこんでいくかが課題だと考えています。

バズやミームの種をとらえる編成が鍵
─放送と通信の融合には、制作と編成の連携が重要だというお話がありました。
連携においては編成の役割が非常に大きくなります。コンテンツはクリエイターの力量やセンス、個性で作っていくものであり、"良いコンテンツの作り方"のようなマニュアルがあるわけではないですよね。しかしインターネット動画メディアには、双方向性の原理のなかで「何が視聴者にウケているのか」を、送り手が把握できるという利点があります。その情報をすかさずキャッチして編成を組んでいくことができれば、放送と通信の間にコール&レスポンスが生じます。
この現象が最初に起きたのは、2010年の『セカンド・バージン』(NHK)というドラマでした。当時は、日本ではじめて見逃し配信とアーカイブ配信が連結された頃で、期間限定の見逃し配信だけでは間に合わなかったファンを獲得することに成功したのです。『セカンド・バージン』はSNSで徐々に評判になり、中盤から盛り上がってきたドラマだったので、途中からアーカイブ配信の視聴者数が劇的に増加。その視聴者が本編のリアルタイム放送へと流れる現象が生じたと考えられます。
─他にも事例があれば、教えてください。
同様の現象がもっと大規模に生じたのが2013年の『あまちゃん』(NHK)ですね。いつでも1回目から視聴できたことに加えて、出演者インタビューや地域局制作の関連番組などの派生コンテンツも配信し、ファンダム(強固な支持者の集まり)が形成されていきました。この番組が持っていた「バズが発生する要素」にうまく適合できていたといえます。ほかには2016年の『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS)で、「恋ダンス」というミームが発生し、大きなムーブメントになったことも挙げられます。
これらは意図的に仕掛けられることもあれば、偶発的である場合もあり、バズやミームといったインターネット動画メディアならではの現象が深く関与しています。そうした現象を把握して、ムーブメントを起こす方法論を組織化していくことができるかは編成にかかっています。ネットで広報を打つとか、ディレクターがブログを書く...などという次元に留まるものではなく、もっと大規模な展開が必要なのです。
─"仕掛け"として考えていくことが重要なのですね。
コンテンツの制作過程とディストリビューションを立体的に設計することです。テレビ番組をそのまま通信という伝送路に載せるのではなく、コンテンツの特徴をうまくとらえて、タイミングや、コンテンツのなかにバズやミームの種があるかどうかを見極めて、インターネット動画の適性に合わせた形で意識的に発信・展開していく。これはステルス・マーケティングや炎上狙いなどとは異なるもので、データを常に参照して自然発生した兆しをとらえ、動線の最適化を図っていくというやり方です。

通信における成功の秘訣とは
─コンテンツをより多くの人に見てもらうために、インターネット動画メディアで大切なことはありますか?
確かにメディアとして視聴数が多いに越したことはないのですが、インターネット動画メディアに関する研究では、登録者数のほうに重きが置かれているものがあります。マスを対象にしたテレビとは違い、ユーザーの反応をダイレクトに把握できる動画メディアでは個と深くつながることがコンテンツの内容を高め、結果として再生回数も増加します。
テレビは一斉同報なので、多くの人に見てもらうべく俳優や脚本家にヒットメーカーを起用することがあります。しかしそうすると、現在の一部のハリウッド作品のように、固定客を狙ってヒット作の類似化やシリーズ作品が量産され、同じようなものばかりになっていく可能性もあります。
一方、インターネット動画メディアの場合は、必ずしも「平均的なものが支持される」というわけではありません。無数のコンテンツのなかからユーザーが自由に選べるので、「他にはない」ということが非常に重要。同じようなことをやってもオリジナルには勝てないので、本当に実力が試されてしまう。動画コンテンツのクリエイターには、個性・感性を大事にして、自分が「面白い」と思うことに真剣に向き合い、突き詰めていく姿勢が求められます。
視聴数を事前に知ることはできないとしても、インターネット動画メディアには配信したら即座に反響が得られるという、トラディショナルメディアにはない特性があります。バズやミームといったインターネット特有の伝播の仕方を理解し、視聴者の反響を注視しながら、ファンダムの生成につなげられるかどうかが重要になってくるでしょう。
―ファンダムを生成するような、コンテンツ編成の手法とはどんなものでしょうか?
動画メディアでは視聴者をひきつけてファンダムを生成するために、コンテンツの作り分けと機動的な編成が行われています。
たとえば、Googleは、YouTubeのマーケティングにおいて、「HHH Strategy」という方策を動画制作者に提示しています。HHHとはHero Hub Helpの頭文字をとったもので、動画にそれぞれ役割をもたせてコンテンツを作り分けるという戦略です。
Heroはなるべく多くの視聴者を呼び込むための動画で、大きな話題を集めて注目を高めることをねらっています。Hubは視聴習慣を根付かせることを目的として定期的に配信する動画で、何か得意とする分野に特化して固定客を確保することをねらっています。Helpは予めキーワードリサーチをしてニーズを見極めた上で、そのニーズに答えることにより確実に視聴者を獲得しようとすることをねらっています。
この3種類の動画にキャラクターやデザインなど統一感を持たせた上で、それぞれのサイト内での配置や配信するタイミングも工夫し、データに基づいて逐次修整をおこない、改善を図ります。このように、インターネット動画メディアではテレビとは異なる機動的な編成が行われているので、コンテンツそのものも大切ですが、編成が適応していくことが肝心です。
─確かに、Netflixのインターフェイスはアカウント毎に切り口やコンテンツの並び方も全然違います。
Netflixは2010年代以降、莫大な予算を投入してオリジナルコンテンツの制作に注力していますが、オリジナルに視聴者を呼び込むためにはインターフェイスも重要になってきます。一人ひとりのデータをもとにカスタマイズしてインターフェイスを提供し、動線最適化を行いながら、日々改善している。これを成し得るのが、インターネット動画メディアなのです。
通信は能動的なメディアでユーザーがみずから訪ねてくるので、最初にユーザーと接するインターフェイスは非常に重要です。PCとスマートフォン、ブラウザとアプリで違った仕様に作りこまれ、機械(アルゴリズム)が駆使されている。従来のトラディショナルメディアとは全く次元の違う編成に、テレビ局はどう対応できるかが課題です。

新しい海図と羅針盤を持って大海原へ
─2020年は5Gのスタートという節目の年でもあります。テレビにとっても分岐点になると思いますが、辻先生はどうお考えですか?
2018~2019年に起こった「大登録者戦争」をご存じですか?著名なYouTuberであるPewDiePie氏とインドの配信事業者T-Seriesとの間でYouTubeチャンネルの登録者数を競ったもので、双方とも登録者数が1億を超えるという大規模なムーブメントとなりました。この「大登録者戦争」が起こる前は、長年にわたってPewDiePie氏が登録者数第1位だったのですが、最終的にはT-Seriesが抜きました。
この2者の動画には、それぞれ特徴があり、個人YouTuberであるPewDiePie氏が作るのはUGC(User Generated Content)、一方T-SeriesはPGC(Professionally Generated Content)というレベルの高い作りこまれたコンテンツを強みとしていました。通信が高速化し、大容量の動画でもスマートフォンで視聴できるようになっていたことが、T-Series勝因の一つといわれています。
またT-Seriesが急激に伸ばしてきた背景には、インドで急激にスマートフォンが普及したことも関係していると私は考えています。5Gが普及すれば、テレビ放送があまり発達していなかった国々で、一気に動画配信が広まる可能性があります。固定電話が普及していなかった国で携帯電話が一気に拡がった例もありますよね。後発国が先発国の経由してきた発展段階を省略して一気に最先端のテクノロジーを採用するいわゆる技術的跳躍が、動画メディアでもおこるかもしれません。
─オリンピックは、放送と通信の融合にとって起爆剤となりえますか?
メディアの歴史を見ると、オリンピックは常に節目として存在しています。例えばベルリンオリンピック(1936年)の記録映画『オリンピア』(1938年/ドイツ/監督:レニ・リーフェンシュタール)は、大規模な仕掛けやマルチカメラを駆使して、新しい撮り方でスポーツを描き出し、映像メディアに多大な影響を与えました。また、ロサンゼルスオリンピック(1984年)あたりから、テレビの放映権と絡めて、ビジネスや番組としてもオリンピックの存在感が増しました。放送と通信の連携においても、次のオリンピックは大きな可能性を秘めていると思います。
前述したように、スポーツは放送・通信の有機的結合と相性が良いです。ただし、放映権の問題があります。通信に乗り出すときには、その他にもさまざまな権利処理の問題に直面することになります。
─テレビが駆逐されてしまう危険性はありますか?
今やインターネット動画メディアは急速に成長・進化し、テレビにとって単なる「伝送路の拡充」「広報手段」などではなくなりました。娯楽性と情報性を兼ね備えたうえに、利便性も高い。
メディアとしてのテレビが完全に消滅することはないと考えられますが、コンテンツでは、映画からテレビへの転換に際してニュース映画が劇場から姿を消したように、今後テレビに残らないジャンルが出てくるかもしれません。その一方で、テレビが映画では不可能だった同時中継、クイズ番組やトークショーといったジャンルを生み出してきたように、インターネット動画メディアにおいては、テレビでは考えられなかったジャンルが次々に現れています。
こうした点では、インターネット動画メディアに勢いがあるのは否めませんが、テレビは1980年代の"テレビ離れ"のときに、一度生まれ変わることができました。今度もまた生まれ変わる可能性がないとはいえませんよ。
─放送と通信の融合・連携にあたって、テレビ側にアドバンテージはあるのでしょうか?
GAFAやFANNGと呼ばれる巨大なプラットフォームは、常にデータを参照しながら改善するという取り組みを行っており、今から放送局が規模の点でこれに対抗しうるプラットフォームを築こうというのは、いささか非現実的と言わざるを得ません。
しかし、"放送"というメディアを有していること自体が、テレビ局にとって最大のアドバンテージだと思います。一斉同報するときの規模の大きさや安定性は、やはり放送のほうが優位であるといえます。常時同時配信の開始がテレビにとって分岐点であることは間違いありませんが、一方でテレビは放送波が有する特性を活かせるはずです。
これまでは放送人が「そもそも放送とは何なのか」を突き詰めて考える機会はあまり無かったのではないでしょうか。これからは通信を理解すると同時に、自身(放送)の特性や利点についてもあらためて考察し、理解を深める必要があるでしょう。
また、テレビや新聞などのトラディショナルなマスメディアを支えているのは、経験と訓練によって技能を身につけたプロフェッショナルたちです。彼らの高い倫理観や職業意識によって信頼性が担保されるはずだという前提があります。テレビとして矜持をもって取り組んでいくべきだと思います。いたずらに怯えたり恐れたりせずにね。
─心して望む必要がありそうです。
「iPlayer」が2007年に始まっていることを考えれば周回遅れではありますが、いよいよ踏み出したということですね。この先に進んでいく通信の世界は、いうなれば大海原で、放送とは全く異なる海域ですから、遭難しないようにするためにも、海図をしっかり備えておく必要があると思います。
通信の特性や現状を理解するとともに、今まで自分たちが携わっていた"放送"というものが何なのかを今一度問い直し、両者の特性を活かすような設計ができるかどうかです。「変化の時代に生き残るのは"最強の者"ではなく"変化に対応できた者"である」といわれていますから。
常時同時配信で今までより利便性が高まることは確かでしょうし、ユーザーとの接触が深まる可能性もある。そのこと自体は歓迎すべきことですが、重要なのはそこから先の設計です。今はあくまで出発点にすぎず、船出をしたところ。船出をしてみたら10年前の穏やかな内海とはすっかり様変わりして、そこは大海原であったと。新しい海図や羅針盤が必要ということです。情報収集をして、"放送"と"通信"、両者の特性をよく理解したうえで、大海に乗り出していくことが必要なのではないでしょうか。
─貴重なお話、ありがとうございました。
<了>
筑波大学 メディア論教授 辻 泰明 (つじ やすあき)さん
筑波大学教授。博士(情報学)。東京大学文学部フランス語フランス文学科卒。
日本放送協会において、ドラマ部、ナイトジャーナル部、スペシャル番組部、教養番組部などで番組制作に従事。その後、編成局にて視聴者層拡大プロジェクトおよびモバイルコンテンツ開発、オンデマンド業務室にてインターネット配信業務を担当。著書に『映像メディア論 ─映画からテレビへ、そして、インターネットへ』、『インターネット動画メディア論 ─映像コミュニケーション革命の現状分析』ほか。