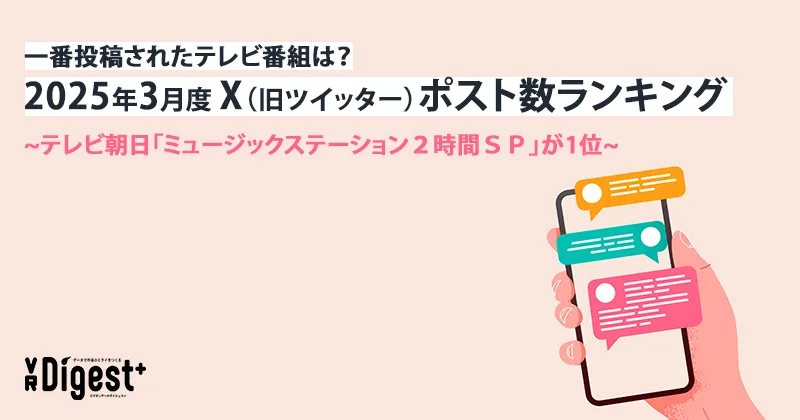てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「貴島誠一郎」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第9回
「株を売るより、夢を売りたいんです!」
山一證券の営業マンだった男がTBSの中途採用試験を受けた際、そう言い放った。
のちに『ずっとあなたが好きだった』(1992年)で「冬彦さん」ブームを巻き起こす名プロデューサー・貴島誠一郎氏である。
その後も『ダブル・キッチン』(1993年)、『誰にも言えない』(1993年)、『スウィート・ホーム』(1994年)など次々にヒットドラマを手がけ、1995年には豊川悦司、常盤貴子主演の『愛していると言ってくれ』を大ヒットさせた。このドラマが、今年5月31日から4週連続で「2020年特別版」として放送されたのも大きな話題となった。
貴島はもともと映画青年でもドラマ青年でもなかった。ただ人気企業に憧れる"ミーハー気質"だったため金融会社に就職したが、実際に働いてみるとお金を扱う仕事が性に合わず、TBSに飛び込んだ。
テレビ局に入ったら、やはり制作をやりたいと思うだろう。貴島も研修では制作を希望したが、配属されたのは営業だった。前職の経験から、会社は営業のエキスパートとして期待していたのだ。
その後、編成に異動し、再放送担当となった。それまでドラマの再放送には一定のルールがあったが、貴島は『高原へいらっしゃい』や『天皇の料理番』など、自分が見たいと思うものを選んだ。また、自分なりに工夫し、それぞれのドラマに合った時間帯に編成するようにした。すると、17時台で再放送した『スクール ウォーズ』や『3年B組金八先生』が高視聴率を獲得したのだ。
その手腕を買われたのか、貴島は30歳を過ぎて制作に異動になった。だが、年をとっているだけで、制作のことは何もわからない。邪魔な存在になってしまった。だから、普通のADでは経験の少ない、スケジュール管理や他部署との交渉事などを行うAPの仕事を進んで行うことにした。それなら営業や編成の経験を活かせるからだ。
初めて彼がプロデュースしたのは1991年の『結婚したい男たち』。当時はフジテレビのトレンディドラマ路線が大当たりしていた。それを後追いしたようなドラマだった。その結果、視聴率は尻すぼみになる惨敗だった。
その反省を生かして生まれたのが『ずっとあなたが好きだった』だ。貴島は、フジテレビとTBSのドラマを徹底的に研究し、当時の視聴者の見たいものと、TBSの伝統の「ホームドラマ」を組み合わせられないかと考えた。「フジテレビがロケ中心でやっているのに対し、TBSはほとんどスタジオ。ホームドラマの強みを生かしてロケで新鮮につくれないか」(※1)と。
バブルとトレンディドラマが生み出した理想の男性像は"三高"。けれど、「結婚相手として"三高"の冬彦さんでいいんですか?」というアンチテーゼを込めたドラマが『ずっとあなたが好きだった』だった。だから当初"マザコン"のドラマという意識はなかった。けれど、1話目を撮影している現場で、冬彦さんに扮する佐野史郎の演技を見て、「これは今までのドラマと違う面白さがある」(※2)と感じた。すぐに貴島は脚本を担当した君塚良一に「このキャラクターを強調したい」と伝えた。貴島の直感通り、冬彦さんは大きな話題となり、視聴率は尻上がりに高くなっていった。
貴島のドラマは、『ずっとあなたが好きだった』に限らず、開始当初はそれほど視聴率が高いわけではないが、後半になってどんどんと上がっていく作品が少なくない。
彼のもとで"修業"した『ケイゾク』『SPEC』などを手がけたプロデューサー植田博樹は、貴島がいつも「アイデアの総量が作品の質を決める」からと「全てのスタッフは、毎日1つずつアイデアを持ってきてください」と言っていた、と証言している(※3)。
プロデューサーとしては台本どおりに撮ることが一番効率がいいと思ってしまいがち。けれど、みんなのアイデアを取り入れることで少しでもブラッシュアップしていくのだ。
たとえば、冬彦さんは蝶の標本をコレクションしている。これは「生きている女性を愛せなくて標本のようにしたがる」彼の側面をわかりやすくあらわすものだった。だが、君塚が貴島との話し合いの下に書きあげた台本では蝶の標本ではなくエロ本だったという。
「僕と脚本の君塚良一さんの発想だとエロ本なんですよ(笑)」(※3)
それを美術プロデューサーの提案をすぐに採用し変更したのだ。重大なモチーフを自分たちの発想にこだわらず、いいと思えばギリギリまで柔軟に対応していく。そのようにして"木馬"のシーンも生まれたのだ。
貴島は「もともとクリエイティブな人間じゃない」というコンプレックスがあった。だからヒット作を生んでも「ビギナーズラックが続いた、ただのアマチュア」だと思い続けた。
当初は「プロデューサーは企画者であり責任者であり、すべてを引っ張っていかなきゃいけない」と思い込み、自分で苦しくなっていた。けれどある時から「作家や役者さんの力を借りていいものを創ればいいんだ」という発想を持てるようになり、一気に仕事が楽しくなった。
「プロデューサーは、自分の才能を使って何かを創っていくというより、人の才能を活かす仕事」なのだ(※2)。
そうして貴島は「テレビはライブ」(※1)という信念のもと、積極的に周囲からのアイデアを取り入れ、評判のいい部分を伸ばし、ライブ感覚でドラマを育てていったのだ。
※1 ビデオリサーチ:編『「視聴率」50の物語』(小学館)
※2 伊藤愛子:著『視聴率の戦士』(ぴあ)
※3 木俣冬氏 Yahoo!ニュース記事 2020年6月7日 https://news.yahoo.co.jp/byline/kimatafuyu/20200607-00182158/
<了>