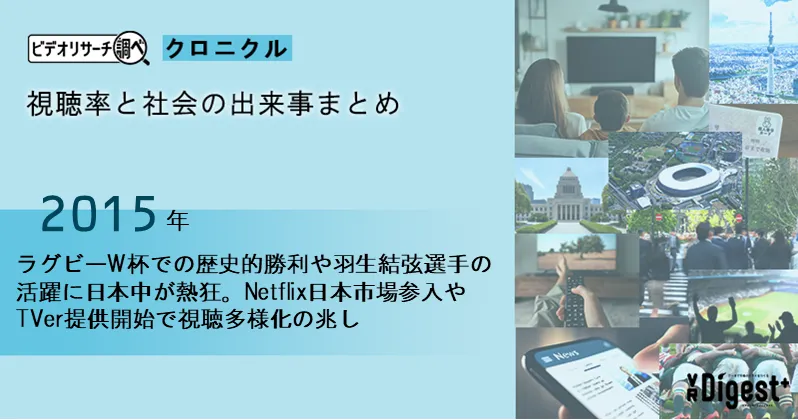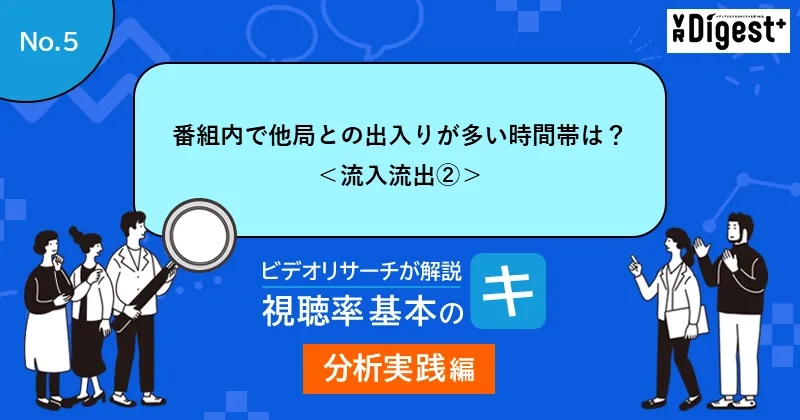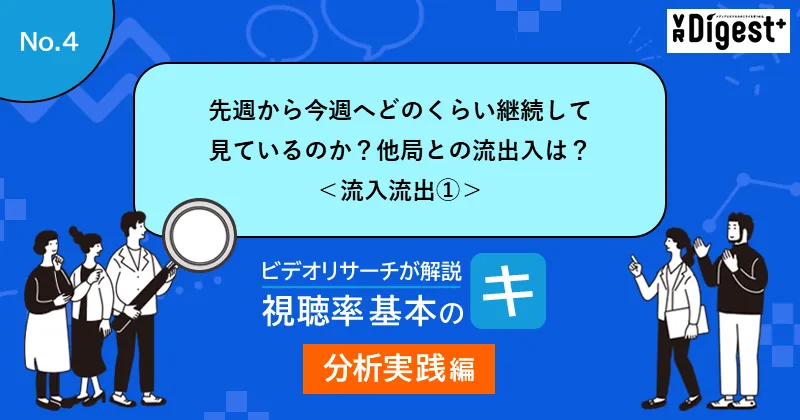てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~「関口静夫」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第11回
関口静夫といえば、フジテレビで三谷幸喜と組んだ『振り返れば奴がいる』、『古畑任三郎』シリーズ、『王様のレストラン』、『総理と呼ばないで』、『HR』などを、企画の石原隆とのコンビで手掛けたプロデューサーとして有名だ。君塚良一と組んだ『TEAM』や『さよなら、小津先生』も印象深い。
現在は、FODで配信される純烈の4人を主人公にしたドラマ『純烈ものがたり~スーパー銭湯が泣いている~』のプロデュースを担当している。
もともとドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー等、なんでも見る"テレビっ子"だったという関口は、テレビにかかわる仕事に就きたいと早稲田大学在学中にTBSでバイトを始め、やがて制作会社「テレパック」に入社した。
『渡る世間は鬼ばかり』などで知られるプロデューサー・石井ふく子のもと、『肝っ玉かあさん』や『ありがとう』などの制作現場で鍛えられた彼は、自然と役者や脚本家との付き合い方や、ものづくりのスタンスを学んでいった。
「トランプカードの組み合わせみたいな企画では人の心を打たないということを、教えられなくても感じられたというか。人に対する思いやりや、ものを創る時の思いの大切さとか、勉強したつもり」(※1)
当初はディレクター志望だった関口はある時、大きな"失敗"をしてしまう。
20代前半の頃だ。「ディレクターとして1本撮ってみないか?」という話が来た。大抜擢だった。けれど、出演者は乙羽信子などの大物ばかり。自分のような若造が演出をつけるなど考えられなかった。勇気が出なかったのだ。
「もうちょっと時間をください」
関口はそのチャンスを棒に振ってしまった。だが、棒に振ったのはその一度のチャンスだけではなかったと後で知ることになる。
後から「二度とチャンスはない」と先輩から言われた。
「誰も若いおまえに完璧な仕事を求めてたわけじゃない。関口がデビューするなら、助けてあげようと言って、役者もスタッフもみんなでアイディアを出し合ってたんだ。なのにおまえは逃げた。せっかくの思いやりを自分で蹴ったんだ。だからこれから先、演出する機会はない」(※1)
大きなショックを受けたが、それにより仕事に向かう心構えが変わった。
そして、自分が目指すのは、ディレクターではなくプロデューサーだと決めた。
そうしてプロデューサーデビューしたのは28歳のときだった。
その時、それまで大好きだったジーパンを全部捨てた。それくらいの覚悟だった。プロデューサーならば、たとえ若くてもお金の話や交渉事をしなければならない。その時に「ガキ」だと思われたくなかったからだ。だから、関口はいわゆる「業界人」っぽいようなファッションはせず、きちんとしたスーツ姿で丁寧な言葉づかいを貫いている。
36歳の頃、共同テレビに"移籍"した。
「プロデューサーという名前とポジションを得るためには、ヒット作がなければダメです。何本かのヒット作がないとプロデューサーとは言えません」(※2)
関口にとってそのひとつだったのが『OL三人旅』シリーズ(フジテレビ)だ。『金曜女のドラマスペシャル』枠で放送された2時間ドラマ。主人公3人も交代しながら、1986年から約10年間にわたり十数回制作された。このシリーズで「当て線」をつかんだという彼は、40代で三谷幸喜と出会った。
『やっぱり猫が好き』を見て三谷の脚本に惚れ込んだ関口は『やっぱり猫が好き殺人事件』で初めて三谷と組んだ。第1シーズン終了後に制作された2時間ドラマで「倒叙」もの。『古畑』の原点ともいえるだろう。
三谷幸喜は一般的には遅筆だと言われている。事実、『古畑任三郎』制作の際も撮影を遅らせざるを得ないときもあった。
だが、三谷の場合、アイディアが沸いてこないから遅いわけではないと関口は言う。逆だ、と。アイディアが思いつきすぎて、どれを選べば一番おもしろくなるか迷うために遅くなってしまうのだという。
だから関口がアイディアを思いついて提案すると「それは当然もう考えました」と言われてしまう。「それも面白いんですけど、それでは後半に破綻をきたしてダメなんです」と(※1)。
もちろん、撮影が遅れてしまえば、それだけ予算が増えてしまう。
けれど、三谷の脚本を「待つ」ことに躊躇はなかった。
二度とチャンスはないのだ。妥協して後悔するわけにはいかない。
「三谷さんに身も心も捧げたわけですから(笑)。面白い作品をやれるなら、社内でペナルティをかぶってでもやりたいって気持ちになるんです」(※1)
リスクを背負う覚悟がなければプロデューサーは務まらない。
「視聴率が悪ければ責任を取る、良ければ次の話を進める、これがプロデューサー」(※2)だ。
「泣いた笑ったいい話だったあれは良く覚えてる、っていうような作品を作り続けて、それを視聴者の心に送り込む」(※2)。
そんな幸せな仕事はないと関口静夫は語るのだ。
※1 伊藤愛子:著『視聴率の戦士』(ぴあ)
※2 「共同テレビブログ テレビ人・見聞録」 2006年1月4日 http://blog.livedoor.jp/kyodo_tv/archives/50350509.html
<了>