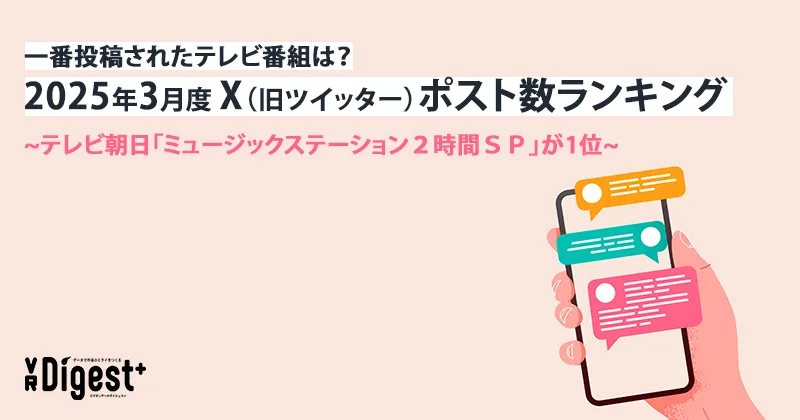てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「細野邦彦」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第12回
「これが名器だ!」
ある日の深夜番組『11PM』(日本テレビ)のラテ欄にそんな文言が踊った。お色気も扱う深夜番組で「名器」。世の男たちは「もしかして......」という下心でチャンネルを合わせた。だが、映し出されたものはピアノやバイオリンの"名器"。それでも、高視聴率を獲得した。
そのようにして細野邦彦は人間の欲望を刺激するのに長けていた。
細野邦彦は立教大学時代、硬派でケンカに明け暮れていた。趣味であるウッドベースのケースの中に匕首(あいくち/短刀の一種)を忍ばせていたという"伝説"まであるほど。ジャズプレイヤーのチコ・ハミルトンが好きなことから日本テレビ入社後、いつしか「チコ様」と呼ばれるようになった。
親のためにも就職しなければと考え、テレビ局なら朝早く行かなくてもいいだろうというのが、入社動機だった。けれど、配属されたのはよりによって朝の生放送番組。毎日寝不足だった。
彼は「自分は細野商店の店主」と自称していた(※1)。つまり、日本テレビに軒を並べる店主のひとりという考え方。テレビ局の組織の歯車ではなく、一匹狼の精神を貫いていたのだ。
細野にとって最初の大きなヒット作となったのは、入社6年目にプロデューサーとして手掛けた『踊って歌って大合戦』だろう。
初代林家三平を司会に抜擢した。既に落語家としては人気だったが、バラエティタレントとしては未知数。そんな彼を、「自分勝手にデタラメなことをやらせたら受けるだろう」と閃き起用したのだ。ヤカンいっぱいの水を飲ませたりして、彼の芸人としての欲求を刺激し、バラエティタレントとしての才能を開花させたのだ。
『テレビ三面記事 ウィークエンダー』では、「ハイブローなことよりも、人間が誰しも関心のあるローブローのことを、そのままストレートに見せるのではなく、綺麗にパッケージして見せることが大切なんだ」(※2)と、下世話な事件を映画のBGMでオシャレに包み込んだ。
そして1969年、細野にとって難題が降り掛かってくる。
NHKはその年、豪華キャストを揃えた大河ドラマ『天と地と』を放送。民放各局の日曜夜8時台の視聴率は軒並み一桁台に落ち込んだ。日本テレビでは、その時間帯のスポンサーが降りかねない状況になっていた。そこで細野にお鉢が回ってきたのだ。
視聴率を挽回することは厳命だった。しかし、負け戦になるのは濃厚。多くのプロデューサーが断った。なにしろ一度ゴールデンで失敗したら、一生窓際族になってしまうような時代。躊躇するなという方が無理だ。細野も一度は断ったが「何をやってもいいんだな」と念を押して引き受けた。
司会には既にコント55号の起用が決まっていた。
当時、彼らは人気絶頂。各番組で即興のコントを披露し、一時代を築いていた。だが、細野の目にはその勢いが収束しつつあると映っていた。
彼らのコントを流すだけでは絶対に『天と地と』には勝てない。
そう考えた細野は、彼らが「いない」と想定してイチから企画を考え始めた。もともと細野はタレントに依存する番組を「ポン引き番組」と評し嫌っていた(※3)。あくまでも面白い企画ありきなのだと。
最初に舞台をコロシアム形式にするというのを思いついた。観客がステージを取り囲むように座る。そうすることによって、カメラが映し出す方向にも観客がいることになり、客の表情がハッキリと画面に映し出される。つまり「お客もセット」にしたのだ。当時は画期的なことだった。大河ドラマに比べれば遥かに低予算。豪華キャストに対抗するために考えついた奇策だった。
では、そんなコロシアムのセットで何をすればいいのか。
細野は頭を悩ませた。
強力な裏番組に対抗するためには、まともな戦いでは勝てない。ならばゲリラ戦しかない。
「テレビでしかできないこと」、それでいて「人間の本能にぶつければ絶対に番組は当てられる」と細野は考えた(※4)。
そうして、ギリギリになって「野球拳」の企画を思いついたのだ。
けたたましいビートに乗せた「やーきゅうすーるなら♪」という歌に合わせて坂上二郎と女性タレントがジャンケンをする。女性タレントがジャンケンに負けるたび、一枚ずつ服を脱いでいく。その一挙手一投足に観客は熱狂した。その本能むき出しの観客の表情を見て視聴者も興奮していく。
それこそが"伝説の低俗番組"ともいわれる『コント55号!裏番組をブッ飛ばせ!!』だ。ちなみに脱いだ服はその場でセリにかけられ観客が買う。その売上金は交通遺児に寄付されるというチャリティー番組でもあった。
そしてタイトル通り、裏番組の大河ドラマを見事視聴率で追い抜いた。もちろん、この番組に対して「低俗」だという批判が殺到した。
だが、細野は「『低俗』批判で反省することは一度もなかった。だって娯楽は、一種の不良性をともなうもの」(※5)とまったく気にしていなかった。
一方で司会の萩本欽一が企画に納得していないのは感じていた。
「つらいだろう、やめたいと思ってないか?」
細野は萩本に声をかけた。
「でも男の意地があるんだ。ワースト番組なんて言われて、ものをつくる人間がそんなことでやめちゃいけない。オレは戦い抜く。欽ちゃん、どうだい?」
萩本はそんな風に目を見据え言われ、男気を感じた。
「ついて行きます」
思わず萩本は答えた(※6)。
細野邦彦は、視聴者の欲望を刺激することに長けていた。だが、それだけではない。
林家三平や萩本欽一といった、タレントたちの本能を刺激することにも長けていたのだ。
※1 『放送文化』2000年1月号(NHK出版)
※2 戸部田誠『全部やれ。』(文藝春秋社)
※3 『映画秘宝EX モーレツ!アナーキーテレビ伝説』(洋泉社)
※4 吉川圭三「メディア都市伝説」(水道橋博士のメルマ旬報)
※5 『GALAC』2003年4月号(放送批評懇談会)
※6 日本テレビ50年史編集室編『テレビ夢50年』③(番組編日本テレビ放送網)
<了>