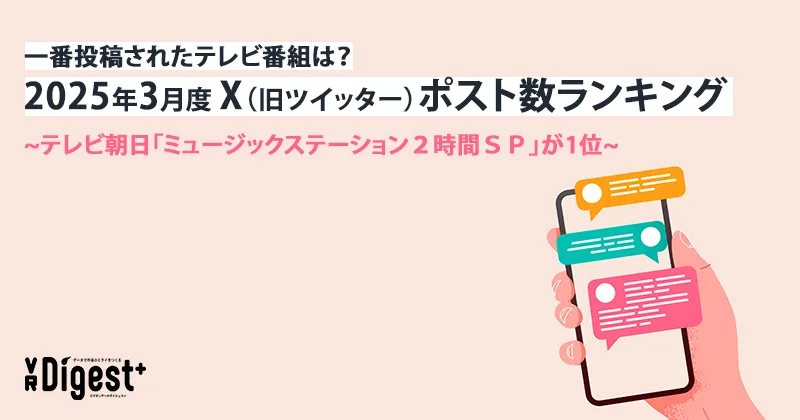てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「佐藤義和」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第14回
今年10月28日、移住先の沖縄で肺がんのため72歳で亡くなった佐藤義和。
佐藤義和は言わずと知れたフジテレビの黄金期を支えたプロデューサー・ディレクター。『オレたちひょうきん族』では「三宅デタガリ恵介」らとともに「ひょうきんディレクターズ」の「ゲーハー佐藤」として番組内に登場し、『笑っていいとも!』ではタモリらから「サトちゃん」と呼ばれ、よく話のネタにされていた。
佐藤の最初の大きな功績は、「漫才」を変えたことだ。
70年代、漫才を始めとする演芸はテレビの世界では衰退の一途をたどっていた。まともに放送されるのは年末年始などくらい。演芸はお年寄りが見る「古いもの」というイメージがはびこっていた。そんな演芸番組を変えたいと考えていたのが「演芸班」にいた横澤彪だった。
1980年4月、予定されていた単発の特別番組枠『火曜ワイドスペシャル』の企画が中止になった。年度初めの特番で各局強力な番組がラインナップされていたため、音楽班やドラマ班が尻込みする中、演芸班にお鉢が回ってくることになった。
横澤は以前から温めてきた「漫才の東西対決」というコンセプトの番組をすることになった。その実質的な制作を担ったのが佐藤義和だった。佐藤もまた横澤同様、なんとか演芸番組を変えたいと考えていた。
横澤と佐藤が初めて仕事を共にしたのは1980年の元旦に放送された『第13回初詣!爆笑ヒットパレード』。佐藤の仕事ぶりを見て信頼を寄せた横澤は、演出に抜擢したのだ。
佐藤は1971年、フジテレビ系制作会社「フジポニー」でアルバイトとしてテレビマン生活をスタートさせ、74年に正式に入社。76年、演芸番組『日曜テレビ寄席』でディレクターに昇格した。
当時フジテレビは低迷していた。中でも「演芸の活気のなさは目を覆うほど」だったと佐藤は述懐する。
「制作子会社のディレクターである私に、この状況を打開する権限もチャンスも与えられなかったが、とにかく私は、毎日のように浅草に通った」(※1)
担当の演芸番組に使うために、演芸場での芸を実際に見て、テレビ用に再構成する打ち合わせをする必要があったからだ。
そんな経験から「これからの笑いをつくっていくという役割をベテランの芸人さんたちが担うことはできない」(※1)と佐藤は判断していた。同時に、凋落しているようにも見える浅草にも、ツービートを筆頭に新しい息吹が生まれてきていることを実感していた。
演芸場通いでの最大の財産は「若い芸人さんたちとの出会い」だったのだ。
「その多くは、前世代のスターである師匠のトレースをする従順な弟子たちだったが、僕の目をひいたのは、前世代をまったく無視するかのように投げやりにしゃべりまくる連中だった」(※2)
彼らは当然、伝統的演芸場の多くの中高年の客には受けなかったし、正統派演芸番組を作るテレビマンたちからも無視されていた。だが、佐藤は「自分自身の不遇を彼らの姿に投影」したのだ。
「エネルギーだけはひしひし感じた。そして旧体制に反発する姿勢に共感した。僕の『変えたい、変えたい』という鬱々とした心の叫びと同様なものを確かに彼らも訴えていた」(※2)
新世代の漫才師たちと様々な形で交流を持っていた佐藤は、横澤からの打診を受けて、この若い世代たちを中心とした番組にしたい、と考えていた。
そこで佐藤が抜擢したのがツービート、星セント・ルイス、B&Bだった。
「お前、そんなマイナーな連中だけで演芸番組をつくって大丈夫か?」
当然、先輩たちは訝しんだ。単発特番といっても、20時からの90分の枠。ゴールデンタイムである。
「テレビの世界に身をおいて9年目にして、初めてゴールデン枠を手にしたのだ。失敗したら二度と手に入らないビッグチャンスだ。私にできることは、今まで地道に蓄積してきたノウハウを込め、さまざまな形で出会ってきた若手芸人を世に問うことだけである」(※1)
もう従来の演芸番組の路線は完全に煮詰まっていると感じていた佐藤は「"失敗してもいい。思い通りの番組を作ろう"」(※2)と意に介さなかった。
新世代中心の出演者が決まれば、それに合わせ、その舞台も新しいものでなければならない。そこで佐藤はディレクターに永峰明を誘った。
永峰は当時26歳。佐藤より6歳若く、ファッションや音楽に造詣が深かった。それ故、演芸部門のスタッフとしては異質で、不遇の扱いを受けていた。
だから、佐藤は「彼なら、今までの演芸番組からは予想もつかない演出をしてくれる」(※2)と確信していた。
佐藤は永峰と構成作家を務める大岩賞介とともに「音楽はディスコミュージックがいい」「装飾も派手でバタくさいものにしたい」などと話し合った。そんな意図を伝え美術デザイナーに発注した佐藤は、あがってきたセット図面を見て驚愕した。中央に見慣れぬ電飾の文字が書き込まれていたのだ。
「THE MANZAI」
これだ!と佐藤は直感した。当初はカタカナで『ザ・マンザイ』と考えていた番組のタイトルも『THE MANZAI』という表記に統一しようと決めた。
新聞のラテ欄で、ローマ字表記は今までない。なんの番組だか分からない。営業からも「売れない」と猛反発された。「変えてくれ」と。
だが佐藤は「絶対嫌だ」と『THE MANZAI』というタイトルに頑なにこだわった。
セットやタイトルだけでなく、演出面でも革新的だった。
芸人たちは敏感にそれを感じ取っていた。佐藤は述懐する。
「ステージに上がると、どのコンビも、いつも以上のスピードで疾走した。機関銃のようにギャグを連発し、まさに息もつかせぬ迫力にあふれていた。これに観客席の若い観衆は、中高年の客では絶対ついてきてくれないハイテンポなネタにしっかりついてきてくれ、笑わせたいポイントで笑ってくれるのだ。出演者たちは、打てば響く快感を味わっていた」(※1)
そんな漫才師たちの躍動した姿を映すカメラアングルも工夫を凝らしていた。
これまでの演芸番組では真正面の引きとアップしかなかったが、左右や背後など様々なアングルから舞台を映し、ある種の「ドキュメンタリー性」を強調した。そうして『THE MANZAI』を象徴する、漫才師の背中越しの客席の映像が生まれた。さらにスピード感を強調するため、冗長な漫才は間を編集でカットしたという。
その結果、80年4月1日、ドリフターズによる『テレビ祭り 4月だョ!全員集合』の裏番組という悪条件で放送された『THE MANZAI』第1回(正式タイトルは『THE MANZAI 翔べ!笑いの黙示録東西激突!残酷!ツッパリ!ナンセンス』)は15.3%という予想をはるかに上回る高視聴率を獲得した。
いや、この第1回の収録は間違いなく視聴率以上の成果を手にした。それは新たな時代に求められている「笑い」の方向を明らかにしたことだった。
佐藤にとって『THE MANZAI』はもはや"演芸番組"ではなかった。それどころか"漫才"とも考えていなかった。
「一種のトークショー」(※3)だと言うのだ。
「漫才じゃなくて、メッセージだよ。あなたたちのメッセージを若いお客さんに向けて発信してくれればいいっていう。歌の世界でもシンガーソングライターが、自分で曲を作って、自分で歌って表現するっていうのが、すごく若い人にウケてる。新鮮だったし。漫才もそうなんじゃないかなと」 (※4)
こうして、自分の言葉で発信するビートたけしを始めとする時代を代表するスターを生んだのだ。
佐藤はその後も『オレたちひょうきん族』を演出する傍らで『冗談画報』などをプロデュースし、新しい時代のスターを生み出そうと常に模索し続けたのだ。
※1 佐藤義和『バラエティ番組がなくなる日―カリスマプロデューサーのお笑い「革命」論』(主婦の友社)
※2 佐藤義和『他人の才能でメシを食う方法―テレビマン、ヒットの秘策』(同朋舎出版)
※3 『週刊サンケイ』(産業経済新聞社)1980年11月20日
※4 朝日放送『漫才歴史ミステリー!?笑いのジョブズ?』2013年3月24日
<了>