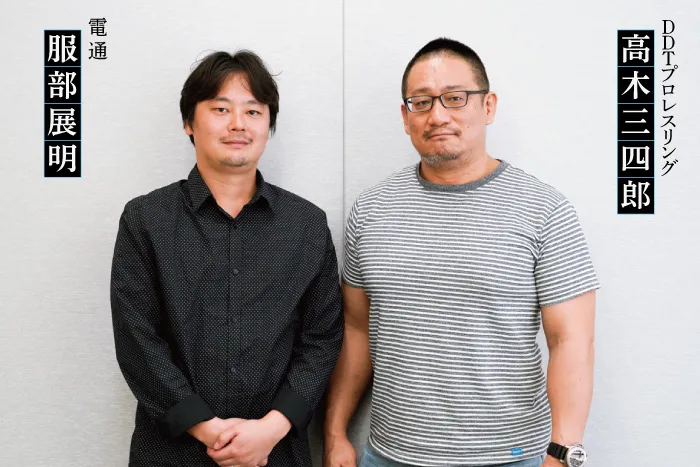〜イベントプロデューサーから、インディープロレスラーへ〜エンタメを極めるDDTプロレスリングの独自性 Vol.1
(左から) 電通 服部 展明氏 DDTプロレスリング 高木 三四郎氏
インディー系のプロレス団体として旗揚げしてから20年。いまやメジャー団体に迫る人気を誇るまでに成長を遂げた「DDTプロレスリング」にあって、レスラー兼社長を務める高木さん。
そして、以前からDDT独自のマーケティング手法などに強い関心があったと語る電通の服部さん。
今回はこのお二人に、プロレスの枠を超えてエンタメ業界全体に広がりつつあるDDTの魅力について語り合っていただきました。随所にお二人のプロレス愛が炸裂する対談をお楽しみください。
高木 三四郎
DDTプロレスリング代表取締役社長であり、現役プロレスラー。
エンタメ性の高い興行で日本武道館や両国国技館での大会を成功させるほか、「路上プロレス」やアイドルとのコラボレーション興行、飲食店やストレッチ専門店の経営など新しいことにも臆せず挑戦する。業界屈指のアイデアマンとして業界内外から注目される。
服部 展明
株式会社電通第1CRプランニング局コミュニケーションプランニング1部クリエーティブ・ディレクター。
1999年に電通に入社後、ストラテジック・プランナーとして、自動車・精密機器・飲料・食品・通信など様々なクライアントを担当。2012年よりCRプランニング局、14年より現職。
イベントプロデューサーから、インディープロレスラーへ
服部
今日はプロレス界を破竹の勢いで席巻する「DDTプロレスリング」において、社長兼レスラーとして活躍される高木さんとお話しできるということで、楽しみにしてまいりました。今日はよろしくお願いします。
高木
なんだか緊張します(笑)。こちらこそよろしくお願いします。
服部
私は幼い頃からプロレスが大好きで、いろんなプロレス団体を見てきましたが、高木さんが経営するDDTプロレスリングは、中でも非常に面白い存在といえます。最初は小さなインディー団体だったのが、いつの間にか新日本プロレスなどメジャー団体と並ぶほどの存在感を発揮するまでに成長しています。今日はぜひ、その成長を成し遂げた独自の戦略について、お聞きしたいと思います。
まずは、高木さんがプロレスに関わるようになった経緯からうかがえますか。
高木話せば長くなってしまいますが(笑)。僕ももともとプロレスが大好きで、大学を卒業したあと、学生時代から手掛けていたイベントの企画やプロモーションなどの仕事をしていたときに、どうしてもプロレスへの夢が断ち切れずにいたんです。それで縁あってPWC(プロ・レスリング・クルセイダース)という団体に所属することになったのがプロレスラーとしての始まりです。
服部
PWCといえば、全日本プロレスなどで活躍していた高野俊二(現:拳磁)さんの団体ですよね。高木さんが所属していた頃は、どんな状況でしたか?
高木
PWCはご存知の通り、インディー団体のなかでも小規模な団体で(笑)、スタッフも少なかったので、僕は学生時代からの経験もあって、新人レスラーながら運営企画にも関わっていました。
当時のインディーブームに支えられたこともあり、後楽園ゆうえんちでやった「真夏のルナパーク」というビアガーデンでプロレスが観戦できるイベントが当たったりして、それなりに好調だったんですが、ここでは言えない紆余曲折があって突然解散することになったんです(笑)。
少しの間プロレスからは離れていたんですが、PWCに所属していた僕と同世代の選手の一部から、どうしてもプロレスがやりたいと相談されて...。
最初は断ったんですけど、みんなの熱意にほだされて、まずは小さな規模でもいいから団体を立ち上げることに。それがDDTの始まりです。

スターレスラーが一人もいない、プロレス界の異端児として旗揚げ
服部
当時のプロレス界は、全日本プロレス、新日本プロレスが2大メジャーとして君臨するなかで、UWFやSWSといった団体も登場して、でもそれらが分裂したことによって、インディーと呼ばれる小さな団体が乱立し始めていた時代ですよね。
高木
そうですね。でもUWFには前田日明さん、SWSには天龍源一郎さんといったスターレスラーがいました。また、PWCを含めたいわゆるインディー団体でも、各団体に一人はメジャー団体で活躍していたレスラーがいて、それが集客力の要となっていました。
DDTにはそうしたビッグネームが一人もいないという点で、異色の存在でしたね。
実際、業界ではすぐに消えると噂されていたようです(笑)。
服部
失礼ながら、当時、私もそう思っていました(笑)。
高木
いやあ、誰でもそう思いますよ(笑)。
でも、そうした周囲の冷たい反応に対して「今に見てろよ」という悔しい気持ちも沸いてきて、それが原動力になったのも事実です。
それと、プロレスファンの気質としては、落伍者が諦めずにチャレンジして、少しずつ成長していくストーリーが大好きなんですよ。だから、自分たちのような知名度のない団体でも、ハードルをひとつずつ越えていけば、必ずファンに支持されるという気持ちもありました。
服部
旗揚げ興行はいかがでしたか?
高木
まず本格的に旗揚げをする前に、「プレ旗揚げ興行」を開催して、お客さんに「DDTを本当に旗揚げしてもいいかどうか」というアンケートをとったんです。プレイベントには270人ほど観客が集まってくれて、その中でアンケートでは150人くらいが旗揚げに賛同してくれて。
決して多いとは言えませんが、こんなに僕たちを支持してくれる人がいるのかと勇気づけられましたし、小さいながらも手応えを感じましたね。
服部
なるほど、本興行の前にそうしたイベントを開催するというアイデアはさすが。
その頃からすでに高木さんは仕掛け人だったんですね。
いち早くエンタメ路線に振り切ることで、プロレスの新時代を開く
服部
DDTの設立当時は、どんなカラーの団体だったんですか?
高木
最初は試行錯誤の連続でしたね。
設立当初のメンバーは、元PWCの選手が中心で、そのなかでも先輩後輩があって、先輩の人たちには木村浩一郎さんなどの"格闘家スタイル"の選手が多かったんです。
服部
じゃあ、最初は総合格闘技色の強い試合が多かったんですか?
高木
そうなんですよ。僕たち後輩レスラーが、先輩レスラーにひたすらボコボコにされて終わるというような、お客さんからすれば、これはプロレスなのか、それとも格闘技なのか、よくわからない感じだったんです。当時はプライドやUFCが登場して"総合格闘技スタイル"が人気を集めていましたが、僕たちみたいな資金力も知名度もない団体がそのスタイルで頑張ってみても、最終的にはジリ貧になるな、と。
このスタイルでは続かないと考えていたときに、ある人からアメリカのプロレス団体WWF(現WWE)の映像を見せてもらったんです。
それを見ると、試合前の控え室で社長と所属選手がケンカしているのを映像で流したり、車を壊したり、試合はそっちのけでメチャクチャなことをやって盛り上がっているんですよ。それで、こんなやり方もあるんだと気づいて、これは日本ではまだ誰もやってないから、自分たちがやれば絶対ウケると思ったんです。
服部
当時も今も、アメリカンプロレスは、いわゆる"ショーマンスタイル"で、日本のプロレスファンや関係者からはあまり評価されていませんでしたよね。
日本のプロレスは、アントニオ猪木さんが提唱した"ストロングスタイル"に代表されるように、多少のスタイルの違いはあれ、基本的には「強さ」を競うという点で一貫していて、アメリカンプロレスのようにエンタメに特化した団体はほとんどありませんでした。

高木
そうなんです。でも、WWEはそのスタイルで毎週1万5000人くらいのお客さんを集めていて、日本とは比べものにならないくらい集客力があったんですよね。
もちろん、お国柄やプロレス観の違いはあるでしょうが、そっちの道こそ可能性があると思ったんです。
服部
当時はまだエンタメに振ったプロレスは茶番劇だと思われていたなかで、最初に思いきってその方向性に舵を切ったDDTは凄いし、それを決断した高木社長の時代の先を読むチカラは本当に凄いと思います。
ちなみに、最初の頃の観客の反応はどうだったんですか?
高木
最初はやっぱりファンの間でも抵抗感があったみたいで、事務所に「お前たちのようなふざけた団体がプロレスを名乗るのは許せない」といった電話がかかってきたりしましたよ(笑)。やはり、当時はプロレスを神聖視するファンも多かったですし、僕たちのようなレスラーはプロレスをやる技量もないと思われてバッシングを受けたりしました。
一方で、僕たちのプロレスを楽しんでくれるファンも確実に存在していましたね。
服部
どの段階で、「これはイケる」と思いましたか?
高木
1999年に後楽園ホールで開催した大会で、満員になったときですね。プロレスや格闘技の聖地とされる後楽園ホールで、自分たちのようなゼロから立ち上げた弱小団体が、観客を満員にできるようになるなんて、やはり感慨深いものがありました。
自分たちが選んだ道は決して間違っていないと確信できましたね。
服部
DDTがエンタメプロレスを標榜してスタートしたあとに、同じようにエンタメ系のプロレス団体が誕生し、なかにはハッスルのように大きな人気を集める団体も現れましたが、現在ではその多くが消滅しています。
そのなかで、DDTだけは今も成長を続けている。違いはどこにあるのでしょうか。
高木
とにかく「お金」の代わりに「頭を使う」ということですね。ハッスルなんかは資金力が豊富でしたが、大きなイベントになりすぎたせいで、かえって続けるのが難しくなった側面があると思います。
その点、僕たちには資金力がなかったので、その分アイデアで勝負するしかなかった。
だから、当時の人気レスラーをパロディにしたキャラクターを登場させたり、バックステージの乱闘映像を流したり...。今ではよくあるやり方ですが、そうした取り組みもDDTが一番早かったんじゃないかと思います。
他にも、当時WWEで24時間どこでも誰でも挑戦できるチャンピオンシップがあったんですが、そのアイデアをもらって「アイアンマンヘビーメタル級ベルト」というのを作って、レスラーだけでなくレフェリーや関係者がチャンピオンになったり、果ては人間以外のものがチャンピオンにもなりました。
服部
ありましたね。ダウンしたレスラーの上に脚立が倒れてきて、スリーカウントが入ると脚立がチャンピオンになったりとか(笑)。あれにはさすがに驚きました。
高木
そんなことをしているから、「ふざけている」と怒られるんですが(笑)。まあ、面白ければ何でもありで、とにかく新しいアイデアを常に考えて、エンタメの幅を広げていったんです。
服部
そうした努力の積み重ねによって今のDDTがあるんですね。