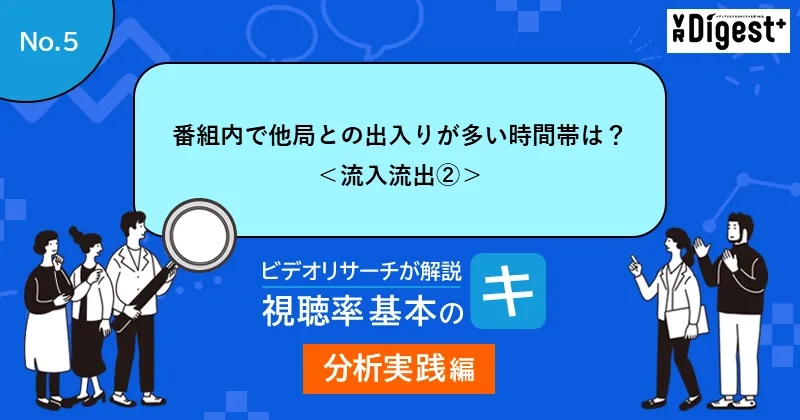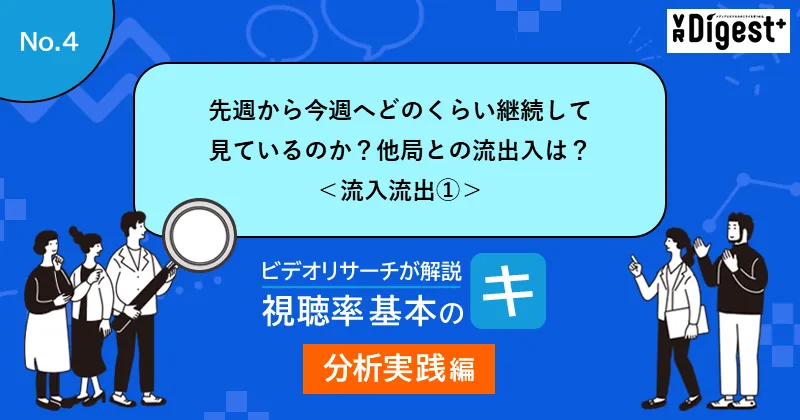てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「常田久仁子」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第17回
「テレビ界のおっかさん」
萩本欽一がそう呼ぶのは、フジテレビの女性プロデューサー・常田久仁子である。
医師の次女として熊本で生まれた常田は、19歳で東京都内の洋裁学校に入学した。卒業後も講師として残るように頼まれたが、女性だけの世界に窮屈さを感じ、文化放送に入社。常田は文化放送から、テレビ放送開始を翌年に控えたフジテレビの社会教養部に移り、「左遷」されてバラエティ担当になった。
当時、フジテレビは「報道」「歌番組」「ドラマ」の順で社内での地位が高く、「演芸」はずっと下の立場だったのだ。また、今では考えられないが、フジテレビ女性社員の"定年"が「25歳」と言われていた時代。世間でもセクハラ、パワハラが当たり前にまかり通ってしまっていた頃に、「女親分」然として、男ばかりのスタッフを仕切っていたという。
常田が萩本欽一擁するコント55号を"目撃"したのは日劇だった。彼らの代表作のひとつ「帽子屋」のコントを見て、その躍動感あふれる動きに「初めて見たときは欽ちゃんが二十歳ぐらいに見えるほど、若く感じた。この人たちならいける、と思った」(※1)と翌1968年から始まった『お昼のゴールデンショー』に抜擢した。
この『お昼のゴールデンショー』は月曜から金曜の正午からの公開生放送。その後の『笑ってる場合ですよ!』や『笑っていいとも!』に継承されていくことになる。また、『お昼のゴールデンショー』でのコント55号は評判を呼び、これを発展させる形で、「土8」枠に『コント55号の世界は笑う!』が制作されることになったのだ。
コント55号はもともとアナーキーな芸風だった。常識人の坂上二郎に対し、萩本が難癖をつけて暴力的に追い詰めていく。萩本欽一の暴力性や狂気が売りだった。
それを親しみやすいキャラクターに変えたのが常田久仁子だったのだ。
「あんたたち、もっときれいな服着なさい!」
常田は2人を叱りつけて言った。
「あんたたちがいた浅草の舞台では客席に男の人たちしかいなかったかもしれないけど、テレビは女の人が見てんの。女はね、いくらコントがおもしろくても、汚いかっこしてると見てくれないわよ」(※2)
それはそれまでの萩本には全くない発想だった。
常田の指導は普段の生活にも及んだ。
「おはようございますって、毎回そればっかり言ってないで、もっと気を遣いなさい。今日の服、素敵ですねとか、髪型が変わりましたねとか、なんかいい言葉を添えないと女の人には好かれないわよ」
女性との接し方に慣れていない萩本にとって、日々顔を合わせる常田との会話が、そのままバラエティ番組に出る際の振る舞いの訓練となったのだ。
一方で、「お笑い」のネタ自体については萩本を尊重した。
「わたしは笑いの専門家じゃないからなにがおもしろいかわかんない。だから欽ちゃんのやりたいようにやりなさい」と(※3)。
ネタに関しては萩本に任せ、男受けするものを演じさせながら、ネタ以外の部分では女性受けするキャラクターに"改造"していった常田。
その功績のひとつと言っても過言ではない、最大の"改造"がある。
それが、萩本欽一のしゃべり方だ。
萩本の口調は「~なのよお」などと女性的で柔らかい。その口調を作ったのが常田なのだ。
「ていねいな言葉をつかわないと、女の人に嫌われるわよ」(※3)
荒々しい言葉遣いをしていた萩本の口調が、常田のアドバイスで劇的に変化していったのだ。
その後、萩本は自身が抱える放送作家集団「パジャマ党」育成も兼ねてニッポン放送でラジオ番組を始める。
それが、72年4月から始まった『どちらさまも欽ちゃんです』だ。そしてその中の人気企画が単独の番組へと成長したのが、同年10月からの『欽ちゃんのドンといってみよう!』だった。
「ハガキ職人」という言葉を生み出したほどのこの企画に、萩本は手応えを掴んでいた。その台本の表紙だけをポケットに入れ常に持ち歩き、「ぜったいにこれをテレビにする」と意気込んでいた。
萩本が駆け込んだのは、やはりテレビで最初に彼を見出した常田久仁子のもとだった。
「投稿ハガキを読む番組をテレビでやりたいんです」
萩本の申し出に、常田は「いいよ! 特別番組の枠で放送してあげる」と快諾。こうして生まれたのが74年9月21日に放送された『欽ちゃんのドンといってみよう! ドバドバ60分!』だった。
だが、視聴率は一桁。それでも手応えのあった萩本は、レギュラー化に向けて動き出す。最初は日本テレビに話を持ち込んだ。その話を聞きつけた常田は当然激怒した。
「とんでもないやつだ! 私がフジでレギュラー番組にするから、よその局へもっていくんじゃない!」(※2)
その結果、『萩本欽一ショー・欽ちゃんのドンとやってみよう!』がスタートするのだ。ついに日本のテレビ史上初めて、コメディアンの個人名を冠した番組が始まったのだ。それも二重で入るというオマケつきだった。
アメリカの『エド・サリヴァン・ショー』という番組を知り、自分の名前を冠した番組を持つことが夢だった萩本欽一の思いを、常田は叶えたのだ。萩本が「観客のくすくす笑いも拾いたい」と言えば、2本だった客席のマイクが翌週には10本以上になったという。
「お笑いはわかんない」と彼女は言うが、だからこそ、彼女は徹底して視聴者目線を保つことができたのだ。
萩本欽一は彼女を評して次のように形容した。
「テレビを楽しくする『魔法の杖』のような人だった」(※4)
(参考文献)
※1 「産経新聞」朝刊(2004年2月17日)
※2 萩本欽一:著『なんでそーなるの!―萩本欽一自伝』(日本文芸社)
※3 小林信彦・萩本欽一:著『ふたりの笑タイム 名喜劇人たちの横顔・素顔・舞台裏』(集英社)
※4 「読売新聞」朝刊(2011年2月19日)
<了>