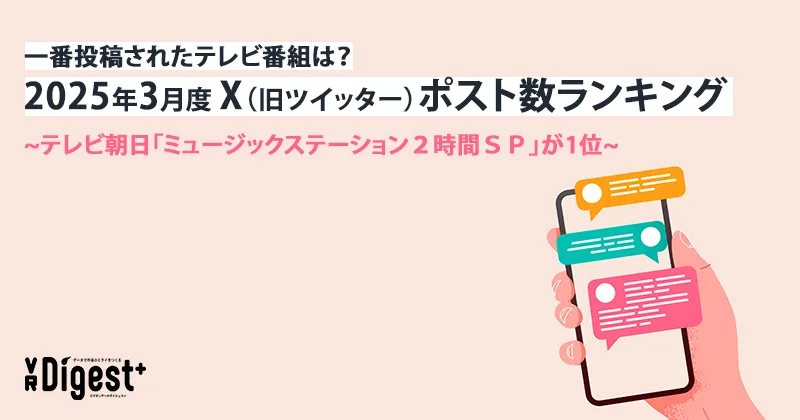てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「太田英昭」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第19回
「楽しくなければテレビじゃない」を標榜し、視聴率三冠王に君臨していた80年代のフジテレビ。
そんなフジテレビを「楽しい」だけじゃない方向から支えた人物がいる。その筆頭が、のちにフジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長まで登り詰めた太田英昭だ。
太田は80年代、『おはよう!ナイスデイ』に立ち上げスタッフとして参加。フジテレビの弱点のひとつであった平日朝の時間帯で視聴率アップに大きく貢献。この番組が始まった1982年からフジテレビの三冠王時代が始まったのだ。
間違いなく彼は、フジテレビの黄金時代を築いた人物の1人である。
1969年、全共闘の風が吹き荒れる中、ドラマや報道番組を作りたくてフジテレビに入社した太田だったが、入社後しばらくは『夕刊フジ』に出向したり、営業局に配属されたりしていた。
79年に太田の強い希望が叶う形で、『フジ制作』に出向。当時、フジテレビはコストダウンを図るため、制作部門を外部制作会社に切り離していたのだ。しかし80年、フジテレビ副社長に就任した鹿内春雄による改革でフジ系制作プロダクションが解体され、各制作会社の社員が一気にフジテレビに社員登用されると、その流れで太田も正式にフジテレビの制作部門の社員となった。
旅番組『わが旅わが心』、ワイドショー『小川宏ショー』を経て、立ち上げスタッフとして参加したのが『おはよう!ナイスデイ』だった。
この番組で太田の名声を一気に轟かせたのが「ロス疑惑」騒動だ。
まだ『週刊文春』がこの事件を「疑惑の銃弾」という記事で取り上げる前、太田は三浦和義を取材。撃たれた妻が亡くなった直後には三浦本人から太田に連絡があり、カメラを持って弔問に行き、三浦の悲しみの声を世に届けたほどの間柄だった。だが、今でいう"文春砲"に追随する形でワイドショーが事件を取り上げ始めると、三浦は態度を硬化。彼にとって都合の良いメディア以外とは連絡を断つようになった。太田も例外ではなく、三浦の行方はわからなくなっていた。
そんな時、ひとりのディレクターが三浦から親戚に宛てたはがきを入手した。その消印には「パディントン」の文字。ロンドン市内シティ・オブ・ウェストミンスター南西部の街だ。すぐに太田はパディントンに飛んだ。
だが、一口にパディントンと言っても決して狭い範囲ではない。どうやって探したらいいか途方にくれた太田は、現地コーディネーターに相談した。すると「日本のテレビ屋さんの悪いところは、カメラマンから音声から通訳まで、全部日本から連れてくること」と諭された。「外国取材は現地の人間を使うのが一番いい」(※1)と。
現地の人間は、地元のコネクションや人脈を持っているし、特にロンドンの人は、"スパイもの"が大好き。その助言どおり、太田が揃えた現地クルーはこの仕事に前のめりで協力してくれ、ついに三浦が潜伏するアパートを発見することに成功したのだ。すぐに番組メインキャスターの須田哲夫を呼び寄せ、三浦を直撃。この映像は大スクープとなった。
そうしてチーフディレクターとして活躍していた太田に、1986年、編成副部長だった重村 一が、新番組の話を持ちかけた。重村は太田の2歳年上で、『小川宏ショー』では先輩ディレクターという関係性があった。
「今の時代を描けるような番組を始めたい」(※2)
重村は「1時間の情報番組を作って欲しい」と太田に提案した。当時、TBSの『そこが知りたい』(『そこ知り』)など各局に1時間の情報番組がゴールデンで編成されていたが、フジテレビにはまだなかったからだ。
提示されたのは木曜夜9時のゴールデンタイム。TBSでは視聴率40%を超えるほどの人気を誇る『ザ・ベストテン』が放送されていた枠だ。フジテレビはこの枠をなんとか打開しようと様々な番組を作ったが返り討ちにあっていた。
そんな難しい状況での"独り立ち"だったのだ。しかも番組開始は約3ヶ月後に迫っていた。
司会は、当時売出し中だったアナウンサー・逸見政孝と三田寛子に決まった。番組タイトルは、太田がこだわった「好奇心」に、小泉今日子のヒット曲「なんてったってアイドル」のフレーズを組み合わせた『なんてったって好奇心』に決まった。
太田は初のプロデューサーに加え、実質的なチーフディレクターも兼ねる立場。彼が早急に着手したのがプロダクション探しだった。
局員スタッフがほぼ太田ひとりという状況で、プロダクションは番組を成立させるために不可欠であった。だが、情報番組のノウハウのないフジテレビにはそのコネクションもない。
太田は各局の情報番組のエンドロールを見て、めぼしい会社やディレクターの名前をメモり、片っ端から連絡していった。さらに"座付き作家"として、『そこ知り』にも参加していた日野原幼紀を招聘。その縁もあり参加したのが制作会社ハウフルスの菅原正豊だ。
『タモリ倶楽部』を筆頭にバラエティ番組を得意とする菅原だが、情報番組でも名企画を連発した。そのひとつが「日本の10人」である。
その道の達人10人を集め、1人ずつ紹介していくのだが、10分割された画面を一つひとつ埋めていき「残るは3人」などと煽っていく、現在では当たり前となった手法を"発明"した。これを俗に「10面マルチ」と呼び、現在も同社が制作する『出没!アド街ック天国』(テレビ東京)などに継承されている。
そして、この番組で強烈なインパクトを残したのが「ノンフィクション 10月改編の裏側」。
改編期の編成局に密着したのだ。社外秘どころか社員でもなかなか立ち入ることのできない、局の心臓部にカメラが向けられたのだ。
編成局のFAXに届いた新番組の視聴率を見る王東順。一桁という結果に「どういうお気持ちですか?」とマイクを突きつける。横澤彪が「企画書を持ってきてください」と編成部員に言われ、「何言ってんの。僕の顔が企画書だよ」と返す場面もあった(※1)。さらには村上光一編成部長(当時)に、副部長の重村が叱られているシーンもそのまま放送した(※2)。この映像は一時、フジテレビの社員研修にも使われることになったという。
その後、太田は『週刊フジテレビ批評』(92年~)や『ザ・ノンフィクション』(95年~)など、現在も続くフジテレビの長寿番組を立ち上げた。
太田は、「報道のど真ん中で仕事ができなかった」という「ルサンチマン」(強者に対して抱く嫉妬や妬みなど)が根底にあったと綴っている(※1)。おそらく「報道」に対してだけではないだろう。報道とともに志望したドラマも作ることは叶わなかった。また、フジテレビにおける花形であるバラエティ班に対してもルサンチマンの思いはあったはずだ。
それを吹き飛ばす"豪腕"で、ワイドショー・情報・ドキュメンタリー番組の分野で革新的な番組を生み出し続けていったのだ。
(参考文献)
※1 太田英昭:著『フジテレビ プロデューサー血風録 楽しいだけでもテレビじゃない』(幻冬舎)
※2 『フジテレビジョン開局50年史』(フジ・メディア・ホールディングス)
<了>