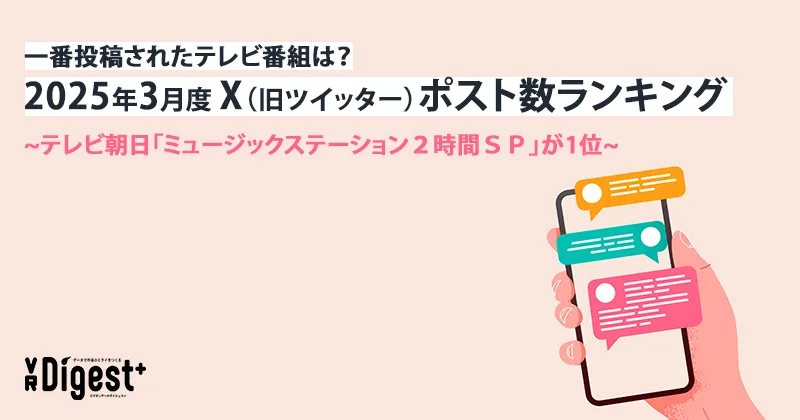てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「井上ひさし」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第20回
井上ひさしといえば、直木賞を筆頭に、日本SF大賞、読売文学賞、星雲賞、谷崎潤一郎賞など数多くの賞を受賞した小説家だ。あるいは、岸田國士戯曲賞を受賞し、劇団「こまつ座」を率いた劇作家としての顔を思い浮かべる人も少なくないだろう。
しかし、そんな井上ひさしの"原点"といえるのは、間違いなく「テレビ」。つまり、テレビ作家としての活動だ。代表作はなんといっても『ひょっこりひょうたん島』。その他、様々なテレビ番組の放送作家としてテレビに関わった。
井上は、国立結核療養所の事務員を経て、上京。浅草のストリップ劇場「フランス座」で進行係として働き始めた。当時のフランス座には、渥美清、谷幹一、長門勇らが在籍していた。
やがて井上は、コント台本を作る"バイト"を始める。採用されたら1本1000円だと言われたからだ。
花園町(現・新宿区界隈)で女と遊びたい、でないと「頭がすこし狂う」と思っていた井上にとって、渡りに船だった。
以前にストリップ用の芝居の台本を書いたことがあったため、コント台本を作ることも安易と考えていた。だが、ストリップ用の芝居の台本は、図書館にある過去の戯曲を種本にして、その物語を徹底的に分解・分析、そしてストリップ劇場に合う形に歪曲し、つなぎ合わせれば良かった(それを容易くやってしまえる井上の能力は驚異的であるが)のに対し、コントはそうはいかなかった。
まず図書館にコントの本はない。浅草の名作コントは関係者の記憶の中にしかないのだ。井上は苦労して30個の名作コントを関係者から教えてもらい、そのひとつひとつを分析していった。
その後、出版社の倉庫番に転身した井上は、またも「女と遊ぶ金欲しさ」に、ある"アルバイト"を始めた。当時、民放の放送局は、開局してまだ3~5年。人材が枯渇しており、テレビやラジオでしきりに脚本の懸賞募集をしていた。井上はそれに目をつけた。
この"懸賞生活"は、2年近く続いたという。
その2年間で応募した回数は実に145回。そのうち入選は18回。佳作が39回にのぼった。その結果、34万6,000円を稼ぎ出したのだ。月で割れば、1万4,000円あまり。倉庫番の給料が月5,000円だったというから彼にとって相当な額だっただろう。
ところで、"懸賞生活"を始めて半年くらいが経った頃、井上は強力な"ライバル"がいることに気がついた。その男は、片っ端から懸賞に応募する"同業者"と見え、やたらに入選率が高く、毎回のようにその名前を目にしたのだ。
その男こそ、当時大阪府立大学に通っていた藤本義一だったのだ(※1)。
このように数多くの懸賞で入選を果たした井上は、やがてテレビやラジオの世界から声がかかるようになり、放送作家として働き始める。
そうして、『ひょっこりひょうたん島』などの名作を生み出していくのだ。
「私の親しいディレクターに武井博さんという人がいて、よく一緒に銭湯に行ったのです。誰もいない昼間のお風呂場で二人きりですから、洗い桶を誰も入っていないお風呂の中に投げ入れたりして、遊んでいたんです。そのとき二人に、水の上に浮く『ひょっこりひょうたん島』のアイディアが浮かんだんです」
これが『スタジオパークからこんにちは』(NHK総合)で井上ひさしが明かした『ひょっこりひょうたん島』誕生の瞬間だ。
しかし、これは真っ赤なウソである。
井上ひさし流のサービス精神から作られたフィクションだという。
『ひょっこりひょうたん島』の演出を担当した武井博とは、確かに一緒に銭湯に行く仲だった。なぜなら、井上は武井の住むアパートの隣の部屋に住んでいたからだ。
そもそも武井と井上が出会ったのは1962年のことだった。NHK放送記念日特集の子供向け番組として武井が『テレビ憲法』というホームドラマを企画し、その脚本を井上が担当したのだ。この『テレビ憲法』こそ、井上ひさしの記念すべき初テレビドラマ脚本作品だという。それが縁でアパートの隣人同士になったのだ。
『チロリン村とくるみの木』という連続テレビ人形劇にディレクターのひとりとして参加していた武井博が、新たな連続テレビ人形劇の企画を提出するように命じられたのは1963年の夏のことだった。
武井には「子供番組に笑いを」という強い思いがあった。今でこそ、それはごく普通の考えだが、当時は決してそうではなかった。「真面目」こそ美徳だとされていたのだ。武井は「大人の真面目さの影にひそむ『おかしさ』、それを笑いのめしてみたい」と考えた。
そこで参考にしたのが北杜夫のエッセイ集『あくびノオト』だった。その中に登場する3人のホラ吹き「三ボラ」のエピソードに心奪われた武井は、「舞台となる島には『三ボラ』的な大人たちがいて、その一方にはしっかりと現実を直視して大人顔負けの発想をする子どもたちがいる。その両者が、対立しつつも力を合わせて、島の未来を築いていく」という物語の骨格を作り上げた。
その企画は見事通り、まだ27歳の駆け出しディレクターにすぎなかった武井博がそのまま『ひょっこりひょうたん島』の演出を任されることになったのだ。
しかし、まだひょうたん島は漂流していない。
北杜夫に原作執筆を依頼するも断られ、途方に暮れた武井は、かつて隣に住んでいた新進気鋭な若手作家を思い出した。もちろん井上ひさしのことである。この頃にはもうお互い別々なところに引っ越していた二人は、『ひょっこりひょうたん島』で再会を果たすのだった。
そして、ひとりでは大変だろうと考えて武井が声をかけたのが、児童文学出身の山元護久だった。その後約10年にわたり、名コンビとして作品を書いていくことになる井上と山元の運命的な出会いだった。
井上本人も「『テレビ』というコトバを聞いたり発したりするたびに、ぼくはなぜかこの山元さんの顔を思い泛べる」(※1)と綴っているように、山元とのコンビの歴史こそ、井上のテレビ作家としての歴史と言っても過言ではない。
だが、なかなか「これだ!」という脚本は作れなかった。『ひょっこりひょうたん島』の具体的な暮らしが浮かび上がってこなかったのだ。
「そうだ! あれだ! 島を動かして、流れ島にすればいいんだ!」
ある時武井が、ヒュー・ロフティングによる児童文学『ドリトル先生』で巨大な貝がらが舟のように湖の上を流れていくシーンを思い出し閃いた。
そこからは早かった。井上と山元は、その漂流する島に住む魅力的なキャラクターを次々と生み出していった。こうして『ひょっこりひょうたん島』は誕生したのだ(※2)。
この番組を象徴するテーマソングも"難産"だった。
タイムリミットまであと3日というギリギリの日を迎えても一向にアイディアが出ない。
とうとう締切りの日。NHKに向かう電車の中で、井上は口を開いた。
「今、僕の頭に、一つだけ、言葉が浮かんだんですが」
「どんな言葉ですか?」
身を乗り出して尋ねる武井に、井上はポツリと言った。
「まるい地球の水平線」
それだ!
瞬間的にイメージが連なっていく。そこからは早かった。まったくアイディアが浮かばなかった2日間が嘘のように、歌詞がとめどなく溢れてきた。
そんな中、井上は少し照れくさそうに言った。
「"泣くのはいやだ、笑っちゃおう"という言葉は、ちょっとナマ過ぎますかね?」
「いや、子どもの素直な叫びとして、いいじゃないですか」(※2)
こうして、あのテーマソングが完成したのだ。
井上にとって、「泣くのはいやだ、笑っちゃおう」は人生の叫びだったのではないか、と武井は振り返っている。
児童養護施設で育った井上の人生は、苦しみの連続だった。
「苦しみや悲しみ、恐怖や不安というのは、人間がそもそも生まれ持っているもの」(※3)だと井上は言う。つまり、「生きる」ということ自体に、苦しみや悲しみはあらかじめ詰まっている。けれど、そこに「笑い」は入っていない。放っておいても人は悲しみ、苦しみ、泣いてしまう。けれど、笑いは自然には生まれない。作り出して初めて生まれるものなのだ。
だから井上は、笑いとユーモアにこだわった。なぜなら「笑いとは、人間が作るしかないもの」(※3)だからだ。
「笑いは、人間の関係性の中で作っていくもので、僕はそこに重きを置きたいのです。人間の出来る最大の仕事は、人が行く悲しい運命を忘れさせるような、その瞬間だけでも抵抗出来るようないい笑いをみんなで作り合っていくことだと思います」(※3)
まさに「泣くのはいやだ、笑っちゃおう」の精神だ。
井上と山元の合作方法は前代未聞のスタイルだった。
「コンビを結成した昭和38年から10年間は、ほとんど毎日のようにわれわれは面を突き合わせていた。ふしぎなことに、10年間、一度も喧嘩したことがない。むろん、作品の主題を決めるときや筋をこしらえるときや、あるいはまた登場人物の性格づけをするときなどには、二人とも口から泡を吹いて議論を闘わせたが、たがいに陰口を叩きあったり、足を引っぱり合ったりしたことは絶えてなかった」(※1)
そして、「相棒に対しては『フェア』であった」という。
例えばディレクターから直しの指示が来ても、どちらか一方の責任にせずに「二人の共同責任ですから、二人で直します」とそれぞれが庇った。逆に褒められたときも二人の手柄にした。そのために筆跡を似せて書き、筆記用具まで同じにして、ディレクターにどちらが書いたのか区別をつかなくなるようにしたというのだから、その徹底っぷりに驚かされる。
さらに驚くのが、その合作の手順だ。
武井が二人に依頼した時に想定していたのは、数話ごとにそれぞれが担当回を交代しながら執筆するというものだった。おそらく、多くの場合そのような手法がとられるはずだ。だが、二人は違っていたと武井は証言している。
「お二人が、喫茶店でストーリーを話し合い、一回分の話の構成を練り上げると、奇数シーンと偶数シーンを手分けして書くのです。例えば奇数シーンは井上さん、偶数シーンは山元さん、という具合に。そして最後はそれらをつなぎ合わせて一回分の台本にする」(※2)
まさに一心同体。信じがたい手法だ。けれど、そんなやり方で5年間、1,224回すべてを書ききったのだ。いや、それどころか『ひょっこりひょうたん島』以後も含めると、このコンビは同じスタイルで10年間書き続けたのだ。
奇跡の二人。
そうとしか言いようがないだろう。「泣くのはいやだ、笑っちゃおう」という世界を「人間の関係性の中で」作っていった。
だが、山元護久は1978年、43歳の若さで急逝。井上はその頃、既に舞台や小説の世界に活動の場を移していたが、彼がテレビの世界に戻ることがなかったのは、もしかしたら、かけがえのない相棒を失ったからではないだろうか。
『ひょっこりひょうたん島』最終回でドン・ガバチョはこんな台詞を言っている。
「人間らしい人間とは、ともに戦う友だちを見つけ、ともに戦う友だちを持っている人のことなのではないでしょうかな?」
(参考文献)
※1 井上ひさし:著『ブラウン監獄の四季』(河出文庫)
※2 武井博:著『泣くのはいやだ、笑っちゃおう 「ひょうたん島」航海記』(アルテスパブリッシング)
※3 井上ひさし:著『ふかいことをおもしろく―創作の原点』(PHP研究所)
<了>