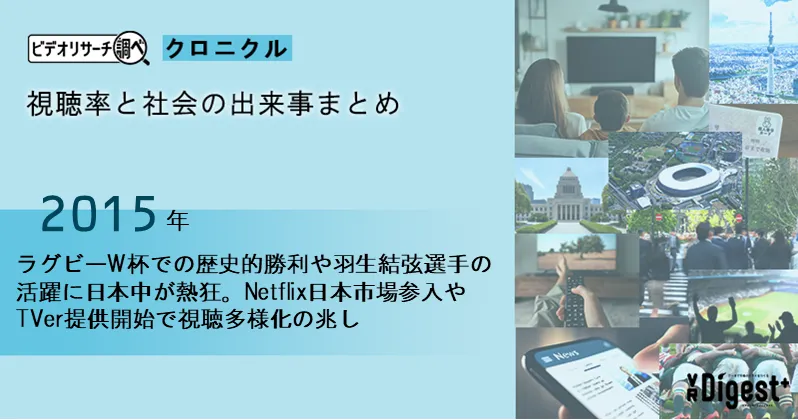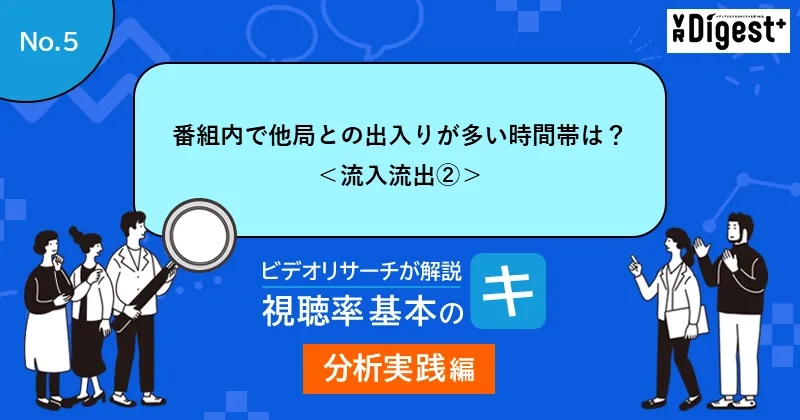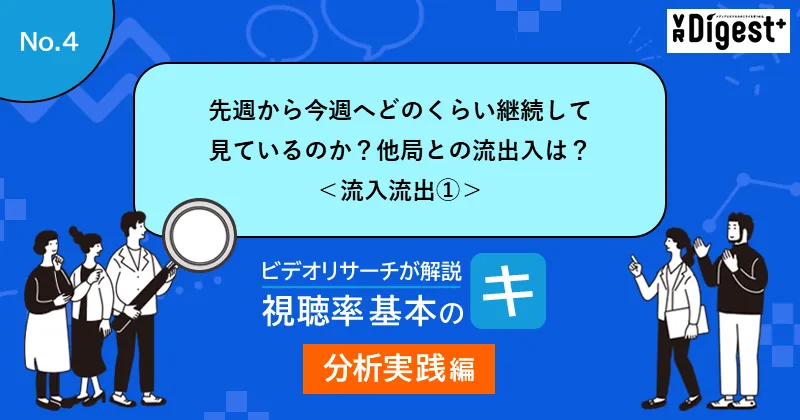てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「山田良明」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第21回
『北の国から』(フジテレビ)のような本格派の大作ドラマを手掛けた一方、フジテレビのいわゆる「トレンディドラマ」路線を生み出したのが山田良明だ。
1969年にフジテレビに入社した山田は、何の専門技術もないのになぜか技術局に配属された。わけもわからないままマイクロ回線を扱っていた。4ヶ月ほど経ったある日、廊下に副社長による檄文が貼り出された。
「我と思わん者は、名乗りを上げよ」
当時、フジテレビは視聴率的にはどん底。"振り向けばテレ東"などと揶揄されていた。それを打破するために編成局企画センターをつくるから、やる気のある者は手を挙げろ、と言うのだ。
山田はすぐに一面識もなかった副社長のもとに走った。
「私はドラマを作るためにフジテレビに入ったんです。それが技術をやっていたら会社の損になりますよ」
血気盛んな若者らしく言い放った。それが功を奏して、その後すぐに企画センターへ異動となった。だが、組織ができたばかりでうまく機能していなかった。結局、山田はそれからしばらく歌謡ショーや『東京ホームジョッキー』などの生活情報番組などを手がけていた。
もう20代最後の年。このままではいけない。そう思った山田は再びドラマ班へ行きたいと主張し、ようやくドラマ班に異動になった。そして、程なくして連続ドラマ版の『北の国から』に参加した。この時も、面識のないプロデューサーの中村敏夫に「倉本聰さんが好きなんです」と直訴して参加を実現させたのだった。
1987年にはフジテレビの月曜夜9時にドラマ枠が復活した。のちに「月9(ゲツク)」と呼ばれるようになる枠だ。
もともとこの枠は時代劇や『大空港』、『87分署シリーズ・裸の街』といった松竹制作の刑事ドラマを放送していたが、80年以降は萩本欽一の番組を放送する枠になっていた。
当時のフジテレビは「漫才ブーム」を生み出し、バラエティが絶大な強さを誇っていた。ドラマもバラエティ同様、若い視聴者層を取り込まなければならない状況で、編成の責任者であった重村一は、若者向けドラマ枠を作る決断を下した。それが「月9」枠の始まりだった。
だが、そこで当初作られたのは『アナウンサーぷっつん物語』『ラジオびんびん物語』『ギョーカイ君が行く!』などいわゆる「業界モノ」ドラマだった。
そんな中で山田が1988年に企画・プロデュースしたのが『君の瞳をタイホする!』だった。これこそがトレンディドラマ路線の第一作だといわれている。
そのタイトルが示す通り、刑事が主人公のドラマだ。しかし、それまでの警察モノドラマと大きく違うのは、いわゆる事件を解決する刑事ドラマではないということだ。警察を舞台にした「太陽にほえない」青春ラブコメディだった。
世代交代を目指したメインキャストにはほとんど無名だった陣内孝則、柳葉敏郎、浅野ゆう子らを起用した。山田とともにプロデュースを担当した大多亮は、「トレンディドラマ」を成す要素として「ロケ地・衣装・音楽」を挙げている(※2)。
通常、ロケ地は物語上の必要性から決められていく。つまりは、物語が先でロケ地が決まる。だが、トレンディドラマの考え方は違った。「話題になっている場所」や「若者が集ってくる場所」をリサーチしロケ地を決め、その上で物語が作られていったのだ。
リアリティよりも若者の憧れを投影した。衣装面でいえば、今では当たり前になっているがドラマにスタイリストを導入したのも本作が先駆だった。女性雑誌のグラビアを見るようなドラマを目指した。さらに音楽も最大限活用し、音楽から触発されたり、歌詞からインスパイアされたストーリーで相乗効果を生んだ。
そんなお洒落で楽しいラブコメディの初回視聴率は17.3%。当時としては及第点くらいの数字だったが、ドラマは徐々に評判を呼んで最終回は21.4%の高視聴率を獲得した。だが、数字以上にのちに「トレンディドラマ」と呼ばれるフジテレビドラマの潮流を生み出した功績は大きかった。
そして同年、浅野温子、浅野ゆう子のいわゆる「W浅野」を主演に据えて木曜劇場で放送した『抱きしめたい!』で「トレンディドラマ路線」を確立させたのだ。
山田は求められているドラマ像が変わってきていると感じていた。ならば、新しいドラマの書き手が必要不可欠だ。そうして立ち上げたのが公募制の「フジテレビ・ヤングシナリオ大賞」だった。応募資格は「自称35歳以下」のみ。審査員は本職の脚本家ではなく、現役のプロデューサーやディレクターが務めた。
「審査基準は『自分が誰とやりたいか』。だからグランプリじゃなくていいんです。最終選考に10作品ぐらい残っていて、そこまで絞り込まれてくるとそれぞれに個性がある。グランプリにはならない、佳作にはならないかもしれないけれども、『いや、私はこの人とやりたい』という人とキャッチボールをしながら育てていく」(※1)
第1回の大賞にはのちに『東京ラブストーリー』を書く坂元裕二、2回目の大賞には『101回目のプロポーズ』などの野島伸司が輝いた。
先に連ドラ脚本家デビューしたのは野島伸司だった。88年に放送された『君が嘘をついた』である。当初は別の脚本家が書く予定だったが「勉強のため」と1話だけ書くように言われたのだが、できあがった脚本が優れていたため、まだ実績皆無の新人が大抜擢されたのだ。
翌年には『同・級・生』で坂元裕二もデビューする。彼もまた"代役"だった。
「最初、『同・級・生』は大石静さんにお願いしていたんです。『同・級・生』は原作がありますから、こういうふうな構成でいきましょうということで、脚本が上がってきたんです。でも、坂元にも、一話はここの部分をやるんだけどちょっと書いてみないかと言って書いてきたら、台詞が違うんですよ。光ってる。
原作があるから話の内容は同じなんだけど、台詞が瑞々しくてバカにいい。だから、こっちでいきたいって言ったら、当然、大石さんが怒って。『ちょっと見せてよ』っていうから坂元の脚本を見せたら、『わかったわよ』って。そこから坂元が全話書きましたからね。ギリギリまで書けなくて、飛び降りて死のうと思ったことが何回かあったって後から聞きましたけど、ちゃんと書いてきた」(※1)
実力さえあれば、実績度返しで無名の新人にもチャンスを与える。
もしかしたら、一面識もない相手に直訴しチャンスを掴んだ若き日の自分を想起していたのかもしれない。そうやって若き才能にベットする。その柔軟性と冒険心が新たなトレンドを生んでいったのだ。
(参考文献)
※1 戸部田誠:著『全部やれ。』(文藝春秋)
※2 中川右介:著『月9』(幻冬舎新書)
<了>