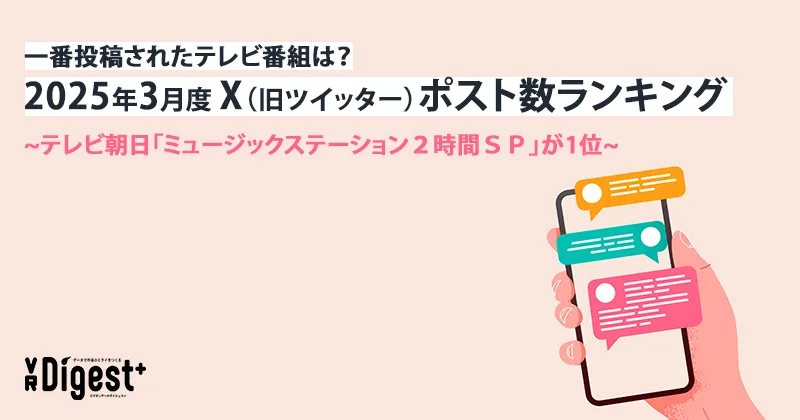てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「岡田太郎」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第26回
フジテレビのディレクターとして活躍後、共同テレビの社長・会長・相談役を歴任した岡田太郎といえば、本人は不本意だろうが、「吉永小百合の夫」という代名詞が真っ先につきまとう。
「正直、最初は気分良くなかったがもう慣れましたよ。事実だからしようがない」(※1)と岡田自身は語っている。
2人の出会いは、吉永小百合の代表作の一つとなる映画『愛と死をみつめて』公開直後に制作されたドキュメンタリー。この番組のプロデューサーを急遽任されたのが岡田太郎だった。
彼女のヨーロッパでの旅に約1ヶ月同行したが「全然偉ぶらない。こんなに素直な子がいるのか」と驚いた。吉永小百合は当時19歳。それから9年後、2人は結婚。当時人気絶頂の女優の結婚、しかも15歳差の年の差婚は世間に大きな衝撃を与えた。
その少し前、吉永は働き詰めで積もりに積もったストレスがたたり、女優の命の一つである「声」がうまく出なくなってしまっていた。その時支えになったのが、「休めないのなら、今できることを一生懸命にやれば、それは見てくれる人がきっと分かってくれるよ」という岡田の言葉だった。吉永はこの結婚について以下のように語っている。
「結婚には、いろんな形があると思うんですね。一緒になって束縛されるものもあれば、私みたいに精神的な自由を得るためにする人も。もし結婚していなければ、この仕事をやめていたと思う。完全に行き詰まってしまって。私は結婚して、本当の新しい第一歩を始めることができた。本当に幸運だったと思っているんです」(※2)
そんな岡田太郎は「吉永小百合の夫」というだけでなく、もちろんテレビ史においても重要な功績を残したディレクターだ。
昼ドラといえば、「メロドラマ」というイメージがある。役者のアップをうまく取り入れることによる独特な演出方法で「アップの太郎」などと呼ばれた彼は、その嚆矢ともいえるドラマをつくり、「昼メロ」などという言葉を生み出したのだ。
元々文化放送に入社した岡田は、開局準備を進めるフジテレビに"移籍"した。フジテレビは当初、文化放送とニッポン放送を主体とし、東宝、松竹、大映の映画会社各社が参加し設立されたためだ。
すると岡田は開局とほぼ同時にスタートする目玉ドラマ『陽のあたる坂道』の演出を担当することになった。フジテレビの開局が1959年3月1日。そのわずか8日後の3月9日から8月31日まで全26回の連続ドラマだった。もちろん、岡田にとってドラマ演出のデビュー作だ。「この処女作から独特の映像表現に工夫を重ねていた」と放送ジャーナリスト・志賀信夫氏は評している(※3)。
例えば、犬小屋で2人が見つめ合うシーン。狭いところで近接しているため、金網越しに撮ると網目のところでぼやけてしまう。当時のテレビでは映画のようにワンカット、ワンカットを分けて編集することができず、生放送に近い撮影方法をとるしかなかった。そのため、複数のカメラで撮影し、それをスイッチングするという手法がとられていた。そこで岡田はそれぞれのアップを映し、お互いが見つめ合っているように撮影、演出した。アップとスイッチングを多用することで独特の臨場感を生み出したのだ。
そして翌1960年、岡田が演出したのが『日日の背信』だった。丹羽文雄が毎日新聞で連載していた小説が原作。タイトルから連想されるように不倫をテーマにした物語だ。これが放送されたのが午後1時。それまでこの時間帯は教養番組や料理番組が並んでいた。
60年代、政治の季節らしく、フジは硬派な討論番組などを放送していた。しかし、6月に新安保条約が自然承認され、デモは一気に終息していった。そんな時に始まったのが『日日の背信』だった。7月4日から9月26日まで全13回の放送だ。
岡田がこの作品の演出をするきっかけとなったのは食堂での雑談だった。
編成主任から「なにかバカ当たりする企画はないものかね」と聞かれた岡田は、会食中の気軽さからか、思いつきでこう言った。
「真っ昼間に"よろめきドラマ"はどう?」
岡田が文化放送に在籍していた頃、朝9時台に、夫や子供を送り出した主婦向けに艶っぽい文芸作品をドラマ化していた。それを仲間内で「よろめきアワー」と呼んでいた。それが好評を得ていたことが頭の片隅にあったのだ。現在では「よろめき」を「妻が夫以外の男性にときめきを感じたり、誘惑されて浮気をしたりすること」の意味合いで使用することは馴染みが薄いが、当時は三島由紀夫の小説『美徳のよろめき』などから流行していた。
「あれ、やることになった」
程なくして、その編成主任からそう言われ、言い出しっぺの岡田が演出をやらざるを得なくなった。
その題材となったのが「よろめき」の典型である『日日の背信』だったのだ。
この演出には『陽の当たる坂道』での経験が役に立った。アップを多用した演出は、情感を生み、受け手の感情移入を促した。加えて、ドラマは昼の放送だが、夜にビデオ録画撮りをしたり、あえて2人きりの芝居で30分間撮ったりもした。抱き合って、また抱き合って、抱き合っての繰り返し。そのため視覚的に変化が出るように工夫した。
「自分で実際にやってみせて、"絵"になる演技をしたのです。だから、曲芸とかアクロバットのように俳優の体を動かして、美しい映像を作るためにあらゆるテクニックを凝らしました。手や足の動きがバラバラになってしまうとか、体の位置と手の置き方が不自然だとか、俳優たちからも苦情が出たりしました」(※3)
岡田は物理的なリアリティよりも、いかに小さなテレビ画面の中で美しく映るか、その感情を表現できるかを考えた。つまり感情のリアルをどうテレビ画面に映すかにこだわったのだ。その結果、この作品は高評価を獲得し、「亭主が会社に出勤している留守の間に、専業主婦の多くが濃厚な愛欲シーンを楽しんでいる」(※3)などとますます話題になり、各局がお昼の時間帯にメロドラマを揃えることになっていった。
そうして人間の欲情を抽出する「昼メロ」路線が生み出されていったのだ。
(参考文献)
※1 「読売新聞」1996年3月18日
※2 「スポーツ報知」2018年2月4日
※3 志賀信夫:著『映像の先駆者125人の肖像』(NHK出版)
<了>