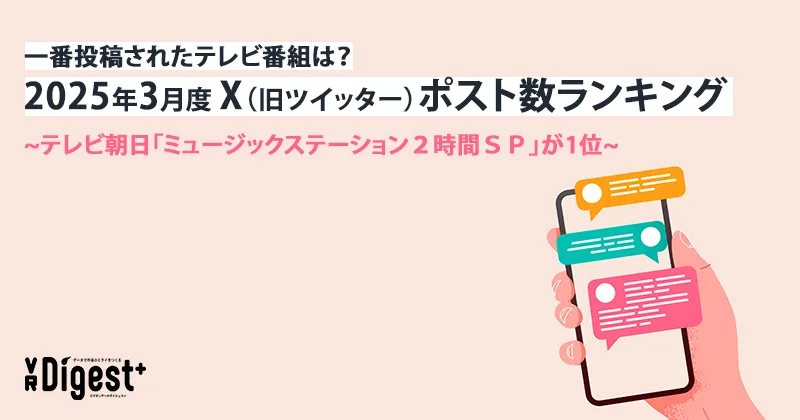てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「佐々木昭一郎」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第27回
何年かに一度、その作品が再放送されるたびに、若い世代を中心にファンを急増させる映像作家がいる。
それが『夢の島少女』『四季〜ユートピアノ〜』などで知られる佐々木昭一郎だ。
彼は、日本のテレビマン史上もっとも多くの賞を受賞したディレクターのひとりではないだろうか。
たとえば、1970年8月放送の初のテレビドラマ演出作品『マザー』は、モンテカルロ・テレビ祭最優秀作品賞を受賞。1971年11月放送の『さすらい』では文化庁芸術祭テレビドラマ部門大賞に。この2つの作品で芸術選奨新人賞受賞やギャラクシー賞期間選奨受賞対象作品に選出されるなどの功績を残す。
続く『夢の島少女』は芸術祭では黙殺されたが、カメラマンの葛城哲郎がギャラクシー個人賞に。さらに、つげ義春原作の『紅い花』で2度目の芸術祭テレビドラマ部門大賞に加えて国際エミー賞優秀作品賞を受賞。
『四季〜ユートピアノ〜』ではイタリア賞グランプリ、放送文化基金賞、ギャラクシー賞などに、『川の流れはバイオリンの音』で4度目の芸術祭テレビドラマ部門大賞、『アンダルシアの虹』でプラハ国際テレビ祭最優秀監督賞、そして『春・音の光』では、芸術選奨文部大臣賞、毎日芸術賞などの個人賞を総なめにしているのだ。
それだけではない。テレビ作品の前に活躍していたラジオドラマでも数多くの賞を受賞しており、イタリア賞グランプリはラジオとテレビ両方で受賞しているのだ。こんな監督、世界広しといえどもなかなかいない。塚本晋也、河瀨直美、是枝裕和など、彼は現代日本映画を率いる多くの映画作家たちに影響を与えた。
佐々木の作品はドラマともドキュメンタリーともいえないような、独特の詩情あふれる映像が特徴だ。
「私の作品はすべて、私が見た夢がもとです。『夢の島少女』の場合、赤いワンピースの少女が夢の島15号地から荷物をかかえやって来る夢で、ワンピースは雨に濡れ肌に吸いついている。私は白昼夢が好き」(※1)
その『夢の島少女』で主人公を演じたのが中尾幸世だ。彼女は以降、『四季〜ユートピアノ〜』、『川』三部作(『川の流れはバイオリンの音』、『アンダルシアの虹』、『春・音の光』)など佐々木作品に欠かせない演者となる。
「主人公選びには、とことんねばった。諦めていたころ、中尾幸世さんが現れた。17歳の美大受験生だ。『彼女の目は放射能を放っている!』と、名手・葛城が感動して言った。テスト撮影などせず、一気に撮影した」(※1)
佐々木がこう回想するように、当時、中尾は演技の素人だった。
企画が通って3ヶ月以上、ピンとくる演者が見つからず頓挫しかけた中で突然現れた逸材だった。上北沢の喫茶店で初めて会って、まずその声の良さに惹かれた。オカッパ頭もどこか鬱屈とした雰囲気も、イメージにピッタリだった。何より、自分の「意志」を感じたという。
佐々木作品には、中尾に限らず俳優ではない"演技の素人"が数多く起用されている。
それは、ラジオドラマ時代の苦い経験からきている。
NHKに入社してすぐの頃、佐々木はラジオドラマのディレクターを任された。
だが、1作目、2作目は大失敗だった。当時の売れっ子作家に台本を頼み、当時話題の若手俳優をキャスティングするという「普通」のことをやってしまったからだ。「0点に近かったよ。学芸会だった」(※2)と振り返っている。
佐々木には、「役者が生き生きした言葉を使っていない」ように感じた。
それはなぜかといえば、「誰かが書いたセリフを読まされているから」だった。事実、まったく話題にもならず、賞にも引っかからなかった。
その反省を踏まえて作ったのが1963年のラジオドラマ『都会の二つの顔』だ。
この作品で佐々木が主人公に抜擢したのは、高校時代の親友だった。彼は魚屋。「らっしゃい!」など魚屋のやりとりが音として魅力があると感じていたからだ。相手役は宮本信子。いまや大女優だが、当時はまだ文学座の研究生にもなっていない見習いのような状態でほぼ素人だった。
書いたセリフを単に読ませるだけでは、また「学芸会」のようになってしまう。だから、佐々木は収録の直前に手のひらに書いたセリフをパッと見せて即興に近い形で、街でデンスケ(携帯用録音機)を使って録音していくというスタイルを用いた。これが、ラジオテレビ記者会年間最優秀作品賞、芸術祭奨励賞を受賞し、佐々木の作風を決定づけたのだ。
その後、佐々木は親友となる寺山修司と組み『二十歳』やイタリア賞受賞の『コメット・イケヤ』などを作った後、30歳でテレビディレクターに転身した。
佐々木は演者に対し、その多くが素人にもかかわらず演技指導はしないのだという。
それは「いじわるで教えないんじゃなくて、自分の頭で考えてほしい」(※2)からだ。たとえ演技ができても、あたかも本当にその世界の中で呼吸しているように生き生きとしてもらえなければ意味がない。演技の上手い下手よりも自分の頭で考えられる人のほうが重要だと。だからこそ、中尾がそうだったように演者選びには徹底的にこだわるのだ。
そして、佐々木は見る側にも「考える」ことを要求する。佐々木の作品に抽象性が必ずあるのはそのためだ。
「観ながら考えるからですよ、観客が。自分の頭で。で、観客に考えてもらわなきゃ、深まらない。作品ってのはさ、何だろう、何もかも与えちゃったら、つまらないんだ」(※2)
だからこそ、視聴者の心にいつまでも残る。
そうして佐々木昭一郎は「映像詩」としかいいようがない、唯一無二の作品群を作り上げていったのだ。
(参考文献)
※1 志賀信夫:著『映像の先駆者 125人の肖像』(NHK出版)
※2 ほぼ日刊イトイ新聞「伝説の映像作家・佐々木昭一郎さんに訊く 物語とは何か。」(2014年11月6日~11日)
<了>