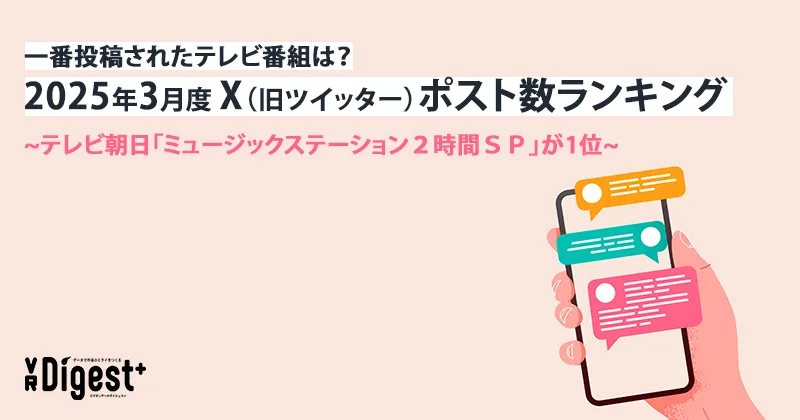てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「横澤彪」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第32回
今考えると想像がつかないが、70年代、フジテレビのキャッチフレーズは「母と子のフジテレビ」だった。朝は子供向け番組、お昼は主婦向け番組。そして、当時フジテレビの"顔"ともいえる看板番組は『スター千一夜』や『ザ・ヒットパレード』をはじめとする歌謡番組だった。
それが80年代の初頭、「楽しくなければテレビじゃない」という名キャッチフレーズを打ち出すことになる。そのきっかけを作った人物の1人が、言わずと知れた名プロデューサー・横澤彪だ。
横澤彪は、東京大学卒業後、1962年にフジテレビに入社した。テレビ局に入るつもりはなかったが、どこよりも入社試験が早かったため「腕試し」に受けた。100倍以上の高倍率ながら見事合格したため、もったいないと思い入社。配属されたのは制作部だった。
初めて担当した番組は演芸番組『お茶の間寄席』(フジテレビ)。ここで早くも横澤はプロデューサー的センスを開花させる。東京ぼん太に唐草模様の風呂敷を首に結ばせ、栃木訛り丸出しで喋らせたのは横澤の提案だったという。この「東京の田舎っぺ」キャラは一躍人気者になった。さらに、コント55号を初めてテレビのレギュラーに起用したのも横澤だったという。
テレビマンとして順風満帆に見えた。
だが、思わぬ形で足をすくわれることになる。1966年にフジテレビに労働組合が結成されると、横澤もそれに参加。「組合ニュース」の編集を担当する。
2代目副委員長だった妹尾河童はその頃の横澤について「横澤くんが編集する組合ニュースには、組合用語なんか一語もない。読んだらおもしろくてね、評判でしたよ。こちらの言おうとすることを、他者に伝えるための発想力のすばらしさ。これは彼、このころから抜群でした」(※1)と述懐している。
しかし、この活動が上層部から目をつけられてしまう。
折しもフジテレビは「経営の合理化」を名目に制作部門を分社化。フジポニー、ワイドプロモーション、フジプロダクションなどの子会社に番組制作を委託し始めた。
制作部門がなくなった横澤は、関連会社である産経新聞出版局に飛ばされてしまったのだ。しかも配属されたのは営業部だった。
そこで出会ったのが「戦後最大の出版プロデューサー」と呼ばれる神吉晴夫だ。
「一流の制作者になるためには、自分が少年のように感動して、他人にこれを伝えたいと切望し、自分に賭けるピュアな心が絶対に必要だ。しかし、それだけでは成功しない。もうひとつ、商売人のたくましさが必要なんだ。きみは、ぼくのところにいるうちに、たくましい商売人根性を身につけなさい」(※1)
失意で会社を辞めようか迷っていた横澤はその言葉に奮起した。
制作部門を子会社に委託したことや、組合運動を理由に実力ある者が左遷されてしまったことで、フジの制作現場のモチベーションは下がり、視聴率も低迷していた。
そうした状況の中、1980年に35歳の若さで鹿内春雄が副社長に就任した。彼は真っ先に子会社化していた制作会社を吸収。横澤もその流れでフジテレビの制作部門への復帰を果たした。
横澤は『ママとあそぼう!ピンポンパン』や『スター千一夜』のプロデューサー経験を経て、演芸番組に舞い戻った。12年ものブランクがあったにもかかわらず、その演芸番組の光景があまりにも変わっていないことに愕然とした。
横澤は、なんとか演芸番組を変えたいと強く決心した。
そんな時、単発の特別番組枠『火曜ワイドスペシャル』で予定されていた企画が中止になった。年度初めの特番で、各局強力な番組がラインナップされていたため、音楽班やドラマ班が尻込みする中、演芸班にお鉢が回ってくることになった。
『激突!漫才新幹線』の収録を会場で見ていた横澤は、漫才が若者の間で盛り上がっているのを肌で感じていた。このタイミングしかない。横澤は以前から温めてきた「漫才の東西対決」というコンセプトで番組の企画を提出し、それが採用されたのだ。
横澤がこだわったのは、若い新しい感性を取り入れることだった。
佐藤義和、永峰明など若いディレクターを配し、出演者もこれまでの序列を排し、ツービートや島田紳助・松本竜介、B&Bなどまだまだ無名に近い若手を起用した。
タイトルも「漫才」という古いイメージを変えるため『THE MANZAI』とアルファベット表記にした。それは横澤たちの狙い通り、若者たちを中心に熱狂的に支持された。
これによって興ったのが「漫才ブーム」だった。
横澤はすぐに次の一手を投じる。
平日お昼の生放送という帯番組に、『THE MANZAI』で活躍した漫才師を中心とした番組を立ち上げたのだ。それがスタジオアルタでの公開放送という形をとった『笑ってる場合ですよ!』だ。
もちろん、この番組のプロデューサーも横澤だ。
「なんだ、このタイトルは意味不明だ。我が社は業績最低で笑ってる場合じゃない!」
フジテレビは『THE MANZAI』が成功したとはいえ、全体で言えばいまだ視聴率は低迷していた。「これではスポンサーに説明できない」と反対された。だが、横澤は押し通した。
「ぼくが企画書です!」
そう叫ぶ横澤の熱意に幹部たちが折れ、企画が通ったのだった。
この番組が開始した翌年、「楽しくなければテレビじゃない」というキャッチフレーズが誕生した。
さらにほぼ同じスタッフ、主要出演者たちで『オレたちひょうきん族』が生まれ、"フジテレビ=若者のお笑い"というイメージが定着していくのだ。
反骨精神と商売人のたくましさで若い感性を巧みに取り入れ、フジテレビの"文化"そのものを変革させたのだ。
(参考文献)
※1 『女性自身』1983年9月15日号(光文社)
<了>