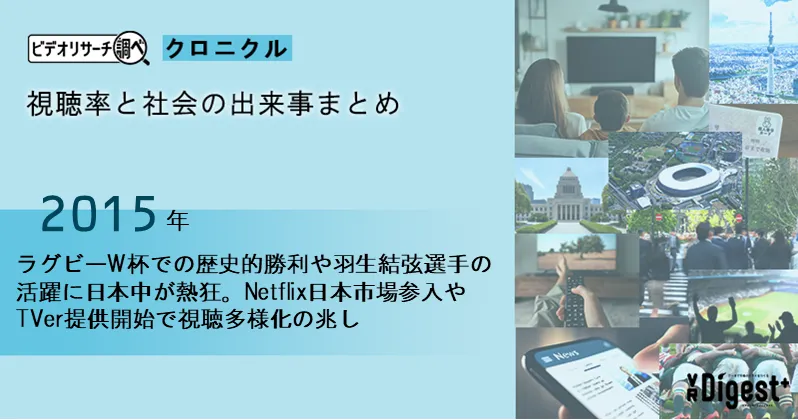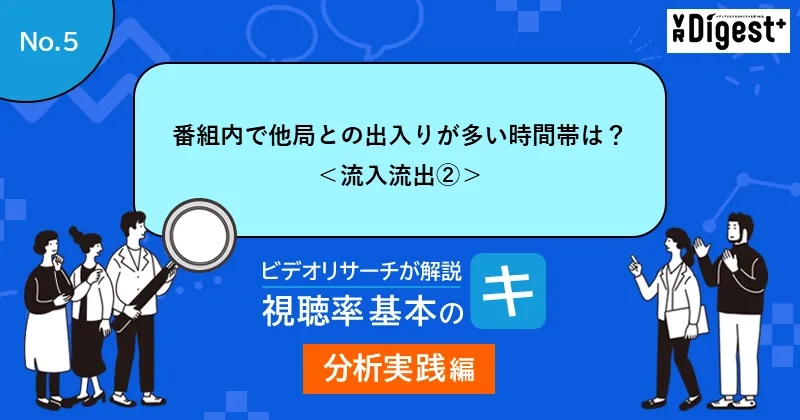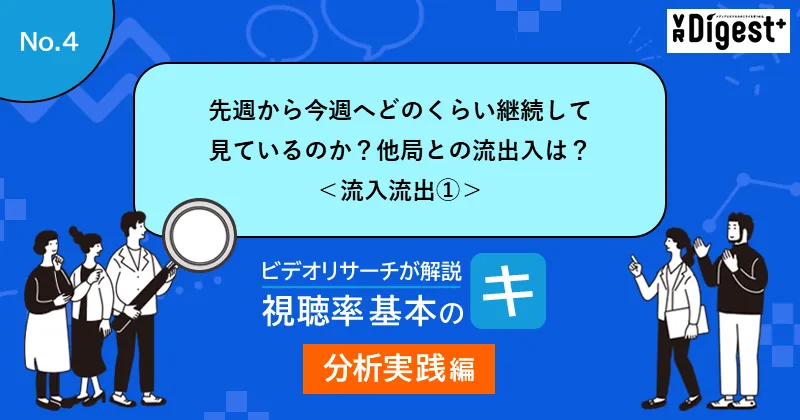てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「加藤就一」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第36回
今から45年前、その後「伝説」となる番組が産声をあげた。
『史上最大!アメリカ横断ウルトラクイズ』(以下、『ウルトラ』)(日本テレビ)である。
それはあまりにも衝撃的なものであった。
挑戦者たちがアメリカをはじめとする世界各国を、クイズを勝ち抜きながら旅するのだ。
ゴールはニューヨーク。出題者の福留功男が「ニューヨークへ行きたいか?」とアジテートするたびに挑戦者たちのボルテージは上がっていく。クイズが強いだけでは生き残れない。「知力・体力・時の運」すべてを必要とし、時に理不尽な仕掛けで熱狂を生んだ。
加藤就一もまた、この番組に釘付けになったひとりだ。
そして、この番組を作りたいという思いから日本テレビに入社した。
早稲田大学の政治経済学部時代、英語が得意だったこともあり「世界中、なるべくたくさんの国を見て死のう」ということを生涯の目標に定めた。だから就職活動も三井物産、三菱商事、伊藤忠商事、日本航空、全日空など、職種よりも海外に行ける可能性を重視して試験を受けた。その中に日本テレビもあった。他のテレビ局は受けていない。
つまりは、『ウルトラ』があるから。理由はその一点だけだったのだ。
1980年に日本テレビに入社すると、配属されたのは『木曜スペシャル』(以下、『木スぺ』)だった。言うまでもなく『ウルトラ』が放送されている枠。願いが叶ったと思った。
しかし、『ウルトラ』の季節が近づいてきても一向に声はかからなかった。
「『ウルトラ』に行きたい」と『木スペ』を統括するプロデューサーの石川一彦にお伺いを立てると「100年早い!」と一喝されたうえにこんな指令が下った。
「お前は南の島から持ち帰った日本海軍の爆撃機の復元をやれ」(※1)
グアム島の南にあるヤップ島で発見された艦上爆撃機「彗星」を日本に持ち帰り復元するというのだ。果たしてそんなことが可能なのだろうか。そもそもどうやって機体を持ち帰るのだろうか。
そうこう考えているうちに、『木スペ』班は機体を両翼、尾翼、胴体、エンジン部......と大胆に切り刻んで持って帰ってきてしまったのだ。
「大学出たての私の常識は、初っ端でバッコ~んとぶっ飛ばされた」(※1)と加藤は回想している。
そこからは朽ち果てた機体を直すという、ひたすら地味で地道な復元作業が続く。そして数ヶ月後、見事に復元された「彗星」は、かつて飛び立った木更津の滑走路を復元班に押されて走りきった。
地味な作業の積み重ねがロマンにつながることを肌で実感することとなったのだ。
翌年、ついに加藤は『ウルトラ』に配属された。
スタッフとして参加してまず驚いたのは、その厳格すぎるともいえるルールだった。
「絶対に挑戦者と話してはならない」
「挑戦者担当」と呼ばれる挑戦者のケアをするスタッフを除き、挨拶程度は構わないが、それ以上の会話は厳禁とされた。なぜなら行き先や問題などが漏れる可能性があるからだ。いや、漏れなくても、他の挑戦者に疑われた時点でアウトだ。だから、挑戦者としゃべることは決して許されなかった。
「ロケハンに行ってきます!」
ある日、加藤は大きな声で宣言しロケ地に向かおうとした。するとプロデューサーの佐藤孝吉から烈火の如く怒られた。
普通の番組なら、上の人間に伝わるようにADが大きな声で断りを入れて仕事を進めるのは当然のことだ。だが、この番組ではそれは許されない行為なのだ。ロケハンするなどといえば、もうすぐクイズがあるということが挑戦者たちに伝わってしまう。さらに万が一、その後をつけられればどんなクイズをやるのかもバレかねない。それだけ徹底してクイズの秘密は管理されていたのだ。
加藤は『第7回』でディレクターに昇格すると、『第11回』から総合演出を任されるようになった。
『ウルトラ』には番組を立ち上げた佐藤孝吉プロデューサーが掲げていた"憲法・前文"のような絶対的番組コンセプトがあった。
それが「太平洋戦争で負けた日本がアメリカをジャックする」というもの(※2)。
『第7回』でディレクターデビューした際も、アメリカ西部の開拓史が書かれた分厚い書籍を読むことを課せられたという。『ウルトラ』を撮るためにはフロンティア精神が必須だったのだ。
そんなコンセプトをもっとも体現した「クイズ」のひとつが、『第13回』の第12チェックポイントで行われた「爆走?コンボイリレークイズ」だ。
このクイズは、チムニーロックの50キロにわたる広大な直線の道を6台の巨大なコンボイが走り抜けるという、『ウルトラ』の中においてもとりわけスケールの大きな形式だった。
当時"ドル箱"ともいわれ、莫大な予算がかけられた『ウルトラ』といえども、もちろん予算は限られている。ただし、予算を出し渋ってしまうと『ウルトラ』に見合うスケールやスペクタクルは生み出せない。
そこで加藤たちが考えるのは、どうメリハリをつけるかだ。
十数箇所のチェックポイントそれぞれにバランスよく予算を配分してしまえば、すべてが中途半端なものになってしまう。そうではなく、ここが見せ場だという場所に惜しみなく予算を使う。そうすることによって最大の効果を生み出すのだ。
放送上はこのチムニーロックが第5週目、つまり最終週のオープニングに当たる。ここで大迫力のクイズを見せようと考えたのだ。そして、そこに「ロマン」が生まれたのだ。
逆にほとんど予算不要で生まれた名勝負もある。
同じく『第13回』の準決勝、ボルティモアでの戦いだ。
広大な草原にただ解答席が置かれているだけ。そこで行われるのは「激戦?通せんぼクイズ」という名の早押しクイズ対決。3ポイント獲得で"お立ち台"などと呼ばれる「通過席」に行くことができる(誤答は1ポイント減点)。このお立ち台でさらに正解すれば勝ち抜けで決勝戦の舞台であるニューヨーク行きが決まる。ただし、他の挑戦者が正解したり、本人が誤答して0ポイントに戻ったりすると再び解答席へ戻るというルールだった。
いずれもクイズ研究会出身で実力は伯仲していた挑戦者4人の対決は熾烈を極めた。
「クイズが始まったら決してカメラを止めてはならない」(※2)
それが佐藤孝吉が掲げた『ウルトラ』の決して犯してはならない、もうひとつの"憲法"だった。なぜなら『ウルトラ』はクイズ番組の名を借りたドキュメンタリー。ひとたび中断してしまえば挑戦者たちの感情がつながらなくなってしまうからだ。
けれど、あまりの激戦に勝負がつかず、用意していた問題は尽きようとしていた。慌てて予備の問題を準備し始めるが間に合わない。カメラのテープも残りわずかとなっていた。
「ここで一旦休憩!」
ついに"憲法"を破るときが来てしまった。それだけ4人ともが一歩も引かない、制作陣の予想を遥かに上回る激戦だったのだ。
「13年の歴史の中でもっとも素晴らしい戦いだった!」
福留功男は戦いを終えた若者たちをそう称賛した。加藤は、激戦に敗れた2人の若者の表情をつぶさに追い、『ウルトラ』史上に残る名シーンをカメラに刻み込んだ。
大金をかけた大スケールでも、予算をほとんどかけず純粋に勝負論に徹した戦いでも、結局、撮るべきは「人間」だ。その感情をいかにむき出しにさせ引き出すか。そこにこそスペクタクルが生まれるのだ。
(参考文献)
※1 『QUIZ JAPAN』Vol.14(セブンデイズウォー)
※2 戸部田誠:著『史上最大の木曜日 クイズっ子たちの青春記1980-1989』(双葉社)
<了>