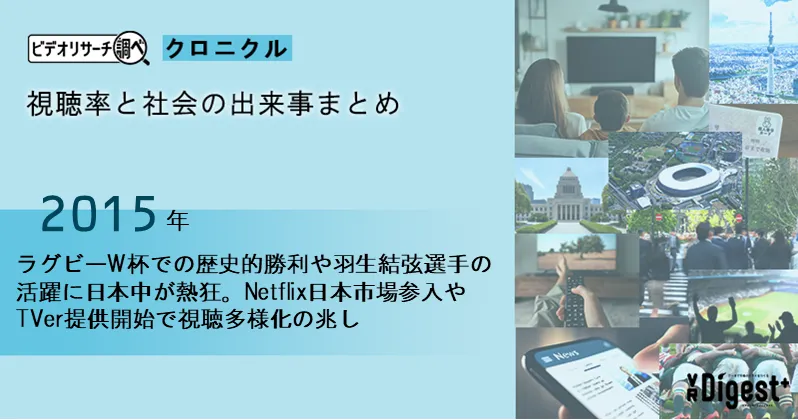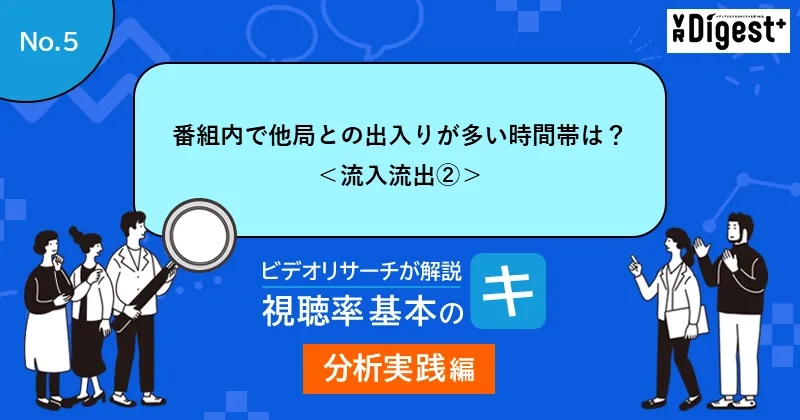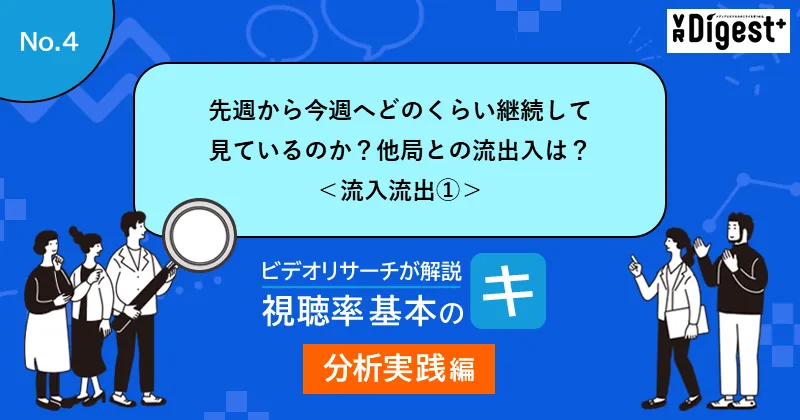てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「山田太一」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第37回
「学校どこですか」
テレビドラマ史上に輝く山田太一脚本の名作『ふぞろいの林檎たち』(TBS)には、各話に質問形式のサブタイトルがつけられているが、初回はこんなタイトルだった。
放送が開始された1983年頃、「大学生がドラマを見なくなった」という調査結果があったそうで、ならば大学生のドラマを作ろうと本作が企画された。だが、脚本の山田もプロデューサーの大山勝美も当時アラフィフ。当事者である大学生への取材が不可欠だった。
山田は集められた大学生たちに、日常の時間の使い方、バイトの種類、読んでいる本、好きな映画などを聞いていった。そして、「一番聞かれたくない質問は?」という問いに、1人の学生が答えたのが「学校どこ?」という質問だったのだ。
当時は今以上に学歴による"差別"があからさまだった。その一言に山田は「視座を得た」気持ちになったという(※1)。まさに「現代」の空気を掴んだ瞬間だった。
山田太一は、松竹に入社後、木下惠介監督に師事。木下惠介の映画をテレビドラマ用に脚色する仕事を始めると、1965年に脚本家として独立した。
1968年には「木下恵介アワー」枠の『3人家族』(TBS)を執筆。これは山田が初めて書いたオリジナル脚本による連続ドラマで、反響もよかったため、放送後にパーティーが開催された。「ああ、これでぼくは食べていけるなあ」と思ったという(※2)。
以降、山田はオリジナル脚本にこだわった。テレビでの放送は難しいと思うものは、小説や芝居など別のジャンルで書いた。
『岸辺のアルバム』(TBS)も当初はそうだった。登場人物も物語もあまりに暗い話であったため、テレビでは企画が通らないと思い新聞小説にしたのだ。けれど、嬉しい誤算であった。連載が進むにつれ、暗いだけの話ではないと理解してもらえ、TBSからドラマ化の話が来たのだ。
その後も様々な媒体で執筆しつつも、やはり山田の主戦場はテレビであり続けた。それは、山田がテレビの特性を最も理解していたからに他ならない。
山田は、「舞台と違いテレビは客の反応がダイレクトに見られないから不安だ」と語る一方で、「現実が舞台よりもものをいってしまう」のがテレビドラマの特性であり「生の皮膚であるとか、そういうものが映る」のがおもしろさだと言う。
テレビはすべてを映す。台詞以上のものを視聴者は画面から感じ取ることができるのだ。
「一人の人間が言葉で書いたもの、たとえば小説などがなかなか到達できない複雑さを、一瞬にして手に入れたり出来る」のだと(※3)。
また、山田はテレビドラマを書く際「なるべくストーリーを少なくしちゃおうということを自分の課題にした」という。なぜなら視聴者が物語ばかりを気にしてしまい、人間の心理描写を見逃してしまうからだ。
「こういうことが言いたいのだと答えられるようなドラマを書いても仕方がない。主張したいことが明確なドラマは、たいてい大ざっぱになりがちです。こういうことがあった、とそれをいいとか悪いとか判断せずに、まるごと捉えるようなドラマがいいドラマだと思っています」と山田は言うのだ(※3)。
1990年前後、社会は激動の時代を迎え、ニュースやドキュメンタリーのほうが面白いと注目が集まっていた。当時のインタビューで山田は「くやしいけれども賛成せざるを得ない」と同意しつつも、テレビカメラを向けてインタビューしても本当の現実を聞くことができるかというと、まず聞けない、と指摘している。
「人間はもっといろんなおもしろいものを秘めているんじゃないか、そういうものを知りたい」と語った上で、「ニュースやドキュメンタリーが立ち入れない、となれば何が立ち入れるかというと、フィクションだと思う」「逆にフィクションというものを手放したら、我々は本当の現実を語るチャンスを失ってしまう」と主張するのだ。
「現代」の複雑な現実をとらえるのは至難の業だ。それでも山田はフィクションの力を駆使して「現代」を書くことにこだわりながら、「その時代で多くの方が普遍性を感じるもの」(※2)を書き続けているのだ。
(参考文献)
(※1)日本放送作家協会・編『テレビ作家たちの50年』(NHK出版)
(※2)ビデオリサーチ・編『「視聴率」50の物語:テレビの歴史を創った50人が語る50の物語』(小学館)
(※3)『文藝春秋』1990年8月号(文藝春秋)
<了>