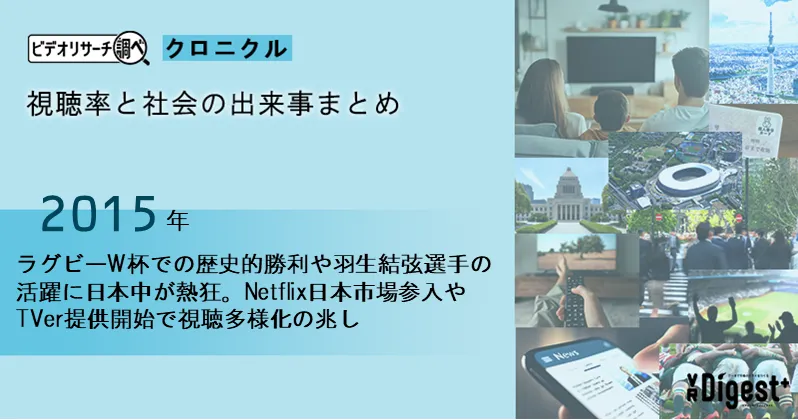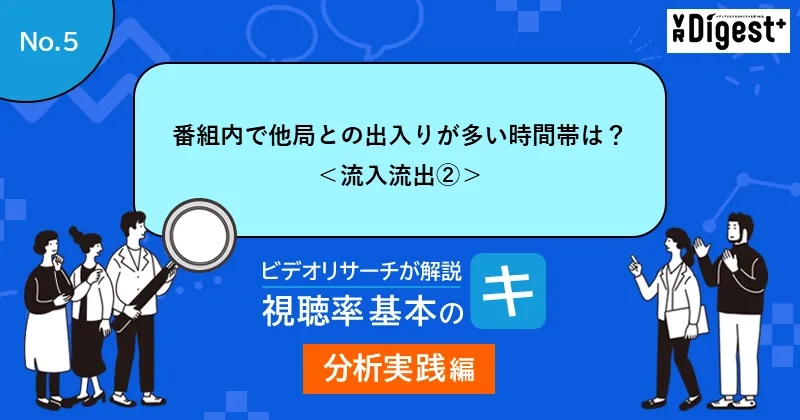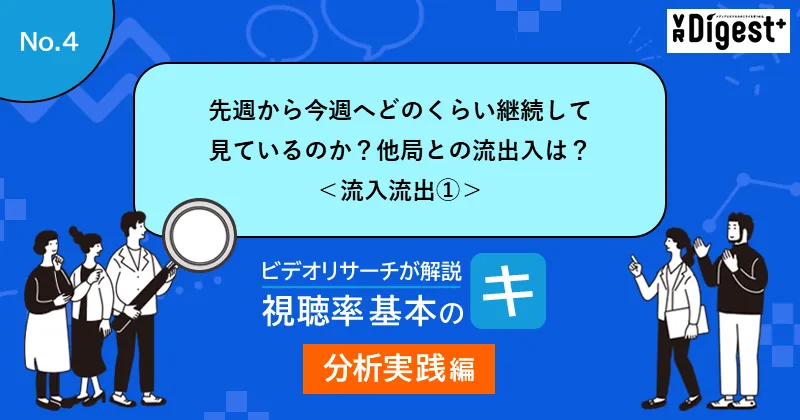てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「三木鶏郎」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第40回
永六輔、キノトール、野末陳平、直木賞作家の野坂昭如や神吉拓郎、「見上げてごらん夜の星を」や「いい湯だな」を作曲したいずみたく、日本を代表するジャズドラマーのジョージ川口、歌手の中村メイコ、コメディアンの三木のり平やなべおさみ、俳優の左とん平......。
様々なジャンルで活躍した昭和のビッグネームに共通するのは「三木鶏郎」だ。彼らは、三木鶏郎率いる三木鶏郎グループや三木鶏郎楽団に所属したり、その門下生だったメンバーだ。
"冗談音楽の怪人"と呼ばれ、数々のCMソングを手掛け、日本のポップカルチャーを作ったといわれている三木鶏郎だが、日本におけるテレビの放送作家の"始祖"といえる存在でもあるのだ。
青島幸男、大橋巨泉、前田武彦、そして門下の永六輔と、演者としても一時代を築いた放送作家は少なくないが、その"二刀流"のパイオニアでもある。
永六輔の証言によれば、1958年から放送された井原高忠演出による『光子の窓』(日本テレビ)に日本のテレビ番組で初めて構成者がクレジットされたという(※1)。
それが三木鮎郎、キノトール、永六輔といった三木鶏郎グループの面々だった。井原は早くから作家の重要性に気づき、作家たちを高待遇にしたことでも有名だ。そうして三木鶏郎グループはテレビの中で確固たる地位を築いていった。
三木鶏郎が最初に脚光を浴びたのはラジオ番組だった。東京帝国大学(現:東京大学)を卒業した後、すぐに就職するも戦争が始まり従軍。戦後は死生観が変わったことにより、元々好きだった音楽の道に進む。
「南の風が消えちゃった」という自作曲をNHKに持ち込むと、後に『NHKのど自慢』(NHK)などの立ち上げにかかわる丸山鐵雄に気に入られ、ラジオ番組の制作と出演を任された。それが1946年の『歌の新聞』(NHKラジオ)という番組であった。
痛烈な社会風刺と軽快な音楽をテンポよく絡めた構成は当時としては斬新で、「彗星のごとき天才現る」と新聞評が載ったという(※2)。
しかし、内容が進駐軍の検閲にふれ、番組はわずか半年で終わってしまう。代わりに1947年から始まったのが、いまや伝説の番組などといわれる『日曜娯楽版』(NHKラジオ)である。風刺コントをメインに据えた番組で、その中の「冗談音楽」というコーナーの出演・作・構成・演出を三木が務め、人気沸騰。
三木は時代の寵児となった。だが、やはりこの番組も時の政府から圧力がかかる。なにしろ、冗談音楽による風刺の最大の標的は政府だったからだ。
やがて三木の主戦場はテレビやCMへと移り変わっていく。
三木の構成作家としての奇才っぷりがよくわかるのが、『ヤマハタイム』(フジテレビ)という番組だ。フジテレビが開局してまもなく放送されていたというこの番組の内容を、三木鶏郎の事務所に残された8ミリフィルムで見たという荒俣宏が『TV博物誌』(小学館)に貴重な記録として書き残している。
その中から抜粋すると『ヤマハタイム』は以下のような番組だった。
そもそもこの番組は、今ではなかなかあり得ないことだが、文藝春秋が制作を手掛けていた。するとわずか1ヶ月ほどで制作が暗礁に乗り上げてしまった。なにしろ、番組制作などやったことがなかったからだ。
そこで文藝春秋が頼ったのが三木鶏郎だった。文藝春秋と三木は、『日曜娯楽版』(NHKラジオ)が権力による圧力で終わってしまったことに関する回想録を書いた縁があったのだ。
三木は『ヤマハタイム』の5回分を担当した。
そのタイトルは第1回「狂(マニア)」から始まり、「賭(トトカルチョ)」、「欲(エネルギー)」、「祭(フェスティバル)」、「泪(ウエット)」と洒落ている。
「たとえば第一回の『狂』は、六月の梅雨時期にあたるので、冒頭に役者がバケツをもって登場、これをぐるぐる回し、やにわに頭の上で回転をとめる。本人はズブ濡れ。唖然とする中で、タイトルが映しだされる。そして、 カーマニア、 洗濯マニア、ガンマニア、バレエマニアと、マニアのオンパレード。」(※1)
さらには、スタジオ内に神社を作ったり、番組放送中に靖国神社とフジテレビの間をオートバイで往復できるかを賭けたりと、まさにやりたい放題。靖国神社に向かったオートバイは途中で警察につかまって帰ってこなかったという。
「あの番組は、ぼくが東京の局でタッチしたいちばん大きな仕事だったが、うまくいった。 というのは、当時ぼくの下に有能な門下生がたくさんいた。音楽ではいずみたく、 作家では野坂昭如、気がついたら中国服着てテレビに映ってた野末陳平とかね。だから、なんでもできたんだ。 それで、本格的な風刺ミュージカルをつくってしまおうって話になったんだけどね」(※1)
そう三木鶏郎自身も回想している。
他にも1958年の関西テレビ開局記念特番『これがコマーシャルだ』(関西テレビ)は、全編がコマーシャルのミュージカルショー。各社が商品を呈示し、それを題材に寸劇が行われていく。
「日産の自動車のパートなんて、ラインダンスする女の子の列に車がはいってきてピタリと停まるんだが、女の子がまちがえて《さすがトヨタね!》っていっちゃったりね。出演してた森繁もね、かれの出番は厚木ナイロンのところでさ、《厚木アツギ、ツギがない》っていうんだけど、 脚本読んで、こんなもの開局記念特番になるわけないじゃないかといいだした。じゃあ、なにかしてくれってやり返したら、 森繁さん、マネキンの脚を抱いたんだよね。それだけ」(※1)
『日曜娯楽版』で彼を起用した盟友の丸山鐵雄が手掛けた『三十八度線上のサンタクロース』では、朝鮮戦争を題材ににらみ合う米ソ両軍の兵士の前にオルゴール人形が空から落ちてきて、その可愛らしさにしばし戦争を忘れるといった本を書いた。
また、テレビが家庭に運ばれてチャンネルをひねるところから始まる、テレビ目線、つまりテレビの一人称番組『吾輩はテレビである』という脚本も書いた。
「アイデアだけならいくらでもある」(※1)という彼は、その後、テレビ番組を離れてCMの世界で天下を取っていくのだ。
三木鶏郎は反骨精神と類まれな発想で創世期のテレビにユーモアと「自由」を持ち込んだのだ。
(参考文献)
(※1)荒俣宏・著『TV博物誌』(小学館)
(※2)太田省一・著『放送作家ほぼ全史 誰が日本のテレビを創ったのか』(星海社新書)
<了>