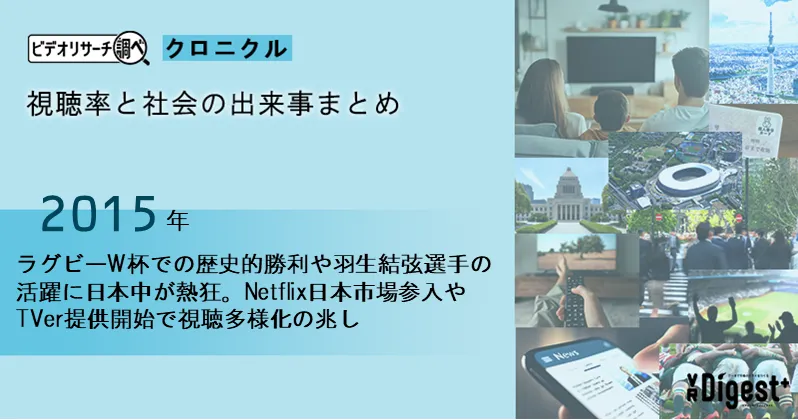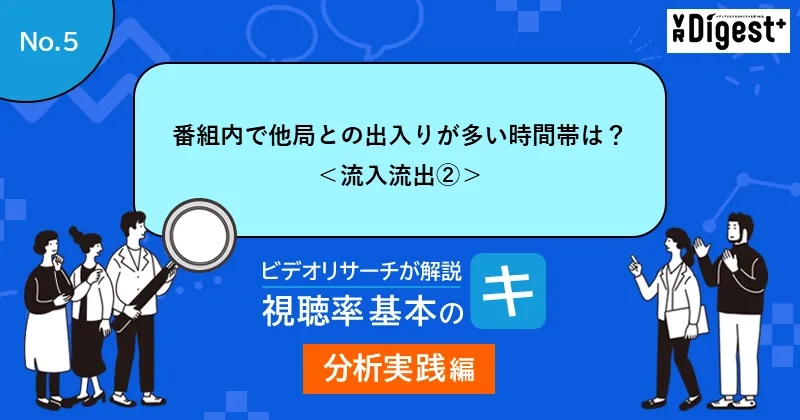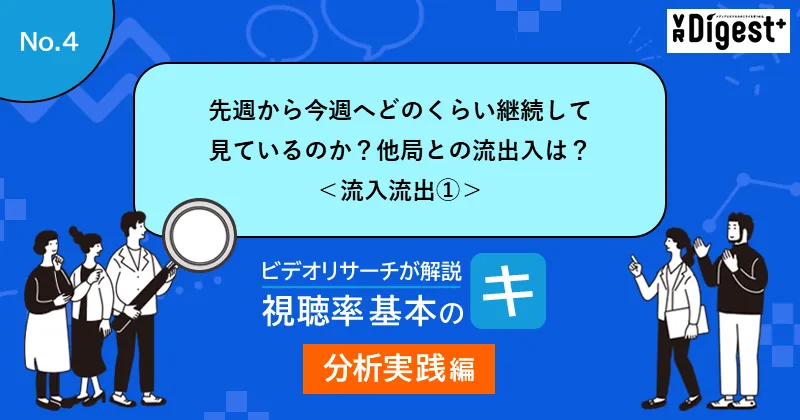てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「中島丈博」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第44回
誰も調べたことがないせまい歴史を調査・報告するバラエティ番組『私のバカせまい史』(フジテレビ)。
現在は毎週木曜21時のゴールデンタイムでレギュラー放送されているが、そのお試し段階であるパイロット版時代に、お笑いコンビ・インパルス板倉によって研究発表されたのが「ドロドロ昼ドラ"愛憎グルメ"史」だった。
1964年から2016年に至るまで214作品が作られた昼ドラ。
そこに初めて"愛憎グルメ"が登場したのが2002年に放送された『真珠夫人』(フジテレビ系)だという。それが、あの有名な「たわしコロッケ」だ。スタッフは「少しでもコロッケに似るようにたわしの毛を刈り込んだ」とこだわりを証言する。
その2年後の2004年『牡丹と薔薇』で「財布ステーキ」が登場すると、2006年の『偽りの花園』では「草履カツレツ」「五寸釘入り玄米パン」、2007年『麗わしき鬼』(いずれもフジテレビ系)の「携帯ケーキ」と続いていく。
そのすべてを考案したのが脚本家の中島丈博だ。
中島は「嫌がらせ、復讐、愛をはかる、そのために作る料理。料理を作っている間に彼女の胸に去来する想い。あらゆる感情が絡まり合って『どうぞあなた』って出すわけだから。愛憎半ばするから人間は苦しむんですよね」と語るのだ。
そんな中島が「第2の故郷」と呼ぶのが高知県中村市(現・四万十市)の下田地区。終戦間際の1945年、10歳の頃に京都から疎開してきて21歳まで暮らした町だ。
日本画家の中島敬朝を父に持ち、芸術家の多い京都で生まれた中島にとって、プライバシーがあけすけであった田舎町はカルチャーショックだった。
「性にオープンな土地柄で、モラルだけで律しきれない人間が生きる姿が丸見えでした。そこがボクの原点」(※1)と振り返るように、中島の人間観はここで培われた。
高校の頃はシナリオを読みまくる演劇少年だった。高校を卒業してからは銀行に就職したが、演劇サークルに入って役者をやりながらシナリオを勉強した。
社会人3年目に、東京のシナリオコンクールに送った作品が佳作となり、脚本家の夢を捨てきれずに上京。
当時、開設されたばかりのシナリオ作家協会設立シナリオ研究所の第1期生となった。そして、同人誌に発表したシナリオがきっかけとなり、橋本忍に師事することになる。24~25歳の頃だ。
毎日橋本の自宅に通い、仕事への姿勢を徹底的に教わった。橋本は「一日八時間は机の前に座っていろ。まず座ることから始まり、書き続けてものになっていくのだから」と厳しく指導した。立っていいのは昼食時とトイレに行く時だけ(※2)。毎日、机に差し向かいになって仕事し、気の休まることはなかったという。
「ある場面を書いてと注文され、提出しても突き返される。細かい指示はなく、『違う』とだけ言われる。それを10回ほど繰り返し、ようやく1、2行採用される日々だった」(※3)と述懐する。
仕事ぶりは職人のようで、決まって午前9時から夕方6時まで机に向かう。時間になると「中島くん、今日は(筆を)置こうか」(※3)と仕事を終えていたという。
中島は1961年、橋本が監督を務めた東宝映画『南の風と波』で脚本家デビュー。その後は『四畳半襖の裏張り』など日活ロマンポルノ、キネマ旬報ベストテン1位に輝いたATGの『津軽じょんがら節』などの映画から、『元禄繚乱』『草燃える』などのNHK大河ドラマまで幅広い作品を書き続けた。
1989年には『恋愛模様』『海照らし』『幸福な市民』(いずれもNHK)の3作品で向田邦子賞を獲得した。それらほとんどの作品に共通するのは、人間性をむき出しにして葛藤する姿を描いていることだった。
そんな彼の作風をもっとも活かせる集大成的な場となったのが、1995年から参加した東海テレビ制作の昼ドラだった。
執筆の依頼があった当初はあまり乗り気ではなく「軽い気持ち」で引き受けたという。だが、実際にやってみると思いの外、面白かった。
「昼ドラって時間がたっぷりあるから、人間の情感とか葛藤を書き込めるんですよ。セリフもね、どれだけ書いても大丈夫。30分が全 60回くらい、最近は40回前後のものもあったけど、この長さでセリフを中心にガンガン押していける、脚本家にとって面白いドラマだったんです」(※4)
大河ドラマの経験もあったため、長い連続ドラマも苦にならない。普段は午前中から書き始め、夕方6時には仕事を終えると証言している。そう、師・橋本忍とまったく同じやり方だ。
担当プロデューサーは「ウチのドラマにタブーはない。自由に書いてください」と言ってくれたという(※4)。
その覚悟に応え、中島は愛憎とエロス、人間の業をこれでもかと過剰なまでに書き込んだ。その根底には「人間は本来、愚かなもの、滑稽なもの、悲しいもの。きれいごとの中からドラマは生まれない」(※5)という思いがある。
「人間の中には、愚かさも崇高さも混在している。むき出しになったものの中にこそドラマの醍醐味があり、自分でも乗って書いてしまう。今はみんな相手に遠慮して、自分を全開にして相手にぶつけることを怖がっている時代だと思うんですね。だから欲求不満になる。愚かさもバカさ加減も見せながら突っ走っていくドラマがあれば、欲求不満の解消になると思いますよね」(※5)
そうやって、唯一無二の人間らしさがむき出しのドラマを生み出したのだ。
(参考文献)
(※1)「毎日新聞」2006年05月08日
(※2)「中日新聞」2018年07月21日
(※3)「読売新聞」2018年07月23日
(※4)『週刊女性』2016年3月8日号
(※5)「中日新聞」2012年09月13日
<了>