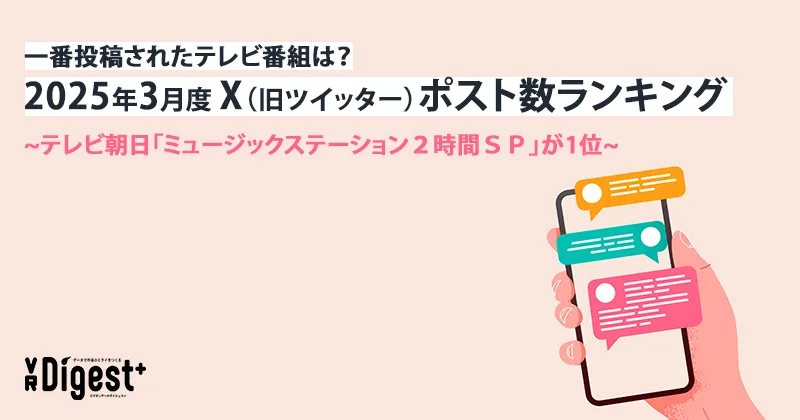てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「鵜沢茂郎」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第47回
『ニュースステーション』(テレビ朝日)が、報道番組として革新的であったことに異論を挟む者はいないだろう。
初代プロデューサーは、後にテレビ朝日の生え抜きとして初めて同局の社長・会長を歴任することになる早河洋。早河は、1967年にテレビ朝日の前身である日本教育テレビ(NET)に入社すると、報道畑を歩み、1983年にジャーナリストの筑紫哲也を起用した『TVスクープ』(テレビ朝日)などを立ち上げた。そして1985年、『ニュースステーション』を生み出したのだ。
もちろん、それは簡単なことではなかった。何しろ当時、平日プライム帯で約80分という長尺の報道番組を作ることは前代未聞。その前例を覆すためには、大きな起爆剤が必要だった。そこで白羽の矢が立てられたのが、久米宏だった。久米といえば元TBSアナウンサーではあるが、『ザ・ベストテン』『ぴったし カン・カン』(いずれもTBS)など、エンタメ分野で活躍してきた。従来、報道番組のキャスターといえば活字媒体の出身者が多かった。しかし、早河はそんな常識を覆したかった。
「エリートがしたり顔で読み上げるニュースはやめよう。中学生でも分かるニュースにしよう」(※1)
そうして「日本初のニュースショー」ともいえる『ニュースステーション』が誕生したのだ。
そのコンセプトを実現するために報道番組の常識を覆す試みが数多くおこなわれた。その中でもっとも革新的だった試みのひとつは、報道番組に放送作家を本格的に導入したことだ。
放送作家といえば、バラエティ番組の企画を考えたり、構成台本を書いたりする仕事だ。果たして、ニュースを伝える報道番組にそんな人たちが必要なのか。その風当たりは強かった。
『ニュースステーション』の立ち上げに参加したスタッフは、久米が所属する企画・制作プロダクション「オフィス・トゥー・ワン」(以下、OTO)からのスタッフを含む何十人という、報道番組としては空前絶後の大所帯で、その中に数人、放送作家も入った。
久米宏は自身の著書の中で、報道畑のスタッフとOTOをはじめとするバラエティ畑を歩んできたスタッフとの軋轢を「スーツ集団と短パン集団」とコミカルに表現してこう綴っている。
報道局の記者・デスクたちは、制作会社の人間とは口を聞いたこともない、いわばエリート集団だ。対するOTOのディレクターや放送作家たちは、報道のことなどまったく知らない雑草軍団だ。
全体会議は、報道局のスーツ姿が並ぶ会議室に、短パン、Tシャツ、ゴム草履姿の連中が乗り込んで対峙するかたちとなった。
「報道局の人たちはスーツなんだから、こちらもそれなりのきちんとした格好で臨むように」
海老名さん(引用者注:OTOの社長)がOTOスタッフに申し渡すと、
「服装なんてどうでもいいじゃないですか。問題は仕事の中身でしょう」
そこから始めなければならなかった。最初は言い合いばかりで、話がまったくかみ合わない。報道局側は事実を正確に伝えるという正統的なニュース報道のあり方にこだわり、派手な演出や目新しい工夫を嫌った。OTO側は、ニュースをいかにわかりやすく面白く見せるかに重点を置き、セットやスタジオ演出に気を配る。そのズレは容易には解消しなかった。(※2)
引用元:久米宏:著『久米宏です。 ニュースステーションはザ・ベストテンだった』(世界文化社)
そんなバラエティ畑を歩んできた「短パン集団」の雄が、放送作家の鵜沢茂郎だ。鵜沢は、『カックラキン大放送!!』『金曜10時!うわさのチャンネル!!』(いずれも日本テレビ)、『水曜スペシャル』(テレビ朝日)の「川口浩探検隊シリーズ」などに参加。そして『久米宏のTVスクランブル』(日本テレビ)のメイン作家を担当。この番組は「未来のニュース番組につながるステップボードのような役割を果たしている」(※2)と久米が振り返っている通り、『ニュースステーション』にその重要なエッセンスの一部(たとえば「中学生でもわかるニュース」「テレビ的ニュース」といったコンセプト)が継承されている。だから、『ニュースステーション』に鵜沢が起用されるのは必然だった。
とはいっても、鵜沢自身は、1985年10月7日の第1回の生放送のスタジオに立ち会った時、「この番組がテレビの歴史を画期的なものになるという予感はなかった」という。(※3)
むしろ、失望のほうが大きかった。手法に新鮮さもなく、慣れないスタッフの不手際もあり、進行がギクシャクしている。中継ネタも弱い。報道局主体の番組とはこんなものか、と。
反省会は連日深夜まで及び、空中分解寸前の緊張感だったという。
久米らが掲げる「中学生でもわかるニュース」というコンセプトを、どのように具現化すれば良いか、それを報道マンにイメージさせるのは、あまりにも困難な作業だった。そもそもそんな発想で報道に向き合ったことなど皆無なのだから。
その意識の違いが如実にあらわれた場面を鵜沢はこう振り返っている。
「政治部の記者が新聞の常套句「政局は正に流動化しています」とレポートしていた。これでは中学生には分からない。すなわち、流動化とは映像にするとどのようなものなのか、具体的に見せるのがこの番組のコンセプトであるべきだ、と反省会で述べたがそれに反応するスタッフはいなかった」(※3)
引用元:日本放送作家協会:編『テレビ作家たちの50年』(NHK出版)
「密室の茶番劇」という常套句で伝えるのではなく、「密室なのになぜ茶番劇だと分かるのか、視聴者に説明すべきだ」(※3)と鵜沢が主張した。
当時、政局は三派にわかれ、主導権争いが"密室"でおこなわれていた。それをわかりやすく可視化することはできないか。
そこで「日々変動している総裁選の動きを映像で中学生にも分かりやすく見せるための小道具として、三派の人数を積木で表すことが発案された」(※3)。今では多くのニュース番組が採用している手法だ。しかし、当時は斬新だった。しかも、そこに久米宏の卓越した話術が加わる。そうして、「密室の茶番劇」は見事に"映像化"されたのだ。
それはまさにテレビでしかできない「テレビ的」な報道番組「ニュースショー」誕生の瞬間だった。
放送作家、報道マン、制作会社スタッフ三者のギクシャクした関係も早河洋の手腕で次第に融合していき、それぞれの得意分野を活かし合いながら円滑に進むようになっていった。やがて、視聴率のオバケ番組となった。その頃にはもう、ニュースに放送作家はいらないという声は聞こえなくなっていたのだ。
(参考文献)
(※1)『文藝春秋』2016年10月号
(※2)久米宏:著『久米宏です。 ニュースステーションはザ・ベストテンだった』(世界文化社)
(※3)日本放送作家協会:編『テレビ作家たちの50年』(NHK出版)
<了>