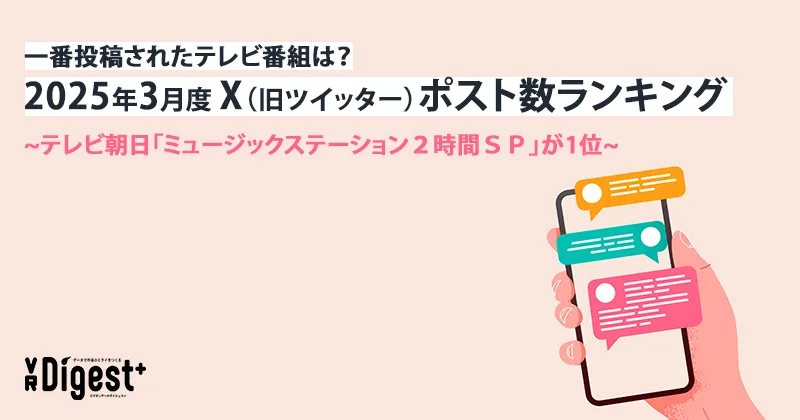てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「森達也」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第49回
今年公開された映画『福田村事件』。その監督を務めたのは森達也。今作はいわゆる劇映画だが、言うまでもなく森達也は日本を代表するドキュメンタリストのひとりだ。
これまでオウム真理教を描いた『A』や『A2』、ゴーストライター騒動の渦中にあった佐村河内守に密着した『FAKE』などのドキュメンタリー映画を手がけ、大きな話題を呼んだ。そんな森達也がテレビドキュメンタリー出身だということもよく知られていることだろう。
もともと森達也は役者志望だった。10代の頃から友人たちと自主映画を制作し、大学卒業後は俳優養成所に通っていた。商業映画に端役で出演したこともあったが、まったく芽が出なかったという。
結婚や子供の誕生を機に広告会社や不動産会社などに就職するも映像の仕事への未練を断ち切れず、番組制作会社テレコム・ジャパン(現・テレコムスタッフ)の求人を見つけ応募した。
テレビドラマ制作を志望していたが、当時同社はほとんどドラマを作っておらず、ドキュメンタリー制作が主な業務。仕方なくドキュメンタリーの世界に足を踏み入れることになったが、最初にADとして就いた番組の撮影がはちゃめちゃだったことで、「この仕事、なかなか悪くない」と思うようになった(※1)。
入社2年目でディレクターに昇格し、最初に出した企画が小人症のレスラーたちによるプロレス、いわゆるミゼットプロレスについてのドキュメンタリーだった。その時点で森はその企画がある種のタブーに触れていることを知らなかった。
実際、テレコム・ジャパン内では、「局に提案してもこんな企画が通るはずがない」という反応がほとんど。結局、森はテレコム・ジャパンを退社。別の制作会社と契約し、プロデューサーという肩書を得ると、その企画をフジテレビに持ち込んだ。すると、深夜のドキュメンタリー番組『NONFIX』で放送されることとなった。ミゼットレスラーたちが出ることで抗議が来ることも危惧されたが、抗議など来なかったという。
その後、ドキュメンタリー番組やニュース番組の特集企画などを手がけていたが、1995年、地下鉄サリン事件が起き、ニュースはオウム一色になった。
そんな中、取材陣で唯一教団の中に入り、ドキュメンタリーとして撮影を始めた。なぜ森だけが中に入れたかというと、答えは単純。正面からドキュメンタリーの撮影依頼をしたのが森だけだったからだ。もちろん、森はテレビで放送するつもりで撮影していたが、どの局も拒否したため『A』として劇場公開されることになった。
『A』を発表後、森はテレビドキュメンタリーに"復帰"する。
最初に撮ったのは、「超能力」を生業にする人たちを追った『職業欄はエスパー』(1998年、フジテレビ)。少年時代スプーン曲げで一世を風靡した清田益章をはじめ、堤裕司、秋山眞人を主人公に据えた。いずれも70年代のオカルトブームで超能力少年と騒がれた人物。その日常を描いた。
さらには『放送禁止歌〜唄っているのは誰? 規制するのは誰?~』(1999年、フジテレビ)を制作。放送業界のタブーである「放送禁止歌」がいかに曖昧で根拠がないものかということを暴いた。
宮沢賢治の童話『よだかの星』をモチーフに商品開発と動物実験の現状を描いた『1999年のよだかの星』(1999年、フジテレビ)では、なかなか企画が理解してもらえなかったという。
「企画書を提出した局のプロデューサーに『そんな恣意的なドキュメンタリーはありえないでしょう』と真顔で言われ、『恣意的ではないドキュメンタリーなど意味があるのですか』と思わず聞き返したことがある」(※1)と振り返っている。ドキュメンタリーはよく「公正中立」が是で「客観的な事実の集積」などといわれるが、そんなものはありえない。どこまでも主観的なものなのだ。
そのことを「メディアリテラシー」向上の一環として描いたのが、森が企画・監修、そして出演者として参加した『ドキュメンタリーは嘘をつく』(2006年、テレビ東京)だ。
この番組で森は自らカメラを回しながら『ゆきゆきて、神軍』などで知られる原一男ら、第一線で活躍するドキュメンタリストに話を聞いていくのだが、その様子を「メイキング」として撮影しているカメラとの"ズレ"が徐々にあらわれ、一種の違和感が漂ってくる。
遅刻をしたり、現場を休みがちになったりした森は、やがて一方的に番組を降板してしまう。混乱する現場の中で、メイキングのディレクターだった村上賢司によって撮影は継続していく。そしてエンディングにどんでん返しともいえる"事実"が明かされるのだ。
これは、いわゆるフェイク・ドキュメンタリー。かつて俳優を目指していた森の演技力が垣間見える。
プロデューサーの替山茂樹はフェイク・ドキュメンタリーにした理由を次のように語っている。
「メディアリテラシーは『メディアからの全ての情報を、鵜呑みにせずに自分の頭で考えて判断する』ということだと思ってます。メディアからの情報は全てを鵜呑みにするのではなく、自分で判断することが大事だ......という以上は、『そういう主張をしている番組自体も』鵜呑みにしたらダメですよね。ということがあったんで、ああいう構成にした訳です。
森さんとどういう番組にするか打ち合せをした時にフェイク・ドキュメンタリーという手法に決めたのは、番組のテーマに合致すると思ったからです」(※2)
この番組は日本民間放送連盟賞・特別表彰部門「放送と公共性」で優秀賞を受賞した。
受賞理由は「蛮勇」。
辞書には「理非を考えず、むやみやたらに発揮する勇気。向こう見ずの勇気」とある。まさにこの番組のみならず、森達也そのものを示す言葉だ。
森達也は、テレビのタブーに蛮勇を持って足を踏み入れる。
しかし、森は平然と言うのだ。
「『タブーだと皆が思いこんでいることのほとんどはタブーではない』ことを呈示しただけで、タブーそのものには抵触していない」(※1)と。
(参考文献)
(※1)森達也・著『それでもドキュメンタリーは嘘をつく』(角川文庫)
(※2)森達也・替山茂樹・著『ドキュメント・森達也の「ドキュメンタリーは嘘をつく」』(キネマ旬報社)
<了>