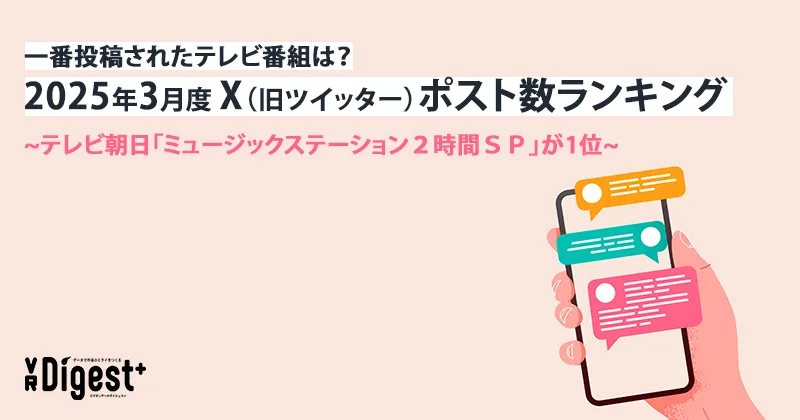てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「鶴橋康夫」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第51回
よくテレビドラマは「脚本家のもの」などと言われるが、堀川とんこう、杉田成道、そして鶴橋康夫らが牽引した「個性派ディレクターの時代」も確かにあった。
昨年10月、「映像の魔術師」などと呼ばれた監督・鶴橋康夫が亡くなった。その訃報に映画『後妻業の女』などで仕事を共にした大竹しのぶは、自身のSNSに長文で感謝の思いを綴っていた。
それによると2人の出会いは彼女が20代の初めの頃だったという。
「その時期、私はあまりに忙しかったので自分の時間が欲しいという理由でお断りしたのですが、とにかく会って話を聞いてくれと言われ、マネージャーさんの自宅でお会いしたのでした。
『この作品にどれだけ君が必要か』と延々お話をされて、夕方になり、夜になり、私も強情だったけど鶴橋監督はそれ以上でとうとう私は泣き出してしまって。そんな出会いでした。」
それから何度となく仕事を共にした2人。投稿に添えられた写真は、撮影が終わると毎回鶴橋がくれたという直筆の「感謝状」だった。
その「感謝状」が示すとおり、「人たらし」とも評される鶴橋はチームを大事にする監督だった。それは俳優に対してだけではない。
いつしか、鶴橋と共に仕事をするスタッフは「鶴橋組」などと呼ばれ、テレビドラマ界では有名となっていた。鶴橋は一人ひとりのスタッフの名前を完璧に覚えるまで仕事に入らなかった。
そして、撮影前にこれから撮るドラマの狙いを末端のスタッフにまでしっかりと共有した。それぞれの持ち場でどう行動したらよいかを主体的に考えてもらうためだ。
「そのためには、今度のドラマはどういう制作意図を持っているかを、自分自身でまずしっかりつかんでおかなければならないし、誰にでもその意図をわかりやすく話せるようにしておく必要がある」(※1)という鶴橋のもと、自然とスタッフが育っていったのだ。
鶴橋は1940年、新潟県に生まれた。中央大学卒業後はジャーナリスト志望だったが、先輩の読売新聞記者に「関西には日本の文化の源泉があるし、関西で仕事をするのは日本文化の基本に触れられるのだから、これはいい機会ではないか」と説得され読売テレビで働くことになった(※1)。
そこからドラマ演出畑一本で歩んでいった。鶴橋が頭角を現したのは、76年に放送された『新車の中の女』(読売テレビ)。主演は浅丘ルリ子。その後、何度となくコンビを組む盟友だ。
浅丘の鶴橋への信頼は、その後の過激ともいえる役柄を厭わず演じたことからも窺える。
例えば『魔性』(1984年)では、女性同士のラブシーンや自慰、失禁シーンなども演じた。それを生々しく艷やかでありながらも流麗な映像で魅せるのが鶴橋のドラマだった。
脚本家もまた、鶴橋のもとで飛躍した。とりわけ鶴橋と共に名作を作り上げたのは、池端俊策と野沢尚だ。
池端とは彼が職業を転々としている時期に出会い、懸命に自分探しをしている姿に惹かれた鶴橋は池端を脚本に起用した。
1982年、芸術選奨新人賞(放送部門)を受賞した『かげろうの死』(読売テレビ)で初めて仕事をして以降、数多くの作品でコンビを組むことになる。
20歳も年の離れた野沢は「鶴橋学校の生徒」を自称していた(※2)。若い頃から鶴橋の仕事場に出入りしていた野沢に、1985年『殺して、あなた...』(読売テレビ)の脚本を新藤兼人と共同して書かせたことが始まりだった。
その後、鶴橋組で鍛えられた野沢は90年代半ばにブレイク。話題の連ドラを数多く手がけていくことになる。2000年には再び鶴橋組で『リミット もしも、わが子が...』(読売テレビ)の脚本を執筆した。
鶴橋は野沢に「この人物はどんな人生を背負って今、ドラマの地平線に立っているのか」を問いかけ、登場人物の背景を徹底的に話し合った。そして、ドラマ本編には出てこないような細かい出来事も含め、キャラクターの「履歴書」を作って人物を立体的に描いた。
「描く対象が何であれ、ヘドが出るほど調べることから出発するしかない。ジャーナリストのように嗅ぎ回り、どこに真実があるのかを探しまわらねばならない。事実はいっぱいあるが、それらの事実の中から真実を選び出していくのが、最も大切な仕事になるからである」(※1)
その鶴橋の信念は、ジャーナリスト志望だった彼ならではのものに違いない。
鶴橋は、オールロケで同じシーンを1台のカメラを使って様々なアングルから撮る手法を多用していた。テレビジョンの語源は「遠くのものを見る」こと。
そこから鶴橋は、一番遠いものは何かと考え、それは「心」ではないかと結論づけた。
「だから僕のドラマはどこかドキュメンタリーなの。学生時代に安保闘争があったんだけど、機動隊の後ろと学生の後ろにいるカメラとでは映るものがまるで違った。しかも、小型カメラが衝突の真ん中で両者を舐めるように撮っている。テレビって不思議な存在だと思ったね。あっちからもこっちからも撮りまくったら、その隙間から人間の心が読めるかもしれないな、と。だから僕のは一種の個人的ドキュメンタリー」(※3)
戦う相手は他のテレビドラマではなく、一流の映画や文学。それに負けない映像表現を模索し続けた。
そうやってテレビドラマの新しい表現を共に切り開いてきた戦友である野沢尚が、2004年、突然自ら命を絶った。それは鶴橋にとってあまりにもショックな出来事だった。
「彼の突然の死で、僕は放心状態になった。僕は何すればいいんだ? と。そこで彼の兄貴分である池端俊策に泣きついたんだ」(※3)
鶴橋は翌2005年、WOWOWで『ぶるうかなりや』を制作する。内部崩壊したある家族が、それぞれ自分を取り戻し立ち上がろうとする姿を描いたドラマだ。
脚本は池端。彼は「不器用な父親とそのせいで失語症になった息子の話をやりましょう。 題名は"ぶるうかなりや"。野沢は青い鳥だった......」(※3)と鶴橋に提案した。
鶴橋組の戦友への鎮魂歌を、鶴橋はやはり自らが愛したテレビドラマという形で贈ったのだ。
(参考文献)
(※1)志賀信夫・著『映像の先駆者125人の肖像』(NHK出版)
(※2)『GALAC』(NPO法人放送批評懇談会)2024年2月号
(※3)NPO法人放送批評懇談会・著『放送批評の50年』(学文社)
<了>