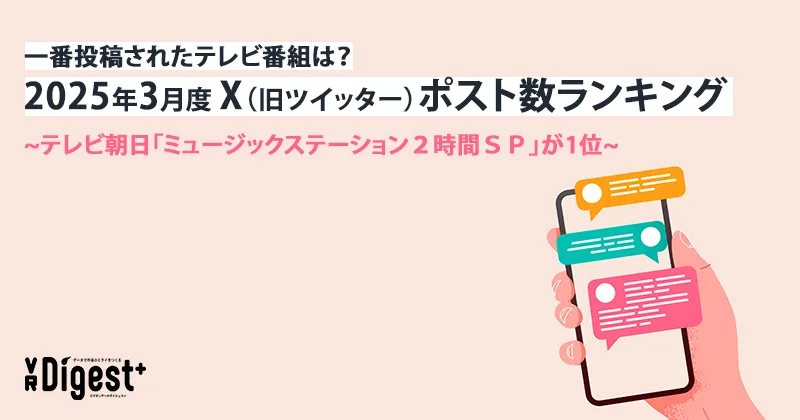てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「佐藤敦」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第54回
「同情するなら金をくれ!」
今からちょうど30年前の1994年4月16日から7月2日まで放送された安達祐実主演の『家なき子』(日本テレビ)は、そんな流行語を生み出しながら、最高視聴率37.2%(関東地区)を記録する大ヒットドラマとなった。
このドラマのプロデューサーを務めたのは、この年に日本テレビに中途入社したばかりの佐藤敦。
日本テレビにとってまさに「救世主」となった人物だ。
当時テレビドラマは、トレンディドラマ路線を突っ走っていたフジテレビが絶対的な強さを誇っていた。それに対抗できるのは、かつて「ドラマのTBS」と称されていたTBSだけ。
日本テレビには、ほとんどヒット作がなかった。
80年代、低迷していた日本テレビは、80年代末頃から「打倒・フジテレビ」を掲げ、有望な若手社員たちを集めた「クイズプロジェクト」を立ち上げるなど、バラエティ番組を強化していった。
90年代に入ると、その成果として『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』や『マジカル頭脳パワー!!』、『世界まる見え!テレビ特捜部』などの大人気番組を生み、フジテレビを凌駕するまでになっていた。
しかし、ドラマにおいては大きく水をあけられており、目標としていた視聴率「三冠王」奪還に向けて残された最後のピースがドラマだといえた。
そのため、日本テレビでは1992年末に「ドラマプロジェクト」を発足。
視聴者にいかに楽しんでもらうかを重視するバラエティの発想をドラマに持ち込むことで、ドラマの作り手に刺激を与えることを目的のひとつとしたプロジェクトで、ドラマの既成概念にとらわれない「時代のニーズに合うドラマ」や「社会現象になりうるドラマ」をつくることを目指した。
そこで白羽の矢が立ったのが、「クイズプロジェクト」で実績を上げた小杉善信だ。94年にはドラマ班のチーフプロデューサーに就いた。
就任してすぐ、小杉は日テレドラマ班の問題点に気がついた。観てもらえば面白いのに、観てもらえない。気づかない視聴者が悪い。そんなクリエイター特有の「作品意識」がはびこっていたのだ。
そんなとき、中途入社してきたのが、佐藤敦だった。
年間600本近くの作品を観るような映画青年だった佐藤は、明治大学を卒業すると1979年に日活(当時・にっかつ)に入社した。
当初は助監督を務めたが、本人曰く「クビになって」、通称「テレビ部」と呼ばれる企画営業本部に配属になった。主に2時間ドラマの企画を考えるのが仕事だった。
この頃の「テレビ部」は、部員が10人にも満たない小さな部署だったが、ここから脚本家の北川悦吏子や龍居由佳里、演出・脚本家の両沢和幸、そして佐藤といった、後にテレビドラマ界を支える人材を輩出している。
その要因のひとつが、部長だった栗林茂の存在だ。
彼は、企画力のあるプロデューサーを育てるため、佐藤らに企画書やプロットを書かせた。
そしてそれを丁寧に添削してくれたのだ。この経験で佐藤は、ドラマづくりのポイントを掴んでいった。
そんな矢先の1993年、にっかつが会社更生法の適用を申請し事実上倒産(97年に会社更生法が適用され、「日活」として復活)。このとき佐藤に声をかけたのが、「ドラマプロジェクト」のリーダーである高橋進だった。
そして佐藤は、"手土産"のように、日本テレビに稀代の脚本家・野島伸司を招聘したのだ。
この頃の野島伸司といえば、フジテレビでは『101回目のプロポーズ』や『ひとつ屋根の下』、TBSでは『高校教師』など、書けば高視聴率を叩き出す大ヒットメーカー。
だが、日本テレビにはまったく縁がなかった。佐藤は、にっかつ時代に「一緒にやりましょう」と約束していた縁で、企画・原案という形で野島を起用したのだ。
野島から出た案が「現代の『フランダースの犬』」だった。
これまでの日テレのドラマ班なら、そんな企画は通らなかったかもしれない。けれど、小杉・高橋によって意識改革がなされた日本テレビでは突っ切ることができた。
天才子役として話題を呼んでいた安達祐実を主演にすることはすぐに決まった。だが、そのキャラクターについては試行錯誤が繰り返された。
当初は『フランダースの犬』の主人公・ネロのような心優しい設定だったが、まじめないい子が頑張っても、いまひとつ面白くないと佐藤は感じていた。
「悪ガキにしてみたら」
そう言ったのは、野島伸司だったという(※1)。こうして、口が悪く犯罪まがいの行為もいとわない少女・相沢すずが誕生した。
「あまりにも反社会的だったんで、"なんでこんなのやるんだ!"って怒ってたアシスタントディレクターもいました(笑)。それまで、前向きなドラマを作ってきた局としては、ひどいヤツがいきなり入って来て、ひどいドラマを作ったっていう感じだったんじゃないですか」(※2)
すずをより魅力的なキャラクターにするために、「決め台詞」をつくることにした。このとき、佐藤の脳裏にはある記憶がフラッシュバックした。
それは他ならぬ、にっかつの倒産騒ぎのときの記憶だ。
多くの人から「大変だね」と同情され、そのときに、大変だねと思うなら金をくれよ、と思ったのだという。「同情するなら金をくれ!」は、佐藤の実体験から生まれたセリフだったのだ。
だからこそ、体重の乗ったセリフとなり、社会を動かすほどの"現象"を生んだのだ。
ショッキングな内容に抗議の電話は殺到したが、視聴者センター任せにせず、自分たちもデスクに座って対応した。それだけの信念があったのだ。
「人生はいいことばかりではない。いろんな道のりを越えながら人は成長していく。その過程を描いている。(ドラマで)成長の過程を見ていただきたい」(※1)と。
それはまさに佐藤の人生そのものだ。
初回10%台だった視聴率は、右肩上がりに上がっていった。まさに「ドラマプロジェクト」が目標として掲げた、ドラマの既成概念にとらわれない「時代のニーズに合うドラマ」や「社会現象になりうるドラマ」を実現させた。
そんな『家なき子』の大ヒットもあり、この年、日本テレビは、悲願の視聴率「三冠王」奪還を達成。その後も佐藤は『金田一少年の事件簿』や『透明人間』などを手掛け、土曜ドラマの新たなカラーを確立し、ティーンエイジャーの市場を開拓していったのだ。
(参考文献)
(※1)スポーツ報知「[あの時]日テレ『家なき子』爆発的ヒット」(2019年3月19~23日)
(※2)伊藤愛子:著『視聴率の戦士 テレビクリエイター列伝』(ぴあ)
<了>