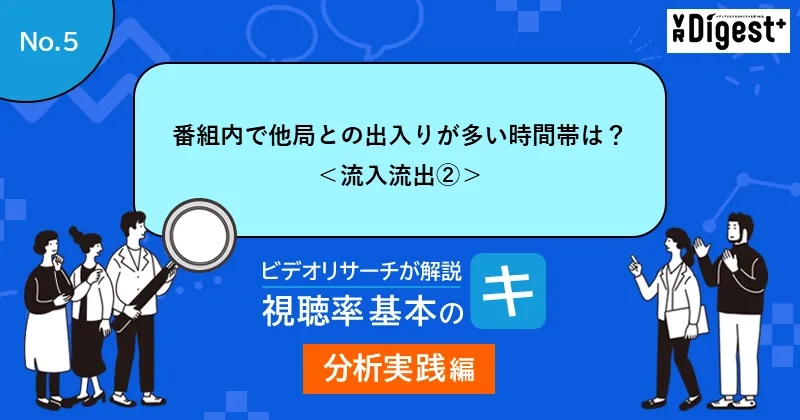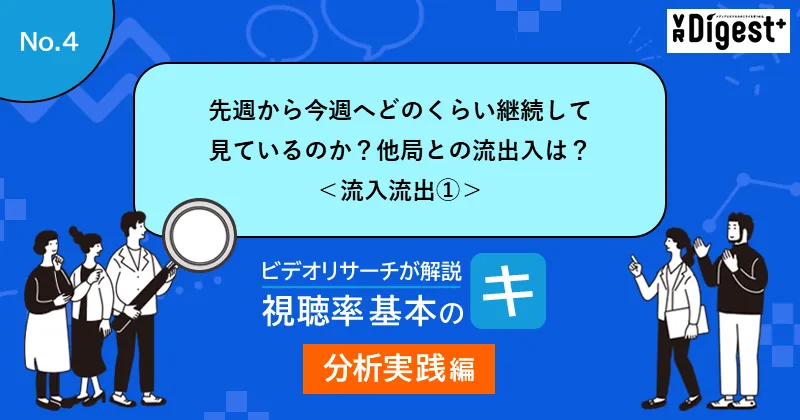てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「岩崎達也」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第58回
いま、日本テレビを「日テレ」と呼ぶことに抵抗を感じる人はいないだろう。
だが、かつて「日テレ」は、どこか蔑称の香りがあった。特にキャリアの長い局員はそれを感じ、口外をはばかられたという。
そんな意識を劇的に変えたのが、1995年に行われた「それって、日テレ。」キャンペーンだ。日テレの番組CMの最後に「それって、日テレ。」と添える。それまで「NTV」「4チャン」など略称は複数あったが、これにより完全に「日テレ」に統一された。
こうしたテレビ局のキャンペーンは、それまで「楽しくなければテレビじゃない」を標榜したフジテレビが行っていたもの以外は、ほとんど行われてこなかった。
それに疑問を感じていたのが、岩崎達也だった。
岩崎は、1992年、35歳で日本テレビに中途入社した。
それまで岩崎は、博報堂でコピーライターとして約11年間、大手企業の広告を手がけていた。
一般の企業は、いかに他社と差別化し、自社のブランド力を上げるかに腐心する。そのために広告があった。だが、テレビ業界のほとんどは、番組制作には最大限の力を注ぐのにもかかわらず、局のブランドイメージを作るということには無頓着だと感じていた。
事実、それを80年代にいち早く行い「楽しくなければ~」のイメージを定着させたフジテレビは、70年代の低迷が嘘のように80年代半ばから90年代初頭まで大躍進した。
ならば、局のブランドイメージを作ることは、番組制作に匹敵するほど大事なことではないかと考えたのだ。
とはいえ、そう考えるようになったのは入社してしばらく経ってから。
そもそも岩崎は、ヒットCMを手がけていた経験から、それを活かして番組制作をしてみたいと日本テレビに転職したのだ。だから、局のブランドイメージ云々より、番組を作ってみたいという思いのほうが強かった。
しかし、配属されたのはやはり経験を買われて広報局宣伝部。せっかくCM業界から転身したのに、同じような仕事を任されることに忸怩たる思いがあった。しかも、最初に与えられた仕事はあまりにも地味なものだった。
実は入局当時、日テレではひとつの一大プロジェクトが立ち上がっていた。そこに参加することになったのだ。
それは、日本テレビと宿敵フジテレビ両局の番組をそれぞれ1日分、つまり合計48時間ひたすら見るというものだった。
それを見ながら、配られた巨大な方眼用紙に一分一秒毎に何が放送されていたか、どんな種類のCMが流れていたか、テロップの出し方、番組の終わり方、番組PRの方法......、そしてその時、どう感じたかなどあらゆることを書き込むように指示された。
「なんでこんなことをやらないといけないんだ」
その意図がわからず困惑する岩崎らメンバーに、プロジェクトリーダーは意図を説明し始めた。
開局から約40年、様々な変遷を経てつくりあげられたタイムテーブルは、複雑な利権やしがらみや、こうでなければといった固定観念が絡み合い、決して合理的とはいえない。
視聴者の生理もスポンサーのニーズも変化してきている中、改めてフォーマットを見つめ直し、視聴率のマイナス要因を取り除き、視聴の流れを最大限考慮した合理的なタイムテーブルを一からつくりたい、と言うのだ。
どんなときにチャンネルを変えようと思うのか、資料や数字だけではわからない、その感覚を知るために、「実際に見る」ということを重視したのだ。それを通して実感したのは、テレビには、数字にはあらわれない画面から出るテイストがあるということだ。同じタレントを使っていても、日本テレビとフジテレビ、TBSでは料理の仕方がまったく違う。画面の明るさからバックの景色、スーパーの入れ方、色、形......、何から何まで違うことがわかった。
そうした細かい違いが重なって、視聴者にとって見やすいか、見にくいかの境界線ができている。
作業が進めば進むほど、日本テレビが抱える課題が浮き彫りになった。
そうしたことを踏まえて「またぎ編成」(フライングスタート)などのアイデアがメンバーの中から生まれてきたのだが、岩崎は自局CMや番組PRの仕方にも問題があると考えた。
それまで、番組PRは自分の番組の中であったり、早朝や深夜といった視聴率が低いところに組み込まれていた。いわば、CMの空き部分だ。
視聴率の高い枠は、高値で売れる枠。そこに自局のCMを流しては営業としてもったいないという考えがあったからだ。けれど、見ている人が少ない時間帯にいくら番組PRを流しても効果はない。
効果がなければ視聴率は上がらず、CM単価が低いままだ。それをなんとしても変えなければならない。けれど、PR枠の新たな捻出は難しい。
思案した末に出した結論は、自分たちの番組の枠内で自分たちの番組PRを流すのをやめることだった。代わりに、他の番組のPRを流した。そうすれば、全体としてはイーブンなうえ、ターゲットが散らばる。
その番組に欲しいターゲットが見ているような番組にPRを置けばいい。それを実現するため、宣伝部が番組PRを一括管理するシステムをつくりあげた。
いまでは当たり前の考え方だが、当時としては斬新だった。
さらに前述のように、以前からやらないのが不思議だと感じていた局キャンペーンも始めることにした。
それまで日本テレビは「存在感が薄い」「堅い感じ」などネガティブなイメージで捉えられることが多かった。それを変えたかったのだ。1993年、日本テレビ開局40年を迎えるのを機に、それを記念するシンボルマークの制作をスタジオジブリの宮崎駿に依頼。一般公募で「なんだろう」と名付けられたそのキャラクターは「みんなの中に、私はいます。」というコピーとともに至るところに"出現"した。
さらに翌年、第2の創業をコンセプトに「Virginから始めよう。」というキャンペーンを実施。このとき、15秒のスポットCMを12秒と3秒にわけ、後ろの3秒にキャンペーンフレーズを入れるという"発明"が行われ、のちに各局も追随する。そしてこの年、日テレは視聴率4冠王を達成したのだ。
だが、様々な調査をしてみると問題点が発覚した。
『クイズ世界はSHOW by ショーバイ‼』『マジカル頭脳パワー‼』『世界まる見え!テレビ特捜部』『進め!電波少年』と当時人気番組は数多くあったが、それが日本テレビの番組だという認識が視聴者に浸透していなかったのだ。
それに危機感を持った岩崎が主導して翌95年に行ったキャンペーンこそが「それって、日テレ。」だったのだ。これにより、柔らかいイメージとともに「日テレ」という名称も急激に浸透していった。
その後も「そんなあなたも、日テレちゃん。」「日テレちゃんパワー」「日テレ営業中」「日テレ式」と、90年代を通してキャンペーンを続けた日テレは、テレビ界の王者としてのブランドを確固たるものに築き上げたのだ。
(参考文献)
岩崎達也・著『日本テレビの「1秒戦略」』(小学館新書)
日本テレビ50年史編集室・著『テレビ夢50年』(日本テレビ放送網株式会社)
<了>