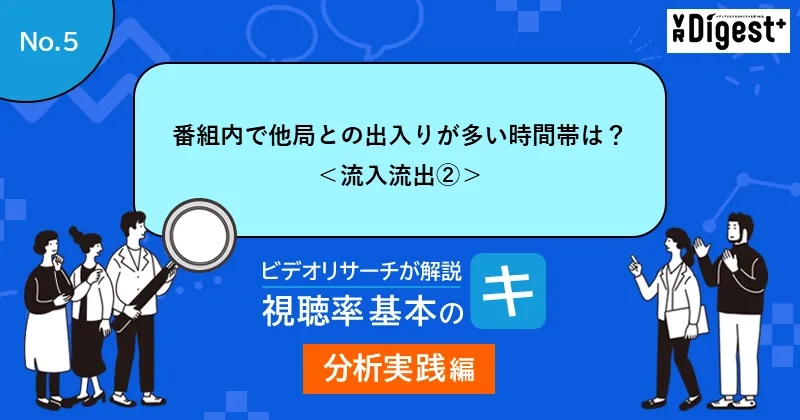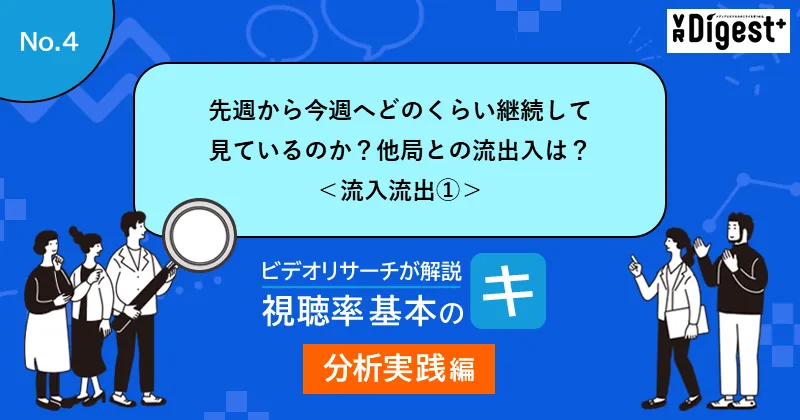てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「杉田成道」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第59回
昨今、Netflixなどの配信プラットフォームからクオリティの高いドラマが次々と配信されていることで、テレビドラマは苦境に立たされている。
よく、こうした配信プラットフォームには潤沢な予算があるといわれるが、どうしても視聴する側は、潤沢な予算=豪華なセットや豪華な出演者だと思いがちだ。
しかし、それは本質ではない。ドラマを撮影するうえでもっとも大きな支出のひとつが人件費だという。それは単に出演者の高額なギャラというわけではなく、スタッフを含めた関係者に対し、拘束期間に応じて支払われる賃金だ。
したがっていかに短い期間で撮影するかが、決められた予算の範囲内に収めることに直結する(それゆえ、天候等の影響を受けやすいロケは極力行われなくなる)。だから、テレビドラマの撮影は無理なスケジュールになりやすいという。
一方で配信ドラマは、その部分にこそ予算を投入する。余裕のあるスケジュールで最大限の能力を引き出し、クオリティを担保しているのだ。
もちろん、テレビドラマにもそうした制作体制でつくられた作品はある。
その筆頭ともいえるのが『北の国から』(フジテレビ)だ。
『北の国から』は1981年に始まった。
それ以前のフジテレビの視聴率は惨憺たるものだった。「振り向けば12チャンネル」などと揶揄されていた時代だ。だが、その前年の1980年、『THE MANZAI』の大ヒットをきっかけにバラエティ番組は若者を中心に支持を集め出し、躍進の時を迎えていた。
ドラマもなんとか立て直さなければならない。
なぜならドラマには優良なスポンサーがつくからだ。だから局の顔となるような象徴的なドラマをつくらねばならないと考えたのだ。
当時ドラマ界では、向田邦子、山田太一、倉本聰、早坂暁という4人の"巨匠"脚本家がいた。彼らに脚本を書いてほしい。だが、何しろ人気の巨匠たちだ。多忙を極めていた。
しかし、倉本聰だけは時間があった。なぜなら、大河ドラマ『勝海舟』(NHK)でNHKと揉め、途中降板。北海道・富良野に移住し、脚本家を事実上引退したような状態になっていたのだ。
プロデューサーの中村敏夫が倉本のもとを訪れ、口説くと、倉本からはこんな答えが返ってきた。
「富良野全体をひとつのスタジオとして、ドラマを撮りたい」
「北海道の四季を撮ってほしい」
すなわち、最低1年にわたる長期の撮影が必須。しかも、雪国の天候の影響をモロに受けるロケが中心になる。前述したテレビドラマの撮影のセオリーとは真逆のものになることは誰の目にも明らかだった。
だが、局の状況が味方をした。70年代のフジテレビは、経営合理化の方針で制作部門を切り離し、子会社化していた。それが士気低下を招き、視聴率低迷の一因になったといわれている。
80年代に入ると、その子会社を局に復帰させる改革を断行し、『THE MANZAI』などが生まれていったのだ。そうした中で、ドラマでも「自分たちが作りたいものを作れ」と旗が振られ、この大型企画が通ったのだ。
通常は撮影をしながら放送していくのがドラマの常だが、『北の国から』はすべて撮り終えてからの放送。半年の放送分を、撮影と編集に2年、打ち合わせやロケハンを入れれば3年、企画から考えれば、放送まで5年を要した一大プロジェクトだった。
『北の国から』の演出を担ったひとりが杉田成道だった。
杉田はもともと松濤館流の空手に熱中していた。大学では100人ほどの部員を束ねるキャプテンとして活躍した猛者だった。
報道を希望し、1967年にフジテレビに入社したが、配属されたのは主にドラマを撮る編成局制作第一演出部。失意はあったが、ドラマ版『男はつらいよ』などの演出で知られる小林俊一に演出助手として就き、テレビ番組作りを習ったのは幸運だったという。
一時は、当初の希望通り報道番組を手がけたり、系列のサンケイ新聞(現・産経新聞)の社会部に出向したりしていたが、ドラマの演出をやりたいという気持ちが強くなっていった。
だが、折しもフジは制作部門を分離していたため、局ではそれは叶わず、杉田は系列制作会社である「新制作プロ」へ。そこで『肝っ玉捕物帳』(1973年)を撮り、ドラマ演出家デビューを果たすのだ。
すぐに全12話の『赤ちゃんがいっぱい』を任され、その後も立て続けに『Yの悲劇』『悪の紋章』『家族サーカス』といった連ドラを手がけていった。 そして、『北の国から』の演出のひとりとして参加することになったのだ。
「杉田死ね! 倉本死ね!」
主人公・黒板五郎(田中邦衛)の息子・純を演じた吉岡秀隆の台本にそんななぐり書きがされていたことは有名な話だ。
たとえば、純が学校から2キロ走って帰って来るという倉本聰による脚本があれば、演出の杉田は、200メートルほど先からカットごとに何度も走らせた。そうやって息を切らせて、セリフがうまく言えないほどの状態にさせる。そんな過酷な演出だった。
そこには「大きなウソをつくのだから、小さなウソはついてはいけない」という倉本の教えがあったのだ。
『北の国から』は、半年間にわたる2クールの連続ドラマだった。前半は裏に山田太一脚本の『想い出づくり。』(TBS)があり苦戦したが、それが終了すると視聴率はジリジリと上昇していった。
当然、続編の話が出てくる。しかし、メインキャストである純役の吉岡秀隆とその妹・蛍役の中嶋朋子が再び撮影するとなれば学校を休まねばならず、出席日数が足りなくなってしまうのだ。
ならば、単発でやるしかない。
そこで倉本が提案したのが「10年単位の家族のドキュメント」だった。
それを聞いて杉田は胸が踊った。それはテレビでしかできないことだと思ったからだ。
たとえば映画『男はつらいよ』の寅さんは、基本的に年をとらない。だが、子供たちがメインのこの作品ならば、純や蛍の成長ドキュメントとして視聴者が見ることができる。親戚の子供に再会するような感覚で、自分たちの人生と重ねて見ることができるのではないかと。
だから、倉本や杉田は、吉岡秀隆や中嶋朋子の実際の"人生"も物語に組み込んでいった。
テレビの作り方のセオリーから逸脱することで、テレビでしかできないことをやり遂げた。そうして2002年まで、20年以上にわたる世界でも類を見ないドラマを生み出したのだ。
(参考文献)
フジテレビ50年史編集委員会・著『フジテレビジョン開局50年史 1959-2009(昭和34年~平成21年)』
(フジ・メディア・ホールディングス/フジテレビジョン)
ビデオリサーチ・編『「視聴率」50の物語 テレビの歴史を創った50人が語る50の物語』(小学館)
志賀信夫・著『映像の先駆者125人の肖像』(NHK出版)
<了>