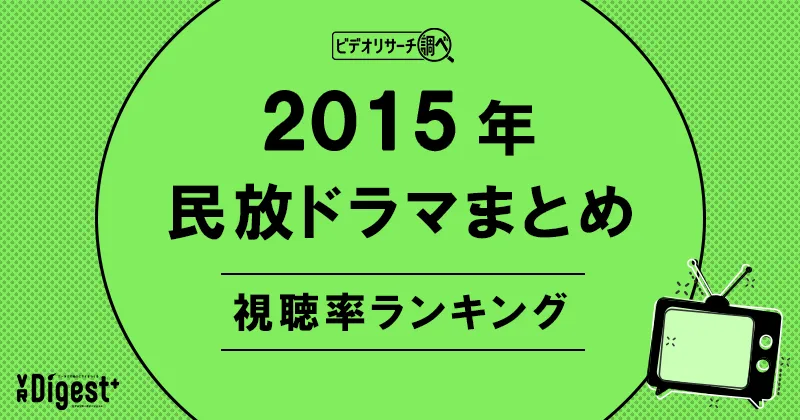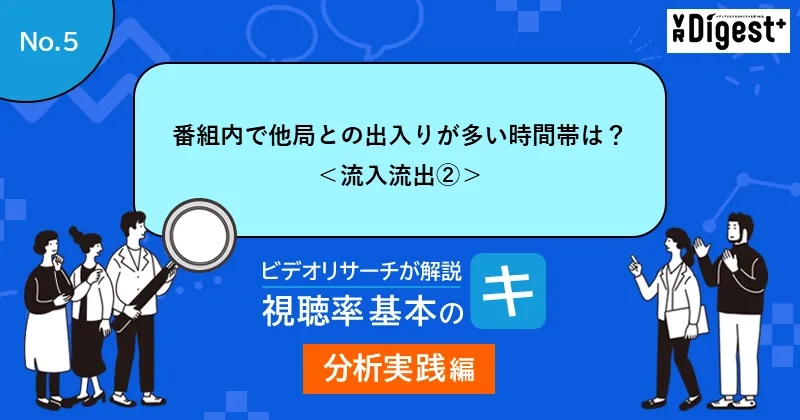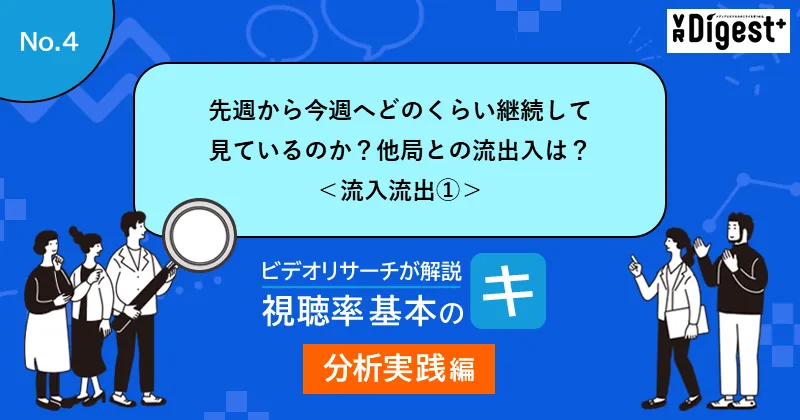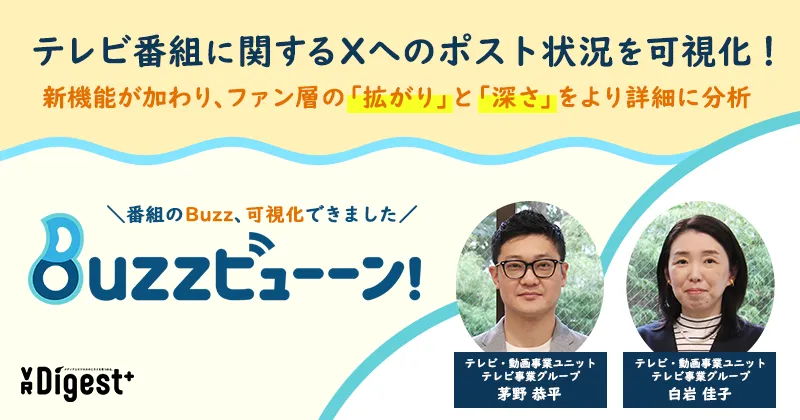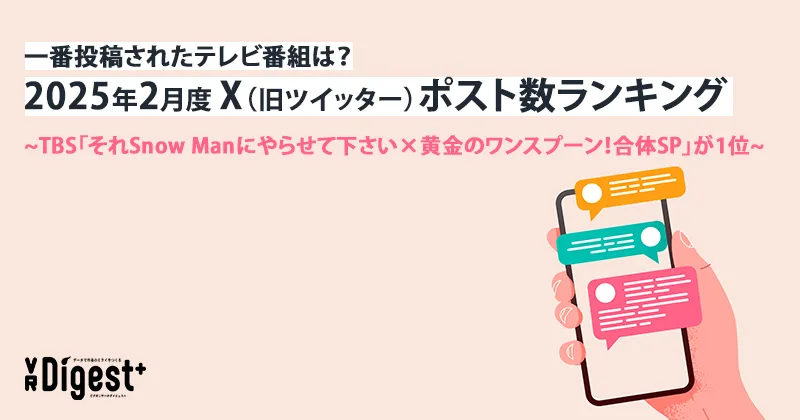てれびのスキマの温故知新〜テレビの偉人たちに学ぶ〜「実相寺昭雄」篇
てれびのスキマの温故知新~テレビの偉人たちに学ぶ~ 第65回
5月2日から「TBSレトロスペクティブ映画祭」が開催される。これは、TBSに残された貴重な映像をスクリーンで上映する企画で、昨年開催された第1回では寺山修司が特集されたが、第2回となる今回、特集されるのは実相寺昭雄。
実相寺といえば『ウルトラマン』や『ウルトラセブン』(いずれもTBS)を始めとする特撮作品の演出で名を馳せ、特撮ファンから絶大な支持を受けるカリスマ的存在の映画監督だ。
「TBSレトロスペクティブ映画祭」では、そんな実相寺がまだ「何者でもなかった」20代の頃に手がけたドラマ・音楽番組やドキュメンタリーを上映する。
映画祭を企画した佐井大紀は、「『電気紙芝居』と揶揄され映画に比べはるかに地位の低かったテレビいう場をあえて選び、試行錯誤を繰り返していた昭和の若者の熱い志を、令和のいま改めてスクリーンで堪能して欲しい」とコメントを寄せている。
実相寺は、高校生の頃にはすでに映画監督を志していた。しかし、早稲田大学在学中に父親が病に倒れ、家計を助けるため、大学は夜間部に移籍し、外務省で働くことになった。そんな中でも映画研究会に入り、並木章らと自主映画の制作も行っていた。
当然、映画会社に就職しようと思っていたが、夜間部の学生には応募資格がなく断念。「仕方なく」ラジオ東京(現・TBS)に入社することになった。
彼が入社したのは1959(昭和34)年。まさに「電気紙芝居」と揶揄され、映画よりもはるかに「下」に見られていた時代だ。同期には早稲田同窓の今野勉、先出の並木や、村木良彦、阿部昭といった、のちにそれぞれの分野で名を成す錚々たるメンバーがいた。
実相寺は、演出部に配属され、『屋根の下に夢がある』『日本剣豪伝』『鞍馬天狗』『駈け出せミッキー』『東響コンサートホール』『日曜観劇会』『東芝日曜劇場』『銭形平次』『日真名氏飛び出す』など様々なジャンルのADを経験していった。
もちろんそれは貴重な経験ではあったものの、同時に「テレビドラマ作りはこんなことでいいのか」という不満を募らせていくようにもなった。 テレビドラマの制作現場の状況への危機感を抱いたのは、実相寺だけではなかった。
そうした「なんとかしなければ」という発露が、同期の昭和34年組でつくった同人誌『dA(ダー)』だった。
同人誌のタイトルは「アシスタント・ディレクター(AD)の同人誌なのだから 『AD』でいいのでは、というところから議論が始まって、これまでのテレビのあり方への異議申し立てを表明するという意味をこめて、ADをひっくり返して『dA』とすることに決まった」(※1)という。
「早く俺たちにもディレクターをやらせろ」という趣旨で発行し、局の内外に配った(※2)と実相寺は回想している。
創刊号に実相寺は、大学へ通いながら勤務していた外務省を舞台にして、役人たちの俗物性を笑いとばすナンセンス・コメディのシナリオを寄せた。主人公が最後にライオンに化身して吼えながら外務省の中を歩きまわるという、のちの実相寺の作風を想起させるものだったという。
また、『私は貝になりたい』などで芸術祭大賞を受賞した岡本愛彦が演出した『血と虹』(1960年)に対するメンバー6人による合評も掲載された。そこで彼らは直の先輩である岡本の演出を酷評しているのだ。
反響は大きかった。局内を中心に売ったが、局外にも広がっていき、これを読んだ同世代を中心としたディレクターたちが、彼らに会いに来たのだ。
その中には、日本テレビの石川一彦や石橋冠、フジテレビの森川時久、NHKの和田勉らもいた。いつしか『dA』のメンバーはまだ1本のドラマも演出していないときから「テレビのヌーベルバーグ」などと呼ばれるようにもなった。
さらに、この6人の共同演出でドラマを1本作らせてみようという企画も持ち上がった。それを提案したのは、誰あろう、彼らに酷評された先輩・岡本だったという。この企画は最終的に頓挫してしまったが、血気盛んな若者たちにチャンスを与える当時の懐の深さを感じさせるエピソードだ。
同期の中でいち早くドラマ演出デビューを果たしたのが実相寺昭雄だった。25歳のときだ。
その少し前、日劇の『佐川ミツオ・ショー』の舞台中継で実相寺は演出デビューをしていた。この頃、舞台中継の演出からスタートするというのが慣例だったという。続いて『さようならー九六ー年、日劇ビッグ・パレード』の舞台中継を担当。このとき、早くも実相寺らしい"実験"を試みている。
「単にショーの舞台を中継する、というのが劇場中継ではなく、劇場そのもの、その場所、その時間、状況を中継するべき」(※2)と考え、ショーを度々中断して、街ゆく人や働く人の写真と、戦争への予感のインタビュー・テープを中継に挟み込んだのだ。
局には「混線してるんじゃないか」といった電話がかかってきて、大騒ぎになってしまい、上司からは激怒された。
それでも初めてのドラマ演出『おかあさん』「あなたを呼ぶ声」にたどり着いたのだ。脚本は実相寺が熱望し、大島渚に書いてもらった。アップを多用したデビュー作を、同期の今野は次のように評している。
「アップの多用は、すでに岡田太郎や和田勉が採用していた手法だが、彼らふたりのアップは、いわば、真正面主義(横顔も含めて)だったのに対し、 実相寺のカメラアングルや高低は、精緻に計算されていて、しかも、アップのままの移動やパンが、緊迫感だけではなくある種のデリカシーを感じさせていた。 それは、実相寺の映像感覚がなせる業だった。『あなたを呼ぶ声』は処女作とは思えない完璧さを備えていた。新鮮なテレビ・ディレクターの誕生だった」(※1)
一方で、脚本を書いた大島渚からは、特に、ラスト・シーンの撮り方について酷評されてしまったという。
その後も、『おかあさん』で、「生きる」「あつまり」「さらばルイジアナ」「静かな恋人たち」「汗」といった作品を演出。その中で様々な"実験"を試行している。常に実験的な精神で新たな表現に挑戦する"戦い"をしていたのだ。
そしてついに『でっかく生きろ!』(1964年)で連続ドラマの演出を任されるのだ。ドラマ演出家として順風満帆......かに見えた。 だが、『でっかく生きろ!』放送開始の少し前に実相寺は"事件"を起こしてしまう。
それは前年の1963年12月25日放送の日劇からの中継番組『トップ・スター夢の歌まつり』でのことだ。
ドラマと並行してこの中継の演出も任されていた実相寺は、舞台の上に、スタジオ用の動き回れるペデスタルカメラを2台あげ、美空ひばりを追いかけた。
彼女の口許をクローズアップし、舌から奥歯まで映した。さらに、歌い始めると、客席奥のカメラをワイドレンズにして、歌手を豆粒のように写し、間奏になるとペデスタルカメラでクローズアップにするなどという撮り方もしたという(※1)。
この挑戦的な演出には、視聴者からも局内からも非難が殺到。さらには美空ひばりの後援会からも抗議が来た。いまでいう"大炎上"だ。
この事件に加え、ドラマでも前衛的な演出が問題視され『でっかく生きろ!』は前半の5回分(とクレジットは変えられたが最終回)だけで降板させられてしまったのだ。ちなみにこの降板に最後まで抵抗したのが寺田農。その結果、以後数年間、TBSから"出禁"扱いを受けることになってしまった。
事実上、"干された"形になった実相寺。しかし、それが彼にとって大きな出会いをもたらすこととなった。 円谷一が演出する『スパイ・平行線の世界』でADを務めたのを機に、自ら志願し、円谷プロへ出向したのだ。
そうして、ドキュメンタリー『現代の主役 円谷英二の巻』で演出に復帰。これで円谷から信頼を得た実相寺は、いよいよ『ウルトラマン』などの演出を任されていくことになった。実相寺が演出した『ウルトラマン』には、それまでの挑戦的で実験的な彼の"戦い"の痕跡も、深く刻み込まれているのだ。
(参考文献)
(※1)今野勉・著『テレビの青春』(NTT出版)
(※2)実相寺昭雄「私のテレビジョン年譜」(実相寺昭雄 オフィシャルサイト)
<了>